
雑誌『rockin’ on』での年代別ロックアルバム特集でランキングされた名盤を、実際に聴いてみて300文字レビュー。
★★★★★ 思い入れたっぷり超名盤!!
★★★★☆ かなりいい感じ!
★★★☆☆ 何度か聴いたらハマるかも
★★☆☆☆ 好きな人がいるのはわかる
★☆☆☆☆ お耳に合いませんでした
ジャケット写真が TOWER RECORDS の商品にリンクしています。
『rockin’ on』70年代ロックアルバム (51位~100位) レビューはこちら。
第101位

Elton John
『Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy』
タイトルはエルトンと相棒の作詞家トニーを表したもの。自伝的要素が強いようだ。
憂いのあるメロディをファルセットを駆使して歌いあげるエルトンはピアニストだが、ギターが映える曲もかなりあるのに気付く。
「Someone Saved My Life Tonight」はコーラスも鮮やかなピアノ・バラード。天にも昇るかのメロディだが、美しいとか癒されるでは片付けられない苦みのようなものがある。
派手な印象のあるエルトンだが、程好い重みのあるメロディは、能天気ではない何かを抱えている。
1曲の中で明るくなったり暗くなったり、表情がコロコロと変わるドラマティックな展開はワクワクするし、何度聴いても新鮮。
人生の浮き沈みのミュージカルのようだ。
★★★★ (2023.11.21)
第102位

The Cure
『Three Imaginary Boys』
時期的に、パンクの洗礼を受けたんだろうけど、明るく潔いパンク・ビートの曲だけがすべてではない。
「10:15 Saturday Night」の無機質なギターのカッティングに諦念まじりの歌声から、突然始まる胸をかきむしるようなギター・ソロに痺れる。
90年代に続くようなダウナーなシューゲイザー・サウンドも見られるけど、「Object」「It’s Not You」の疾走感あふれるロックンロールが文句なくカッコいい。
切っ先鋭いギターを軸に飾り気のないむき出しのバント・サウンドに、ロバートのヘタウマ的ヴォーカルは、ダーク・ヒーローが降臨した感じだ。
流行りに乗ったというか、時代が生んだともいえるけど、その後はオルタナ街道で現在まで生き残る。
★★★★ (2023.11.20)
第103位

Little Feat
『Dixie Chicken』
サザンオールスターズの桑田さんが影響を受けたというバンド。
粘っこいヴォーカルにゴスペル調の女性コーラス。跳ねるリズムにスライドするギター、転がるピアノの音色。
スワンプ・ロックとかサザン・ロックと言われるサウンドの内に秘めた情熱を開放していく様からは、暑苦しいほどの汗がほとばしる。
かと思えば、「Kiss It Off」は都会的な冷たい風が漂い、「Fool Yourself」でも涼しい風を感じるドライブ。
かと思えば、「Fat Man In The Bathtub」ではグツグツと煮えたぎる男が見えてくる。
まるで、サウナで、サウナと水風呂を交互に繰り返して、体を整えていくように。
桑田さんが作る音楽が夏に似合うと言われる源流がここに見える。
★★★ (2023.11.19)
第104位

Frank Zappa
『Apostrophe(‘)』
噂には聞いていた。フランク・ザッパは変態だと。
「Nanook Rubs It」は速射砲のようなヴォーカルに、ギターのざわめき、サックスのゆらめき、先導するドラムは怪しいの極致。
「Apostrophe」はギターだかベースだかサックスだかわからない音が吠え、その上を硬質のギターが暴れまわる。
かと思えば、「Uncle Remus」というピアノが主体の熱く美しきバラードが降臨する。
セリフを交えた演劇的なヴォーカルに、ソウルフルな女性コーラス。コミカルな空気かつスペイシーでもある中、飛び交うSE。速すぎるしどこへ行くのかわからないギターがグリングリンと展開し、ベースはブクブクと鳴る異空間。
こんな俺はどうだい?と変態がこちらを見てる。
★★★ (2023.11.18)
第105位

Mike Oldfield
『Tubular Bells』
20分以上の曲がA・B面1曲ずつ。いかにもプログレの構成。しかしプログレって、テクニシャン同士のバンド・アンサンブルの絶妙さが肝だと思ってたので、これを1人で作ったとは驚き。
映画『エクソシスト』に使用されて、怖い音楽の印象を持つ人が多いらしいけど、僕には神秘的で美しく聴こえた。ベルのような音にアコギやギターが重なり合っていく。何が現れるだろうという好奇心で深い霧の中を歩いていくと、柔らかいタッチのギターがほほを揺らし、突然バチっと火花を散らす。
霧は晴れ、出会いを求めた旅の終盤は、ドラムも入って奇声が入り乱れロック的になり、最後は大道芸のように終わる。
そうか、1人プログレは大道芸だったのか。
★★★ (2023.11.17)
第106位

Carpenters
『Now & Then』
ギラギラした派手なサウンドが主流の70年代前半において、カーペンターズの音楽は異質だったのではないか。
とにかく、カレンの歌声を聴くと落ち着くんだよな。
「This Masquerade」は憂いを含みながらも、作者のレオン・ラッセルと違って、ソフィスティケートされてて聴きやすい。心配事もなんとかなるような気がしてくる。
「Yesterday Once More」の遠き過去を懐かしむ時の切なさ。シャラララのリフレインには涙。
そしてこの曲を起点に、ラジオからオールディーズが流れ出すというコンセプト。明るい曲が多いけど、「Our Day Will Come」はひと際お洒落。
青春の喜びと喪失感が交じり合い、耳馴染みのいいメロディが心にスッと入ってくる。
★★★★ (2023.11.16)
第107位

The Stranglers
『Black And White』
パンクにカテゴライズされることが多いバンドだけど、結成したのは1974年。つまり、後からパンクの要素を採り入れてったということだよね。
「Tank」「Hey!」「Sweden」での、ベースのゴリゴリとしたビートに、キーボードがチープで混沌とした未来感を添える感じ。同時代のパンク・バンドにはこうしたキーボードの使い方は見られなかった。
パンクの潔さを持ちながらも、一癖あるポップなキッチュ感は既にニューウェイヴ的。
純粋なパンクと言えない理由は、特にB面。ポップだったA面に比べると、ノイジーなギターが目立つダーク・サイドへ一気に傾倒する。
流行りのサウンドを自分たちなりに採り入れたら、時代を先取りしてしまったようだ。
★★★ (2023.11.15)
第108位

Mott The Hoople
『All The Young Dudes』
解散寸前だったところをデヴィッド・ボウイの手助けによって起死回生。
WBCで極度の不振に陥りながらも、9回土壇場ここぞというところで逆転のヒットを放った村上選手みたいなものか。指揮して託したボウイは栗山監督か。
自分たちの力を信じることの大事さよ。
ボウイが好きなら、名曲「All The Young Dudes」を歌ったこのバンドには好感を持つのは当たり前で、それ以外のどこに魅力があるのかを探るのが焦点となる。
だけど、「One Of The Boys」はボートラで聴けるデモVer.だとミック・ジャガーみたいな歌い方だったのに、正式Ver.ではボウイみたいな歌い方になってて、結局どうやってもボウイの香りが漂ってしまうんだなと。
ま、仕方ないか。
★★★ (2023.11.11)
第109位

Rod Stewart
『Blondes Have More Fun』
ロッドは眩しすぎて、今まで聴こうとしなかった僕。
ギラギラのミラーボールの光が見えるような「Do Ya Think I’m Sexy?」はディスコ。優雅なストリングスでかなり踊れる。ハスキーに絞る声のAメロの切なさ・苦さも忘れがたい。これは売れるね。
「Ain’t Love A Bitch」はアコギで気ままに歌う自由人。
「Blondes」はホーンも大騒ぎする派手なロックンロール・ブギ。
「Last Summer」はフルートがお洒落なボサノバ。
穏やかな毎日を歌う曲もあるし、再びディスコがあったり、最後は旅立ってしまったり。
華麗なるスターの生活を垣間見せてくれる充実盤。
だけどロッドはそんな日々に満足しているわけでなく、モテる男は辛いよと嘆いてるようだ。
★★★★ (2023.11.10)
第110位
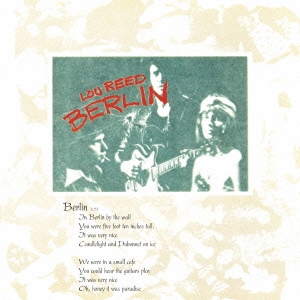
Lou Reed
『Berlin』
東西に分断されていたベルリン。そこで繰り広げられるドラマに思いを馳せる。
荒れたビート、美しいピアノの旋律に息をのむ。優雅なスウィング、煌びやかなグラム・ロックに現れるストリングスの意外性。
「Caroline Says II」のアコースティック・サウンドは美しいメロディを際立たせ、ルーのつぶやくような歌声に耳を奪われる。
「The Kids」で聞こえる子供の泣き声、「Sad Song」のシンガロングは物語に深みを与える。
パントマイムから大芝居へ。陰鬱な世界なのかと思えば、ホッと一息つく場面もあったり。あちらこちらへ綱渡りしていく様に危うさを感じる。
デヴィッド・ボウイがプロデュースした前作よりもボウイとの親和性を感じる。
★★★ (2023.11.9)
第111位

New York Dolls
『New York Dolls』
Spotify未配信のため、聴けませんでした。
第112位

Syd Barrett
『The Madcap Laughs』
元ピンク・フロイドだから、プログレ的な音の構築をする人なのかと思ってた。
ところが、アコギをかき鳴らす曲が多くて、これはフォーク・ロックだね。
「Terrapin」は、ゆりかごのように穏やかなスウィング。
「No Good Trying」は、ギターが色づかせたサイケなサウンドで混沌とした世界。
「Octopus」は、牧歌的でストーリーテリングな味わいはキンクスみたいに思えた。
70年代の作品といっても、70年1月リリースなので、作られたのは60年代サウンド。
ドラッグの影響と、ストレスから精神を病んで、バンドを脱退したという。
制作には多くの仲間が手伝ったらしいけど、孤軍奮闘の切なさを感じるし、孤独を叫んでるようにも聴こえる。
★★ (2023.11.8)
第113位

UFO
『Phenomenon』
マイケル・シェンカー。このアルバムで、クラプトンより先に僕にギター・サウンドの良さを教えてくれた人かもしれない。
序盤はややカントリー・フレーバーで、イーグルスみたいだなと思っていると、「Doctor Doctor」のダイナミズムに満ちたブギでエンジンがかかってくる。
特に素晴らしいのが「Rock Bottom」。感動すら憶えるギター・リフに、かりたてるドラム。キャッチーなサビとスリリングな間奏で、スピードを増していく速弾きギター・ソロ。これに興奮しないロック・ファンはいるのだろうか。
最初から最後まで隙がない。リフもソロも多彩で暴れまわり、魅力的なメロディを歌ってるかのようなギターを満喫したいなら、このアルバムだ。
★★★★★ (2023.11.7)
第114位

Sparks
『Kimono My House』
ジャケットのイメージ通り。パーティーに紛れ込んだ着物姿の女性二人が、花びら舞い散る中で扇子をフリフリ、歌い踊る。そんな世界観。
キーボードが華やかなサウンドを先導し、耳をつんざくギターが金切り声を上げる。
ワルツあり、シャッフル・ナンバーありで、ポップな宴は続く。
ファルセット多用で高音を波打たせる女性ヴォーカルが奮闘する。
ん?スパークスって、女性ヴォーカルだっけ?
「Thanks God It’s Not Christmas」のキーボードの連弾とゴリゴリのベースでの幕開けはプログレのごとき。
「Amateur Hour」はピアノが階段を駆け上がるようなビートを刻む。
でも、歌ってるのが女性なのか男性なのか謎のまま、倒錯した世界は続く。
★★ (2023.11.6)
第115位

Roxy Music
『Country Life』
インパクトあるジャケットは気になるけど、タイトルからして、のどかなサウンドを聴かせてくれるのかなと思ってたら。
「The Thrill Of It All」は刺激的なギター、切迫感あるストリングスで攻めてきます。サビで浮遊感あるメロディになる意外性も。
ギター、ベース、ドラム、ピアノが一体となるスピード感ある演奏に酔う。
ブライアン・フェリーの時にコミカルで退廃的なヴォーカルは、うねるリズムとギターに絡みつき、バラードも一筋縄ではいかない。
アルバムのタイトル、ジャケットからは想像しえなかったサウンドが熱い塊となって展開されていました。
全然のどかじゃない。心をぐわぐわ揺らし、ぐつぐつと煮えたぎらせるエネルギーに興奮。
★★★★ (2023.11.5)
第116位

Jethro Tull
『A Passion Play』
ジェスロ・タルって、人の名前かと思ってた。
英国プログレ・バンドの6作目で、アナログA・B面に各1曲ずつの構成。
アンビエント?な穏やかな効果音から、フルートが朗らかな雰囲気を醸すマーチに。次はフラメンコな音世界…。
キーボードとアコギの響きはイエス風、怪しげなサックスはクリムゾン風だったりしながら、躍動感あふれるピアノ、暴れるドラムと、フィーチャーされる楽器がかわるがわる出てくる構成。
ヴォーカルは比較的スマートだけど、終盤は演劇的なセリフが続いたり。
長尺なのはプログレの特徴だけど、トーンがバラバラのサウンドがつぎはぎされている展開は、異文化を次々と見せられる世界一周旅行に出かけているかのよう。
★★★ (2023.11.4)
第117位

Buzzcocks
『Another Music In A Different Kitchen』
興味のあるものを見つけたら、周りのことなど一切気にせず一直線に突き進む。その信念と行動力はうらやましい。
「Fast Cars」を筆頭に、弾丸のごとき強烈なビートの爆発力、ギターのキレ味も鋭い曲の数々。
「Get On Our Own」はオウオウオウ、「I Don’t Mind」はアイアイアイと、甲高い声でくり返されるヴォーカルが面白い。
「I Need」など、キャッチーで人懐っこいメロディは愛らしくもある。
他のパンク・バンドに似ているようで、どれとも違う聴きやすさ。
性急すぎるビートは、どこまで生き急ぐんだと心配にもなるが、その衝動こそがパンク。
怖いものなしで一気に駆け抜けるが、彼らが走ったのはメイン・ストリートではなく裏道だった。
★★★ (2023.11.3)
第118位
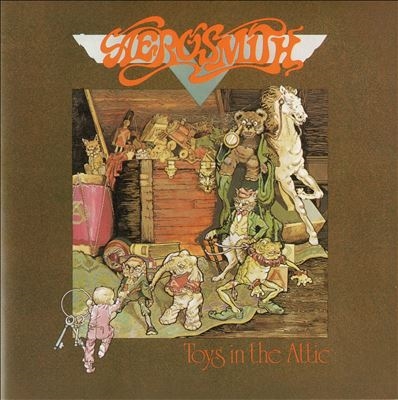
Aerosmith
『Toys In The Attic』
超有名バンドだけど、スティーヴン・タイラーのワイルドすぎる見た目が派手で下品に感じてしまって、敬遠してた。
「Toys In The Attic」はディープ・パープルの「Highway Star」を思わせる、いきなりアクセル全開で疾走感ありの、いかにも幕開けの曲。
「Walk This Way」は僕でも知ってた。強烈なギター・リフ、速射砲のヴォーカル。ランDMCのカヴァーとも併せ、誰もが知ってる曲。
「You See Me Crying」はピアノ主導のバラードで、アルバムの中では異質。ファルセットも使いながら、下品さを覆す、泣いてるようなヴォーカル。
想像してたほどイヤらしい感じはなかったし、クセもそれほど強くなく、意外と正統派。
聴かず嫌いはダメだね。
★★★ (2023.11.2)
第119位

The Slits
『Cut』
やっぱり目を引くのはこのジャケット。今の時代ならアウトだな。もちろん当時でも賛否両論あったでしょう。
こういう、外見で目立ったことをすると、肝心の音楽のことを軽んじられてしまうリスクもありますが、それを承知で勝負にいった彼女たち。
サウンド的にはシンプルで、ほぼ3ピース。ギターはソロよりもカッティング中心。
「Newtown」等、ダウナーな曲が多い。
「Love Und Romance」は性急なビートに企みありげなコーラスとチア・リーディング的なコーラスとが交互に訪れて面白い。
「Typical Girls」はリズムがコロコロ変わり、ピアノの連弾が盛り立てます。
パンクの流れを受けてのレゲエやダブの楽曲の数々。これは女版クラッシュだね。
★★ (2023.11.2)
第120位

Brian Eno
『Here Come The Warm Jets』
イーノって、アンビエントの人だと思ってたけど、聴いてみて驚いたのは多面性。
「The Paw Paw Negro Blowtorch」では、電子音が飛び交う。面白い音を探してたのだろう。
「Baby’s On Fire」は攻撃的なギターが唸りまくるが、アンビエントの萌芽も感じる。
「Driving Me Backwards」は不穏なサウンドに、調子っぱずれにもとれるヴォーカルの不安定さ。
他にも、オールディーズのように心和ませる曲、知的で真面目な曲、気難しい曲。
この人はポップで面白い人?不気味で怖い人?いったい何を考えてるんだ?と、捉えどころがない。でも、そんな多面性の人って、気になるとどんどん惹かれていく。
ニューウェイヴに聴こえるけど、74年の作品だとは。
★★★ (2023.11.1)
第121位

XTC
『Drums And Wires』
“キッチュ”という言葉を聞くと、XTCが思い浮かぶ。正確な意味は知らないけど。
アンディのテンション高いヴォーカル、心を開放するギター、ワクワクするベースとドラムのビート。
サイケはグニョグニョだけど、「Helicopter」はクネクネしたサウンド。
「Reel By Reel」はキャッチーなサビの後のギター・ソロとコーラスがハイな気分を一段階上げる。
疾走感もあり、パンクを進化させた勢いが最後まで落ちないアルバム。
一貫してポップではあるんだけど、そう易々と理解されてたまるかという気概と遊び心に溢れている。エクスタシーを得るのは簡単ではない。
“キッチュ”の意味を辞書で引くと「まがいものをわざと楽しむ、悪趣味」とあった。
★★★★ (2023.10.31)
第122位
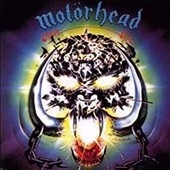
Motörhead
『Overkill』
モーターヘッドって、ヘヴィメタかなあなんて思ってた。
「Overkill」でドコドコと連発される音が胸を打つ。ツーバスかなあ。
「Stay Clean」の昇りつめていく感じ、「No Class」のギター・リフとドラムでリズムのうねりを作っていく感じ。「Tear Ya Down」のスピード感。
「Limb From Limb」は終焉に向かって力を振り絞っていく大作。
ノドを潰すように歌うレミー、腹に響く低音のバスドラと、空気をかき乱すシンバルの破壊的なドラムを叩くフィル・テイラー。
ヘヴィメタほどのギラギラした様式美は感じられなかったので、ちょっと違うのかな。
こんな演奏をするには、圧倒的なパワーが大切なのはわかる。爆音で聴いたらスカッとするだろうね。
★★★ (2023.10.30)
第123位

ZZ Top
『Tres Hombres』
ZZトップって、髭ボーボーのおっさんの割に、爽やかなコーラスを聴かせる明るいアメリカン・ロック、という印象でした。
しかも80年代のイメージだったのに、これは73年の作品?
「Waitin’ For The Bus」を聴いてビックリ。ハード・ロック並みのパワフルなギター・リフ、そしてブルース・フィーリング溢れた流麗なギター・ソロ。
「La Grange」も、前のめりのリフで引っぱる歪んだギターの音色が気持ちいい。
もうこれは完全にハード・ロック・バンドだ。
この頃は、髭も伸ばしてなかったとのこと。
あのおっさんたちは、若い頃、こんなにシャープでイケてたんだ、とイメージを覆された。
よく知らないのに、勝手な偏見を持つのは良くないですね。
★★★ (2023.10.29)
第124位

The Specials
『The Specials』
はしゃいでる姿を見られるのが恥ずかしくて、どうしてもノリ遅れてしまう僕。
レゲエのBPMを速めたのがスカのイメージ。
パンクからラップへと繋がるような早口ヴォーカル。ギターの浮ついたピッキング。地を這うベース・ライン。
「Nite Klub」は、どこかのパブの喧騒から始まる2トーン・スカ。生々しい音で荒々しい演奏にホーンが気持ちを上向きにさせる。体は自然に右へ左へ。ワン・ツー、ワン・ツー。それが2トーンの特徴か。
「Monkey Man」「(Dawning Of A) New Era」はアイアイアーと集団で、そしてグイグイと攻めてくる。
こうして、多少強引なくらいに引っ張ってくれるとありがたい。一緒に踊らにゃ損、ノリが大切だと気付かせてくれる。
★★ (2023.10.29)
第125位
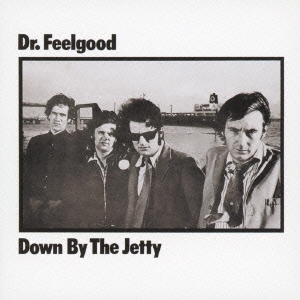
Dr. Feelgood
『Down By The Jetty』
学校で目立つ一軍的存在ではなくて、我関せずといったところでたたずみ、寡黙でいて物知りで、一目置かれた存在感を放つ先輩。
キレ味鋭いギター、ひたむきにビートを刻むドラムとベース。ときおり吹かれるブルージーなハーモニカ。
華々しいサウンドが主流になっていく70年代、ミニマルなロックンロールを鳴らしたバンド。
「Twenty Yards Behind」はスカのリズムが練り込まれていて新鮮さも感じるが、基本的にはどれも10年くらい前の音楽のよう。あえて言えばモッズかパブロック的。
トレンドに流されない男たち。なんてったってモノラル勝負。時代遅れも、貫く姿勢があると一周まわってカッコいい。次元大介のような、ああいう男にも憧れる。
★★ (2023.10.28)
第126位

The B-52’s
『The B-52’s』
パンクからニューウェイヴへ。急速に時代が移ろう中、どれだけ突飛なことをやれるか合戦が繰り広げられてたであろう。
陰鬱なギター・リフが先導し、キーボードのおどろおどろしい音はニューウェイヴの肝。
ヒステリックにぶっ飛んだ女性ヴォーカルは好き嫌いがわかれるだろう。
男女のツイン・ヴォーカルも聴き応えあると思ってたら、なんと女性ヴォーカルは2人いた!
「Rock Lobster」の疾走するビートはロカビリーの進化形。ノドを震わせて、オノ・ヨーコみたいに歌うのはケイトかシンディか。終盤はまるで動物的。
ストリートで演奏する彼らの前を、眉をひそめて通りすぎてく通行人の姿が見える。そんな様子さえも楽しんでいるかのよう。
★★ (2023.10.28)
第127位
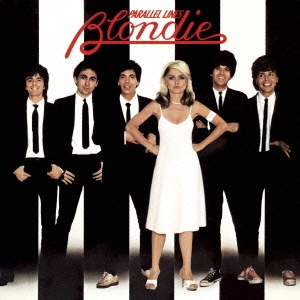
Blondie
『Parallel Lines』
学生時代、憧れの女の先輩がいたよね。
「Hanging On The Telephone」の圧倒的なビート感での押し切り。
「Will Anything Happen」はパンクのビートにストリングスの厚みが加わって不思議な安定感。
全米No.1を獲得したという「Heart Of Glass」は僕でも聴いたことあった。ファルセット交じりで爽やかに歌われるこの曲は、ディスコティックなサウンドでキャッチーなリフレインがとても華やかで、心もフワフワ。
78年という時代を考えると、パンクかニューウェイヴかと括りがちだけど、意外と正統派のロックンロール・バンドなのかも。
真っ白なドレスに身をまとった先輩に「私についてきて!」と言われれば、男子は張りきって後を追うしかない。
★★★ (2023.10.27)
第128位

The Cars
『The Cars』
Carsというバンド名、ハンドルを握る女性のジャケット写真。ドライヴに適した音楽かと想像。
イントロからしてニューウェイヴ感満載。パンクの時代の波を受けて、もっと自由に面白いものをやっていいんだと開き直って作られたサウンド。
「My Best Friend’s Girl」のビートルズみたいなギター・フレーズに耳を刺激されたり、「Don’t Cha Stop」のノリが良くキャッチーなサビにイキの良さを感じたり、「All Mixed Up」のクイーンみたいなコーラスが印象的な美しい展開に圧倒されたり。
シンセがプログレみたいだったり、ハード・ロックの香りもしたり。
70年代の雑多なポップ・ミュージックの総まとめといったところ。
車のスピード出しすぎ注意。
★★ (2023.10.27)
第129位

Scorpions
『In Trance』
仕事でペアを組んだ人と、声をかけあって作業を分担したり、二人がかりで取り組んだりしたりして上手くいくと、一人の時より充実感を感じたりする。
つんざく叫び、驀進するドラムとギターでリズムの渦を作っていく「Dark Lady」や「Robot Man」はテンションが上がる。
しかし、このバンドの肝はウリ・ジョン・ロートとルドルフ・シェンカーのツイン・ギター。
リフとソロを分担したり、ソロの応酬があったり、時にハモらせたりと、縦横無尽の弾きまくりのギターの音色に心奪われます。
ハード・ロックのバンドって、一人のカリスマ・ギタリストが引っ張っていくイメージがあるけれど、ここでは二人が共に高めあうプレイをしているのが魅力。
★★★ (2023.10.26)
第130位
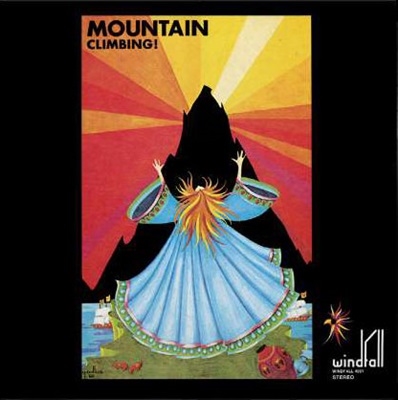
Mountain
『Climbing!』
うっかりクリンビングと読んでしまっていて、なんだろうと思ったけど、マウンテンだからクライミングかと、ようやく気付いた。
時は1970年。まだ登っていく者もわずかだったハード・ロックという山。
「Mississippi Queen」でのパワフルなギター・リフに野太いヴォーカルは、王道。
パルコム・ハルムがハード・ロックをやったらこんな感じみたいなサウンドの曲もあったり、時にアフリカ的、時にインド的な音も聴こえてきたり。
荒々しさに満たされているものの、一本調子ではなく、緩急の付け方が上手い。山の天気は変わりやすいというところか。
頂上に達したと思ったら、隣のレッド・ツェッペリンはさらに高い山にいた。この差はなんだろう。
★★★ (2023.10.26)
第131位
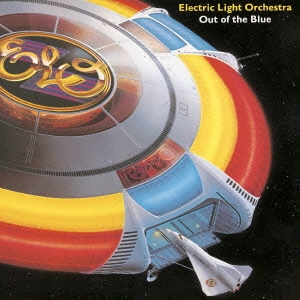
Electric Light Orchestra
『Out Of The Blue』
雨は好きじゃない。濡れるのは面倒だし、雨漏りも心配だし。
「Turn To Stone」「Sweet Talkin’ Woman」...かき鳴らすアコギ、分厚いオーケストラ、優しい歌声にファルセットのコーラス。とことんポップに仕上げるのがジェフ・リンの職人芸。
「Across The Border」「Birmingham Blues」のようなオールド・ロックンロールなビートも、オールドに思わせないアレンジの妙。
今作以降、シンセを多用して徐々にオーケストラから離れていくことを思うと、オーケストラとの融合という意味ではアイデンティティの到達点となった2枚組アルバム。
雨の日から一転、「Mr. Blue Sky」での晴れ晴れとした青空にワクワクするのは最高の気分。
★★★★ (2023.10.25)
第132位
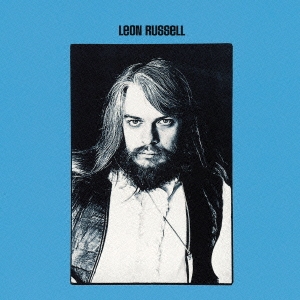
Leon Russell
『Leon Russell』
サザンの桑田さんが歌い方に影響を受けてると聞いて、レオンに興味を持ちました。
「A Song For You」の、しゃがれてノドをぐりぐり回すような歌い方。ピアノとストリングス、かすかにホーンというシンプルなサウンドで、美メロなのにどこか胸騒ぎのする曲に惹かれました。
跳ねたリズムに転がるピアノ、チョーキングし、スライドしまくるギター。これがスワンプ・ロックなのか、と。
「Roll Away The Stone」なんて象徴的で、まるで打楽器かのようにピアノを叩き弾く。サビ終わりのメロディと歌い方は、ホント桑田さん。
パーティーのように大人数でテンション上げた曲もありますが、仙人のような風貌でクセの強いレオンはやはり孤高の存在。
★★★ (2023.10.24)
第133位
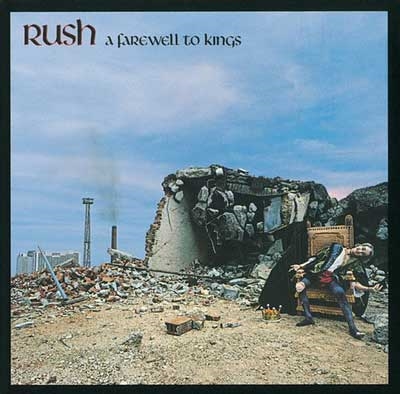
Rush
『A Farwell To Kings』
叙情的なアコギにゴリゴリのベース...と思ったら、え?女性ヴォーカリスト?と思うほどのハイトーン・ボイスでシャウト。
そんな風に始まったRushはカナダのバンド。
「Closer To The Heart」のようにコンパクトにまとまった曲もあるけれど、ハード・ロックとプログレを行ったり来たりするサウンド。
「Cygnus X-1 Book : The Voyage」は宇宙空間を旅するような、メタリックでスペイシーな肌感。難解な曲かなと思っていると、ノリのいいビートに変わったり、トリッキーなギターが目の覚めるようなストローク。激しい展開で表情がコロコロ変わります。
イエスがハード・ロックをやったなら的でもあり、ザ・フーのロック・オペラ的でもあります。
★★ (2023.10.23)
第134位
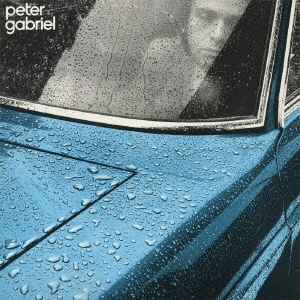
Peter Gabriel
『Peter Gabriel』
雨の中の車の男という陰鬱なジャケットから想像してたのとは違って、甲高いヴォーカルに驚きました。
「Modern Love」はストーンズみたいな派手なギター・サウンド、「Excuse Me」は聖歌隊から一転コミカルで演劇的なヴォードヴィル・ソング、「Humdrum」は厳かで真面目な感じ。
この3曲の流れを聴いて、これは奥深く、幅広いアルバムだと直感。
他にも長尺のギター・ソロのブルース、踊れる曲もあるし、ラストの「Here Comes The Flood」はドラマティックで感動的に盛り上げるサビはクイーンみたい。
一曲ごとにいろんな場面を見せられて、一度聴いただけではイメージが固まらない。一体なにを聴いてたんだろうと混乱もする面白さがありました。
★★★ (2023.10.22)
第135位

The Moody Blues
『Every Good Boy Deserves Favour』
童話の一場面みたいなジャケットの雰囲気からして、プログレなのかと思ってたけど。
「The Story In Your Eyes」は、フォーク・ロックなメロディにサイケなギターがサウンドの核。ノリも良く、終盤はピアノと共に駆け上がっていく感じが盛り上がります。
全体的に、リード・ヴォーカルがダブルになって響いていて、その素朴さも相まって、なんだかサイモン&ガーファンクルに似ている気がします。
ラストで、プログレ的な大展開を見せる「My Song」が白眉。正直、アルバム中盤は地味な印象を受けますが、この曲が最後に暴れてくれるため、大作を聴いた感。
フォーク、サイケ、プログレと交じり合った音楽は、70年代と言うよりも、60年代の残り香。
★★ (2023.10.22)
第136位

Camel
『The Snow Goose』
これもプログレと言っていいのだろうな。
ただ、普通プログレに備わっている重厚感や緊張感はほぼ感じなくて、明るいキング・クリムゾンといったところ。
「Rhayader」は、ところどころ現れる軽い音のフルートが、ほのぼのとしてて、なんだか気持ちまで軽やかに。
基本的にはほぼ全曲インストゥルメンタルなのですが、「Migration」「Preparation」では、「♪ Da Du Da」みたいな、歌詞のないヴォーカルというか、コーラスが現れて、ちょっとしたアクセント。
各曲、目まぐるしい展開はなかなかドラマティックだとは思うけど、リード・ヴォーカルのメロディは無いため、とりとめがないというか、つかみどころが難しく、クラシックに近いかも。
★★ (2023.10.22)
第137位

The Runaways
『The Runaways』
女性だけのバンドは珍しかった時代。
でも、日本ではかなり売れたそうで。
「Cherry Bomb」はハード・ロックのようでもあり、パンクの先駆けのようでもあり。
骨太でパワフルな「Blackmail」では各楽器に見せ場があり、かつアンサンブルも楽しめたのですが、「American Nights」「Secrets」では、突然現れるピアノにハッとさせられました。
女性ヴォーカルに女性コーラスというのは意外と新鮮で、まさしくガールズ・バンドだと実感。
バラードなど一切なく、ロックンロール一本勝負の潔さ。
女性だけで本気でロックしようとする姿勢がカッコ良く、ライヴが観たくなりました。シェリーがほぼ下着姿という格好で歌ってるからという理由だけでなく。
★★★ (2023.10.22)
第138位

Throbbing Gristle
『20 Jazz Funk Greats』
インダストリアルってなんだ?
ノイズと呼ぶには綺麗すぎるが、ベース音や電子音が右へ左へと動き回る。空気中に漂う粒子を表現化したかのよう。
「Hot On Heels Of Love」を聴くと、テクノの一種なのかなあとも思う。
「Persuasion」で、ようやくメロディらしきものが出てきますが、朗読にも近いものが、鳥の鳴き声のようなサウンドと共に行きかう。
「What A Day」に至っては、なにかの儀式で集団で祈祷してるようなトランス状態。
アンビエント・ミュージックというほど環境に優しい音楽でもない。
このような音遊びは、どこからどうすれば、構築できるのか。設計図でもあるのか。
これもロックなのか?だとしたらロックの道も険しいなあ。
★★ (2023.10.21)
第139位
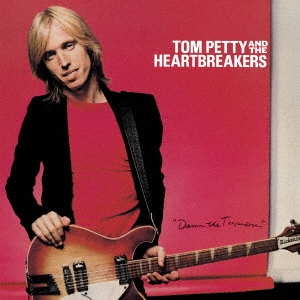
Tom Petty & The Heartbreakers
『Damn The Torpedoes』
トム・ペティとボブ・ディランの声の違いがいまだに聴き分けがつきません。
そんな、粘っこくぶっきらぼうでヘロヘロなヴォーカルに乗って「Refugee」の泥臭く熱いギター・サウンド。
「Here Comes My Girl」のピアノと煌びやかなギターが絡むサビ。
そう、トム・ペティの音楽は煌びやかなのだ。12弦ギターを使ってるからなのか、開放感にあふれています。でも、フォーク・ロックとは違う、紛れもなくロックンロール。
肩の力が抜けてるのにも関わらず力強いトム・ペティの音楽が、アメリカでの人気に比べると日本で知名度低いのは永遠の謎。
だけど、いけそうでいけないもどかしさは感じるし、日本人には刺さりにくい何かを内包しているのかな。
★★★ (2023.10.20)
第140位

Japan
『Quiet Life』
何故グループ名がJAPANなのか。東洋的なサウンドなのか。興味津々。
「Quiet Life」は、どこか冷めた目をしつつ、テクノを下敷きにしたようなビート感に粘っこいヴォーカル。これがイケてる都会の生活か。
「Despair」はデカダンな雰囲気に妖しげなサックスの独壇場。
くり返し弾かれるギターに中毒性がある「Alien」に、ゆったりとした「The Other Side Of Life」。
妖艶なグラム・ロックから退廃的なヨーロッパへと傾倒したデヴィッド・ボウイからの影響を感じます。
グラム・ロックは、来たる80年代にはこうなっていくよと予見したようなサウンド。
ボウイがヨーロッパなら、俺たちはJAPANでいいんじゃね?くらいの気持ちで命名したのかも。
★★★ (2023.10.18)
第141位
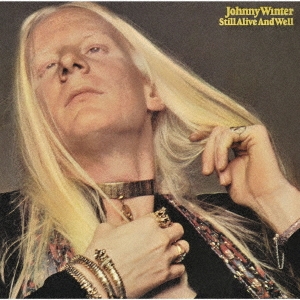
Johnny Winter
『Still Alive And Well』
ルーツのブルースから、ロックンロールへと振り切った頃のアルバム。
1曲目「Rock Me Baby」から、ドタバタうるさいドラムに負けじとギター弾きまくって、これ1発でぶっ飛んだ。超興奮!
「All Tore Down」「Rock&Roll」では火を点けるようなリフに稲妻ソロが唸りまくる。永遠に聴いていたい。
基本3ピースの演奏はライヴ感あるし、ブギ調、カントリー調、がっつりブルースもいいけれど、やはりスピード・ナンバーでの速弾きソロが熱くさせます。
クラプトンにも引けを取らないし、ツェッペリン・ファンにも受け入れられそう。
ブルース・ロックと言うけれど、これだけ歪んだギター弾きまくると、ハード・ロックかヘヴィメタかという気もします。
★★★★ (2023.10.18)
第142位

Daryl Hall And John Oates
『Bigger Than Both Of Us』
Spotify未配信のため、聴けませんでした。
第143位

Bay City Rollers
『Rollin’』
一世を風靡したグループというと聴かなければとは思うのだけれど、ブームになりすぎて、いささか一発屋的なイメージがあると、今さら聴くのもどうかと尻込みしてた。
大ヒットした「Saturday Night」もちゃんと聴いてみると、ぐいぐい来るスピード感に歪んだギター。もっとナンパなものだと思ってたけど、意外とちゃんとロックしてた。
同系統の「Remember」も派手でキャッチー。
カヴァー曲「Be My Baby」はグラム・ロック的なアレンジ。
かと思えば「Just A Little Love」は素朴なフォーク・ロックで、こういう繊細な面もあるんだなと。
デビュー直後に全米No.1というのは改めてすごいとは思うけど、急いでヒットしすぎた負の部分も垣間見た。
★★ (2023.10.18)
第144位

U.K.
『U.K.』
元キング・クリムゾンのジョン・ウェットンとビル・ブルーフォードが中心になったバンドと聞いて、期待がふくらみます。
「In The Dead Of Night」は、クリムゾンよりもポップだなと思っていると、息つく暇なく「By The Light Of Day」に突入。この辺の繋がりは流石プログレ。
「Presto Vivace And Reprise」や「Metal Medication」はベースがゴリゴリ言ってるし、縦横無尽のキーボードは、むしろイエスっぽい。
「Time To Kill」は目まぐるしく様相が変わる展開からキーボード、ギターと見せ場を作ってクライマックスに向かい、ヴォーカル・メロディが出てきた時は感動。
プログレの衰退に抗うように、一致団結してプログレの魂を紡いだ作品。
★★★ (2023.10.17)
第145位
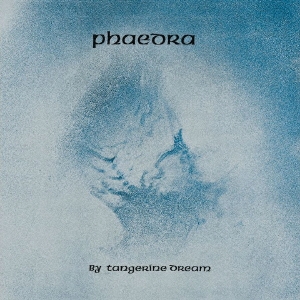
Tangerine Dream
『Phaedra』
いったいどこに迷いこんだんだ?
ドイツのグループと知って、クラウト・ロックの元祖かなんかかなと想像してたけど、聴こえてきたのはアンビエント・ミュージックで、不安に苛まれます。
穏やかな空気に包まれていたかと思えば、また急に強い風が吹いてきたりして落ち着かない。
ビヨンビヨンとか、ポンポコポンとかテロリーンとか、訳の分からぬサウンドに取り囲まれます。
3分間のポップ・ソングが好きな僕からすれば、これはまだ曲が始まってもいない状態。
こういう音楽は、どこが着地点なのかわからない。
で、わからないまま終わった。
これはロックだったのだろうか。
ふと気付く。
タンジェリン・ドリーム?
そうか、夢だったのか。
★★ (2023.10.17)
第146位
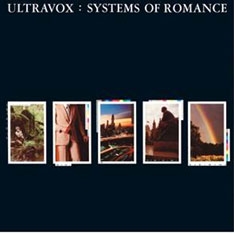
Ultravox
『Systems Of Romance』
ウルトラヴォックスってパンク?ニューウェイヴ?くらいの認識だったけど。
「I Can’t Stay Long」「Someone Else’s Clothes」から聴こえてくるのは、抜けの良いドラムの音(リズム・マシンか?)に追随するベース、ハードなギターで、空に舞い上がって溶け込んでいきそう。
「Some Of Them」は、クラッシュぽくて、同時代のパンクと共に生きてきた証も。
もっとテンション高かったらXTCみたいになるかも。
とてもヒットしたとは言えないセールスだったけど、ここにあるのは、新しい扉を開く瞬間を垣間見るような、ここで蒔いた種が後に花開く予感と発見の数々。
「Quiet Men」なんて、21世紀のエレクトロ・ポップにまで繋がっているようです。
★★★ (2023.10.17)
第147位

Chicago
『Chicago X』
なんだろう?この湧き立つ気持ちは。
理由はすぐ判明。1曲目からファンキーなブラスが煽りまくり、自然とノッてしまうのです。
しかも、ただ煽るだけでなく、「You Are On My Mind」では、ピアノとベース主導で抑えたヴォーカルで歌われる中にもブラスが溶け込み、お洒落に踊れるものになっているのです。
全編を通して、ブラスの効果的な使い方、意外な使い方を熟知していて、ブラス・ロックの面目躍如。
それでいて、ブラスが煽らないバラードの「If You Leave Me Now」が全米1位になったというのだから面白い。
アルバムの邦題が『カリブの旋風』なのは、軽快なダンスの「Another Rainy Day In New York」の印象的なマリンバの音色からかな。
★★★ (2023.10.17)
第148位

Steve Miller Band
『Fly Like An Eagle』
軸は骨太にかき鳴らすギターだけれど、序盤のスペイシーなサウンドが忘れられません。
「Fly Like An Eagle」は、空を飛ぶ鷲が優雅でありつつも、何か獲物を狙っている様子が見えてきます。
「Serenade」はギターのストロークがカッコ良く、心が湧きたっていると、終盤、獣が吠えるようなヴォーカルが。
「Sweet Maree」はハーモニカと共に、一気にアコースティック・ブルースの世界へ。
「The Window」の乾いたドラム、刻むアコギ、浮遊感あふれるキーボード。けだるく虚ろに、異世界へ誘われます。
古くから親しんできた懐かしい音楽と、新しく生み出そうと意図するサウンドが混ざり合い、過去と未来を行き来しているかのような作品。
★★★ (2023.10.16)
第149位

Foreigner
『Foreigner』
アメリカっぽい大らかさとイギリスっぽい繊細さがあると思ったら、メンバーは米英混成なんだって。しかもキング・クリムゾンの元メンバーがいるとは。
大ヒットした「Feels Like The First Time」がいきなりいいけど、「Cold As Ice」のドラマティックなブギに心踊る。
「At War With The World」のリフを聴いてると、ギターを中心としたバンドなんだと実感。
「I Need You」で幕を閉じると、満足感と寂寥感に同時に襲われます。
全編通して、1度聴いただけで心掴まれるキャッチーなメロディに華やかなサウンド。売れ線と言われようが、狙って作れるのは大したもの。
このわかりやすさ最優先の姿勢が、後の80年代の産業ロックを産んだのかなと。
★★★ (2023.10.15)
第150位

Wishbone Ash
『Argus』
ジャケットの兜の騎士(ギリシャ神話の巨人)に、曲名のKing、Warrior、Swordという単語を見ただけで、世界観に引き込まれます。
爽やかなアコギの音で幕を開けたと思ったら、「Sometime World」2分半くらいからテンポが変わってスピード感抜群。そこでギター・ソロがうねるというゾクゾクする展開。
ラスト曲「Throw Down The Sword」では、いつまで泣いとんの!というくらいのツイン・ギターの絡み泣き。
聴きどころはギターだけでなく、意外だったのはヴォーカルやコーラス・ワークに敬虔な気持ちにさせられたところ。
偉大なものの力に圧倒される諦念と、なんとかそれに抗おうという心持ちに、こちらまで奮い立たされます。
★★★★ (2023.10.14)


コメント