
雑誌『rockin’ on』での年代別ロックアルバム特集でランキングされた名盤を、実際に聴いてみて300文字レビュー。
★★★★★ 思い入れたっぷり超名盤!!
★★★★☆ かなりいい感じ!
★★★☆☆ 何度か聴いたらハマるかも
★★☆☆☆ 好きな人がいるのはわかる
★☆☆☆☆ お耳に合いませんでした
ジャケット写真が TOWER RECORDS の商品にリンクしています。
第79位
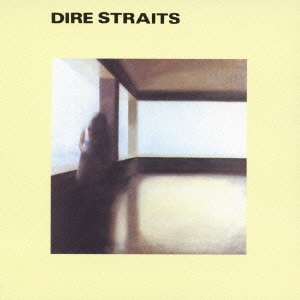
Dire Straits
『Dire Straits』
「お前はどこから来たんだ?」
いきなり現れた新顔にそう尋ねる西部劇のワンシーンのように。
「Down to the Waterline」は流麗なギターとクールなダンスの背景に荒野が見える。
「Sultans of Swing」に代表されるように、マーク・ノップラーの爪弾くような速弾きギターは独特の響きを放つ。軽快なのに、しっとり濡れている。
渋いダミ声ヴォーカルは黒人ブルース・シンガーのよう。
悲しきサルタンとは、放浪者のガンマンか。
アコースティックなカントリー・ブルース調が優雅だったり、ファンキーなサウンドで攻めたりする曲も含め、キレのあるリズムの根幹はギターが担う。
「Lions」は王者の孤独を感じさせる。
イギリス人らしくウエットな肌触りを持ちつつも、曲のスケールはアメリカっぽい。
冒頭の言葉をもう一度問いかけたい。
★★★ (2025.3.7)
第80位

Alice Cooper
『Killer』
どうにもキケンな香りがする。絶対僕の好みではないだろう。食わず嫌いというのは誰にでもある。
ビジュアルからか、歌い方からか、噂話からか、アリス・クーパーはなんか怪しい人、奇人変人の類だと思っていた。
「Under My Wheels」はオールド・タイプのロックンロールかと思ったら、徐々にハード・ロックにもグラム・ロックにも感じさせる弾丸ビートに変化する。
「Halo of Flies」の鋭い緊張感で目まぐるしく展開する様はプログレ。
かと思えば「You Drive Me Nervous」でパンクの先駆けのようなことをやっている。
あるジャンルにおいては継承者で、あるジャンルにおいては始祖でもある。
わずか36分の中で、一粒で何度も味が変わるアメ玉のように、その多面性に驚く。
ソロ・アルバムかと思ってたら、バンド名義だったことにも驚く。
食わず嫌いを克服した時、一気に虜になるのも常だ。
★★★★ (2025.2.11)
第81位

Wire
『Pink Flag』
パンクって結局、動き出さずにはいられない若さゆえの衝動だったと思う。あれもやりたいこれもやりたいと溢れ出るアイデアを詰め込んで、全21曲にもなってしまった。それでいて総時間は35分という不思議さ。
「Mr. Suit」で1・2・3・4!とカウントしてギターをかき鳴らし、突き進む姿はこれぞパンク。
「106 Beats That」ではポップなビート、「Champs」ではクールなビートと使い分け。
いい感じになってきたと思ったら突然フィニッシュしたり、どこが切れ目なのかわからなくてメドレー風になってたり。
各曲もう少し練って完成度を高めてたら、名曲具合も上がってたろうと思えるのに。
そんなに待ってられないんだよ、早く次に行きたいんだよ。そんな若者たちの強い思いと行動力が時代を作るんだな。
★★★ (2024.6.26)
第82位

Jackson Browne
『The Pretender』
穏やかそうなフォークのシンガーソングライターだと思っていたのだけれど、意外にもAORだったり、ブルースだったり、サザン・ロックだったり、ブラス・ロックだったり。聴いていると、アメリカって広いなあと感じます。
「The Fuse」のピアノと共に昇りつめていく感じや、「The Pretender」の力強いピアノを美しいハーモニーとストリングスで包み込むロックな感じは、ビリー・ジョエルを思い出したのだけど、ビリーは都会に住む者の心を正直に描いたのに対し、ジャクソンはどちらかというと雄大な土地に暮らす者で、しかもその真意を隠し、偽りの自分を作り出しています。
穏やかそうな外見に安心したりしないで、その心の奥底を推し量る努力をしないと、他人の辛さはわからないし、真の人間関係は築けないと言われてるようです。
★★★ (2024.6.22)
第83位
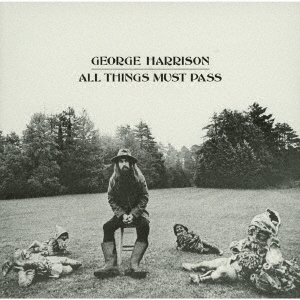
George Harrison
『All Things Must Pass』
大きすぎる2つの才能を前に、謙虚に努力するしかなかった。と同時に成長した己の才能も相当のものがあるはずだとの思いに至る。それが解き放たれ3枚組として爆発した。
「My Sweet Lord」「What is Life」の堂々とした姿で聴く者に有無を言わせない。
そんなジョージをサポートする仲間たちの多さ。みんなでジョージの凄さを世間に証明してやろうじゃないかという気構えを感じる。
クラプトンの熱いギターが冴える「Art of Dying」。
大袈裟なサウンドが美しくやるせないメロディに映える「Let It Down」「Hear Me Lord」。
自信を持つとはこういうことか。圧倒的パワーに満ちている、ポップ・ミュージックの金字塔。
★★★★★ (2024.6.18)
第84位

Queen
『News Of The World』
シングル、アルバム共に大ヒットを出して、クイーンのサウンド・スタイルを多くの人に知らしめた後はやはり、新しいことへの挑戦か。
リズム・パターンから曲を作ったのが明白な「We Will Rock You」のざわめき。
パンクのごときスピード感「Sheer Heart Attack」や、ファンクだけれどディスコとまでは言えない「Fight From The Inside」など、時代の流れを読んだ曲も。
オールド・ブギも小粋なお洒落曲もムーディーなジャズも。引き出しの多さを物語るが、どれもやっぱりクイーンの音。
「We Are The Champions」は勝ち誇ってるようには思えず、敗者の無念を背負っていく覚悟。ここにクイーンの美学を見る。
★★★ (2024.6.12)
第85位

King Crimson
『Larks’ Tongues In Aspic』
静けさの中から迫りくる旋律、暴れまくってるのにピタリと息が合っているドラムとベース。清々しささえ感じるバイオリンは効果的で、タイトル曲で鳴るギターからは「電気」を感じた。
「Book Of Saturday」「Exiles」は、プログレに言うのもなんだが、素朴。アレンジ次第ではフォーク・ソングになりそうなほどメロディアスだ。
「Easy Money」は危険が迫ってくるようなイントロにキャッチーなメロディが絡むニヒルな狂気。
着地点が見えない演奏は、突然終わりが来る。
このアルバムのどこが太陽なんだ?まるで嵐じゃないか。静かな曲だって、曇り空に思える。
クリムゾンは、いつだって聴く者の胸をザワつかせる。
★★★★ (2024.6.12)
第86位

The Band
『The Last Waltz』
ディランやクラプトン等を新しいサウンドへ導いていったザ・バンドの解散ライヴ。
カントリー風ののんびりムードの中での鋭いギター、スリルあるホーン、分厚い演奏にジワジワと熱くなっていく感じ...ぬくぬくと抜け出せなくなるのはまるで炬燵だ!ライヴなので、より臨場感がある。
クラプトンとのギター・ソロの応酬、牧歌的なニール・ヤング、ピリッとした空気を作るジョニ・ミッチェル、いつもより力の入ったディラン。
ロック、カントリー、ブルース色々と操れる下地があるからこそ、楽観的で自由に生きていくさというノリに説得力がある。
普通の解散ライヴは転校していく友を見送る感じだけど、これは多くの人が集う皆の卒業式の趣だ。
★★★★ (2024.1.19)
第87位

Genesis
『Foxtrot』
プログレのイメージなかったけど、プログレ時代真っただ中の作品。
「Watcher Of The Skies」はゴリゴリのベース、神聖なるキーボード、暴れまわるドラムに清らかなヴォーカルと、イエスっぽいサウンドだなと。
「Get ‘Em Out By Friday」はフルート、メロトロンが鳴り響き、静から動へ、安心と緊張が入れ代わり立ち代わり展開していく。
「Supper’s Ready」はギターが美しい音や歪んだ音で世界の色を変えながら、ピーター・ガブリエルの本領発揮な演劇的な要素を持ち、ロックとポップスがつぎはぎになった20分超えの大作。
基本的に爽やかでポップな肌触りが平和的で聴きやすい。彼らに野心はあるのか?ただ単に楽しいと思うままの音作りかも。
★★★ (2024.1.16)
第88位

Led Zeppelin
『Presence』
「Achilles Last Stand」が文句なしにカッコいい。切り裂くギター、タイトに躍動するベースとドラム。ロバート・プラントのどこか諦めた感のあるヴォーカルが切ない。戦いに向かう闘志が奮い立つ。
「Nobody’s Fault But Mine」のギターとヴォーカルが重なるリフがなんともセクシー。そのリフに被さるようにギター・ソロが火を噴く。
「Tea For One」のようなやるせなく燃えるブルースをやってたとは驚き。
ジョン・ボーナムのドラムは迫力あるのに重くならず体が跳ねる感じ。サウンドの骨格。
アルバムのこの流れは大きく盛り上がるポイントはないんだけれど、ゆっくりお茶してる場合じゃないぜ、その笑顔は作り物だろ?とジャケットを見て思う。
★★★★ (2024.1.15)
第89位

Joni Mitchell
『Blue』
キャロル・キングがユーミンとすれば、ジョニ・ミッチェルは中島みゆきか。いや、違うか。
辛いことや恨みつらみで埋め尽くされたアルバムか?とイメージしてたけど。
「All I Want」はフォークというか、鮮やかなカントリーの響き。
どの曲も基本は煌びやかなアコギか、荘厳なピアノでの弾き語り。そしてアフリカン・ビート的な「Carey」など、時折グルーヴをかます。
白眉は「Blue」で、美しいピアノと憂いなメロディで心の奥底の憂鬱を吐き出す。
澄んではいるが、割とテンション高めで、踊るように歌うヴォーカルにはブルースが宿る。
恋に生き、過去、現在、未来を行き来し、心の安寧を求める旅のようだ。
★★★ (2025.2.22)
第90位
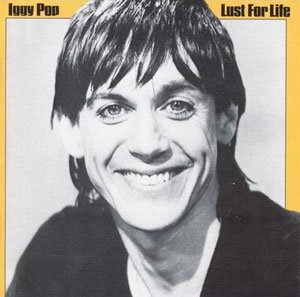
Iggy Pop
『Lust For Life』
イギー・ポップって、一筋縄ではいかない変態性があるイメージだったけど、デヴィッド・ボウイがプロデュースしてるとあって注目。
粗暴なギターを中心に荒くれたサウンドのビートが支配する。
「Some Weird Sin」はリフが素晴らしく印象的な、踊れるロックンロール・ブギ。
「Tonight」はダンディで希望に満ちいてる。
「Turn Blue」は演劇的要素もあり美しくてドラマチック。
「Neighborhood Threat」は裏街道を走るかのように勇気をくれるロック曲。
イギーのヴォーカルは野性的で、曲によって、ささやいたり振り絞ったりと雰囲気を変える。
ボウイの力も大きいが、ジャケットの笑顔からは想像もつかない程のストレートなカッコ良さに驚く。
★★★★ (2024.1.14)
第91位

Pink Floyd
『Atom Heart Mother』
『原子心母』という邦題、そして牛!この不可思議な二大インパクトが、プログレの本質を突いてる気がする。
アナログA面を覆った「Atom Heart Mother」は叙情性あふれるギター、宇宙にとどろくハーモニーから、呪術的な民族の祭りを経て、爆発までも!神聖と不穏を行ったり来たりで、とっちらかってて何じゃコレ感。管楽器、弦楽器が順に盛り立てて終焉に向かってまとめていくと、なんだか凄いものを見たようで、また聴いてみたいと思わせる。
B面は一転してフォーキー。アコギの牧歌的で平和なサウンドが中心で、SE入りの謎多きインストもあり、後の『狂気』の萌芽も見せる。
シド・バレットを失った後のフロイドが別次元へ突入したアルバム。
★★★ (2023.12.19)
第92位

Uriah Heep
『Look At Yourself』
プログレハードの祖ということだけれど。
「Look At Yourself」はハード・ロックで、全体をキーボードの幕が覆っているものを、ギター・リフとドラムで竜巻のごとく巻き上げていく。
「July Morning」は憂いがありながらもキャッチーなメロディ。諦念あふれるギターとスペイシーなキーボードのフレーズが折り重なり興奮。
「Shadows Of Grief」はどう転がるかわからない様々なドラマを見せるプログレ的展開。
「What Should Be Done」はピアノ1本から始まる柔らかな感触。
突き進むハード・ロックと緻密なプログレを器用にこなすが、ジャンル分けされていった中で覇を競った70年代、どっちつかずなのは実は不利だったのではないかと想像する。
★★★ (2023.12.18)
第93位
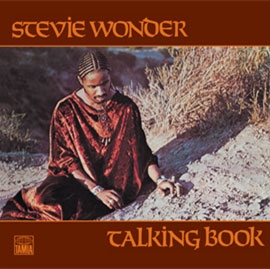
Stevie Wonder
『Talking Book』
スティーヴィーを知った時、50歳過ぎのおじさんだと思ったら、当時まだ30歳くらいで、ビートルズよりもずっと歳下と知ってビックリ。それくらい早熟。
「You Are The Sunshine Of My Life」は、柔らかいキーボードの音色で、陽だまりのようなサウンド。いきなりスティーヴィーじゃない歌声が立て続けに現れて驚くけど。
「Superstition」はイントロに「なんだ、この音は!?」と驚く(どうやらクラヴィネット)。ファンキーなノリの良さは病みつき。
アコースティックなパーカッションを疾走させてグルーヴを作っていくのもサウンドの肝。
スティーヴィーは声そのものがファンキー。それでいてバラードでは優しく抱いてくれるような安心感がある。
★★★ (2023.12.17)
第94位

Boston
『Boston』
ボストンなんて名前が地域限定的で、聴く者を選ぶイメージだった。
「More Than A Feeling」は優雅に、勇ましく空を飛ぶ。キラキラしたアコギから唸りをあげるギターへ。ハイトーン・ボイスが天高く舞い上がる。
「Foreplay / Long Time」は激しいドラムをキーボードが覆っていき、ギター・ソロ全開と、プログレ的な展開。
「Smokin’」はブギ調で、キーボードが暴れまわり、次から次へと超空間を作り出す。
力任せのハード・ロック、緻密なプログレ、わかりやすいポップスをいいとこどりし、どの曲もシングル向きと思う程キャッチー。
ほぼ全ての音をトム・ショルツ1人で作ったというのだから驚き。
地域限定だなんてとんでもない、万人向けだ。
★★★★ (2023.12.16)
第95位

The Doobie Brothers
『The Captain And Me』
サザン・ロック特有の勢いがありながらも、美しいハーモニーで爽やかさを演出するドゥービーズ。
なんといっても「Long Train Runnin’」!歯切れのいいギターのカッティングはファンキーで熱く、サビのコーラスは一緒に口ずさんでフィニッシュしたくなる。ハーモニカ・ソロも含め、切なさも携えている名曲。
「China Grove」のイントロのリフも超有名で、心踊る。
「Ukiah」は小気味いいシャッフルのリズムにヴォーカルのハモりが心地良い。
ギターはカッティングの技術だけでなく、艶があり流麗なソロも素晴らしいものが多い。
ジャケットの青空のように、熱い風も吹けば、涼しい風も感じる爽快感で、ウエスト・コーストに思いを馳せる傑作だ。
★★★★ (2023.12.15)
第96位

Rainbow
『Rising』
ディープ・パープルを脱退したリッチー・ブラックモアが、ハード・ロックはこうやるんだぜと見せつけたアルバム。
低音から伸びのある高音ヴィブラートを駆使するロニーのヴォーカルそのものがドラマチック。怖いものなしの突撃感で速弾きギター・ソロも轟く重厚ロック。
圧巻は「A Light In The Black」で、「Highway Star」を彷彿とさせるスピード感で、スペイシーなキーボード、リフからの長尺ギター・ソロ、爆裂ドラムにシャウトが絡み合いながら高みへ昇りつめていく。演奏を止めないでくれと永遠に聴いていたい名曲だ。
パープルとどう違うのかと疑問符も付くが、興奮するのは止められない。これがハード・ロックのテンプレートなんだろう。
★★★★ (2023.12.3)
第97位
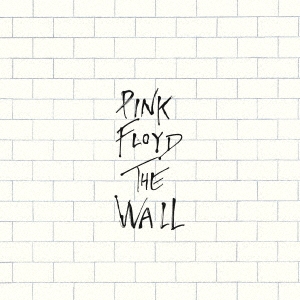
Pink Floyd
『The Wall』
ただでさえコンセプト・アルバムを作るのは大変なのに、2枚組にして大ヒットさせた。
序盤は穏やかに土台を作っていくが、中盤からはやや重苦しさも漂う。
「Comfortably Numb」の叙情的なメロディにとどろく激情のギター・ソロはさすがギルモア。曇り空にゆっくりと太陽の光が差し込んでくるような感がある。
クイーンからの影響を感じたのが「Run Like Hell」。
舞台狭しと繰り広げられる演劇的な「The Trial」。
美しいメロディ、落ち着いたギター、アコギ、ピアノ、コーラスは心が安らかになる。
緊張感や混沌、気難しさは薄く、聴きやすいプログレ。
いろんな声や音のSEが繋ぎ、ラストに壁が崩れるまでの26曲。この流れはアルバムの醍醐味。
★★★★ (2023.12.2)
第98位
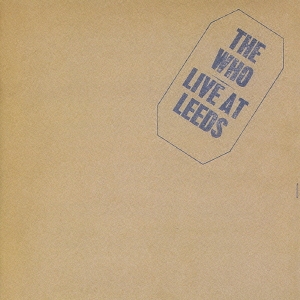
The Who
『Live At Leeds』
こういうランキングでライヴ盤が選ばれるのは余程のことだろう。
オリジナルは全6曲と少なかったが、後に拡張版として全14曲となり、ベストヒット的な収録曲となったのは嬉しい。
真ん中ドラム、左がベース、右がギターの配置は、目の前で瑞々しい演奏が繰り広げられているようだ。
「Young Man Blues」は全然ブルースっぽくなくて、ハード・ロック・バンドの激しさ。
どれも歌メロ後のインプロビゼーションが長尺で、どう展開していくか読めないのが面白く、ライヴならでは。
「Magic Bus」でのヴォーカルの応酬、熱いハーモニカがラストに向かって行く高揚感を演出。
最後は見事に燃え尽きた感。余力なんて残さず、燃え尽きるのがモッズよなあ。
★★★★ (2023.12.1)
第99位

Cheap Trick
『Dream Police』
誰にでも好かれる人がいる。気さくでウエルカムな雰囲気を持ち、人を惹きつける魅力を持っている。
華々しい幕開けで、一気に聴く人の心を掴む。こんなライヴが始まったら、いきなり盛り上がるだろう。
「The House Is Rockin’」はハード・ロック的なギター・リフにソロが火を噴き、盛り上げるコーラスが爽快感。
「Voices」は甘酸っぱい青春の日々を思い出すソフト・バラード。
「Writing On The Wall」はノリが勝負の王道ロックンロール。
ハード・ロックの力強さ、豪快さ、硬派な面を持ちながらも、あくまでポップにまとめている。すると、ギターもコーラスもビートルズ的なパワー・ポップの誕生だ。
万人受けはしても、八方美人にはならない。
★★★ (2023.11.30)
第100位

The Damned
『Damned Damned Damned』
パンクは短距離走だ。ゴールめがけて、いや時にはゴールなんかなくても、とにかく全力疾走する。
パンクの元祖、ダムド。彼らには新しい音楽を作っているという認識はあったのだろうか。
「Neat Neat Neat」を聴いてほしい。初期衝動そのままに、一直線に突き進むビート。サビで「ニニニ!」とキャッチーなフックで叫ぶ様は、これぞパンクだ。
クールなガレージ・ロックや奥深い展開を見せる曲もあるけれど、「See Her Tonite」のようにやけっぱちコーラスをしながらパワフルな爆裂サウンドを聴かせるところに神髄がある。
50mダッシュを100本こなしても、最後に「I’m Alright」と言える若さとタフさ。走りまくった結果、新しい道が出来た。
★★★ (2023.11.29)


コメント