
ジャケット写真が TOWER RECORDS の商品にリンクしています。
『All Things Must Pass』
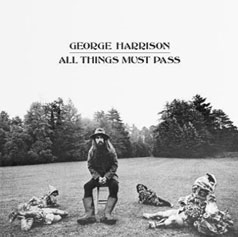
ある時、ジョージ・ハリスンばかり聴いていて、そしたら、ちょうど命日だったという事に気付いた時があった。
命日だから聴いたわけではなくて、何日か前からふとジョージが聴きたくなり、繰り返しiPodで聴いてたら、ネットで命日だったという事に気付いたのだ。
こういう偶然。
ジョージのお導きかもしれないと思っている。
それにしても、改めて『All Things Must Pass』は名盤だなあ、と。
僕にとってのジョージの最高傑作は『Cloud Nine』で、『All Things~』の方はあまりにも多くの人が最高傑作と崇めるものだから、『Cloud~』贔屓の僕としては、どこか冷めた目で見てた所があったんだけど、まっさらな気持ちで『All Things~』を聴いたら、素晴らしすぎてリピートしまくり。
捨て曲がなくて、聴く度にどの曲もどんどん好きになっていく。
70年リリースの実質的な1stアルバム。
オリジナルはアナログ3枚組。
プロデュースはフィル・スペクターだとか、バックで演奏しているのは後のデレク&ドミノスだとかという事が肝。
僕が聴いたのは01年リリースのニュー・センチュリー・エディション。
旧盤はアナログABC面がDisc1、D面+ジャム面がDisc2という、特にDisc2の方は聴きたくなくなる程のバランスの悪さだったけど、このニュー・センチュリー・エディションからはAB面+ボートラがDisc1、CD面+ジャム面がDisc2となって、非常に聴きやすい構成に生まれ変わっている。
Disc 1
「I’d Have You Anytime」。
昔は、こんな3枚組大作のオープニングなのに、地味すぎるなあと思っていたのだが、このさりげなさが寂しく響いてきて沁みるようになってきた。
かなりいい感じじゃん!
「My Sweet Lord」。
寂しい前曲から一転、ポップで明るくなるこのギャップ。嫌いな人がいるのだろうか。
リズム隊が入ってからグッと力強くなって、スライド・ギターのフレーズが気持ちいい高音を奏でる。
「Wah-Wah」。
力強さはさらに増し、ワウワウのギターがまさしくワーワーと騒がしい曲。ハイテンション。
「Isn’t It A Pity」。
壮大なバラードで、ジョージやクラプトンに次々と名曲を作らせるパティの偉大さを思う。
どんだけいい女なんだ!
徐々に盛り上がるウォール・オブ・サウンド。
「What Is Life」。
「My Sweet Lord」に負けず劣らずポップでキャッチー。
元気が出て楽しくなる清々しさがある。
ここでもフィル・スペクターがいい仕事してる。
「If Not For You」。
ボブ・ディランのカヴァーは軽快で、うっかりすると聴き流しちゃう。
「Behind That Locked Door」。
トロピカルな、どこかハワイアンな南国ムードのリゾート・ソングの印象。
「Let It Down」。
重たくパワー溢れるカッコいいイントロから、一転してメジャー・セブンス・コードのやるせなさ漂うメロウなムード。
レオン・ラッセルが弾いてると言われているピアノも跳ねていて聴きもらせない。
サビは再び力強くなって...大好きな曲。
「Run Of The Mill」。
大好きすぎる「Let It Down」の後なので、昔はほとんど印象に残らなかったんだけど、聴けば聴くほど味わいが出てきた。
サビのメロディが最高。
「I Live For You」。
ここからボーナス・トラック。
これは未発表のボツ曲という事だけど、ボツとは思えない程このアルバムに馴染んでいる。
ジョージの優しさに溢れていてスライド・ギターも全開。
「Beware Of Darkness」。
アコギ弾き語りのデモ・ヴァージョン。
「Let It Down」。
これもアコギ弾き語りのデモ・ヴァージョンにギターを足してある。
渋みがあって、オリジナルとはまた違った味わい。
ジョージのヴォーカルもギターの音も、透き通る様な純粋さ。
「What Is Life」。
イントロにホーンが加わって、より華々しく、さあいよいよ歌が始まるぞと思ったら、ヴォーカルはすぐに消えてしまって肩透かし。
結局インスト。これはいらないなあ。
「My Sweet Lord」。
2000年ニュー・ヴァージョン。
スライド・ギターのフレーズを増やし、メロディも崩して歌っている。
まあ、気分転換でたまにはいいか。
ボーナス・トラックも入って、ここまででも満足感でいっぱい。
Disc 2
「Beware Of Darkness」。
僕はレオン・ラッセル・ヴァージョンの方を先に聴いてたんだけど、さすがにあそこまでの粘っこさはなく、ジョージの歌はしっとりとしている。
「Apple Scruffs」。
ハーモニカの響きが印象的。
サビでのジョージのファルセットも耳に残る。
とにかくアコギとハーモニカと思ってたら、ビートルズ風コーラスやらスライド・ギター・ソロも出てきて聴き所満載。
「Ballad Of Sir Frankie Crisp」。
ピアノがいいアクセントになっていて、地味だけど外せない魅力を持っている。これもスルメか。
「Awaiting On You All」。
昔はまったく印象に残らなかった曲なのだが、ある時バングラデシュ・コンサートでのこの曲の映像を観て心奪われた。
イントロのリフ、リズムが華々しく印象的で、自然とノッてしまう。
ライヴでビシッと決めたらカッコいい曲なんだなと大好きになった。
「All Things Must Pass」。
これもビートルズ時代にできていたという曲で、アルバムのタイトル・ソングでもあるから自信のある曲なんだろうけど、バラードという事もあってか、昔はそこまで深入りできない僕だった。
今は無常観にシンパシーを感じるようになった。
「I Dig Love」。
「Come Together」みたいなドラムが怪しげなムードを醸し出している。
「Art Of Dying」。
これは文句なくカッコいいロックンロール。「Layla」みたいだと思った。
演奏してるデレク&ドミノスにとって、後の「Layla」の下敷きになったんじゃないかな。
サイケ風でもある、いかにもクラプトンなギター・ソロとか、ホーンが煽る所とか、もう熱くなってくる。
「Isn’t It A Pity」。
再登場するVersion2。
だけど僕はいまだにVer.1との違いがよくわからない。聴き分けができてない。
それほど印象的には違うものではないので、わざわざ再登場させなくても良かったのにと思っちゃう。
それほど自信のある曲だったのかな。
「Hear Me Lord」。
ダンダンダンッと迫りくるイントロのドラムからして、来た来た来たぁ~という感じ。
やるせなさ、はかなさ全開のコード進行とメロディにうっとりとするし、熱くもなる。
必殺入魂のバラードは、超大作のアルバム本編を締めくくるに相応しい名曲だと思う。
この後はジャム・セッション。
インストが苦手の僕は、こういうジャム・セッションも苦手で、しかも長いし、良さがわからなかった。
一瞬、カッコいいかもと思う場面もなくはないけど、やっぱり僕にとっては退屈なので、いらないなあと思っちゃってた。
こんなジャム・セッション盤は省いて、スッキリ2枚組にして、もっと安く売ってたら、どれだけ売れてただろうと。
高価な3枚組は敷居が高く、躊躇して買えなかった人も多かっただろうしね。僕もそうだったし。
だから、以前はこのジャムは蛇足だと思ってた。
だけど、苦手だったブルースが好きになり、デレク&ドミノスがさらに大好きになると、このジャムも途端に興味深く思えてきて。
クラプトン含めたドミノスと、ジョージとが、時に火花を散らし、時にリラックスした演奏を聴かせる。
これはこれで魅力的なんだよ。
そういったわけで、ジャム・セッションも含めて、当時の3枚組という重厚感も魅力の一つだったんだろうし、それでも大ヒットしたんだから、これは大成功のアルバムで、大名盤。
隙がないよね。
思い出や思い入れは『Cloud Nine』の方にやや分があるんだけど、冷静に考えれば、やっぱりこっちの方がジョージの最高傑作だとの結論にも異を唱える事はできないなあ。
素晴らしすぎた。
(2024.9.26)
静かなビートルは謙虚だったのか?
いや、ビートルズ解散後に単価の高い3枚組を出すなんて、相当の自信の表れだ。
デレク・アンド・ザ・ドミノスらの演奏、フィル・スペクターのプロデュース力もあるけど、やはりジョージの作る曲が圧倒的に素晴らしかった。
(2024.5.5)
大きすぎる2つの才能を前に、謙虚に努力するしかなかった。
が、成長した己の才能も相当のものとの思いが解き放たれ爆発した。
仲間たちも、みんなでジョージの凄さを世間に証明してやろうじゃないかという気構えが見える。
自信を持つとはこういうことか。
(2024.6.18)
『The Concert For Bangladesh』
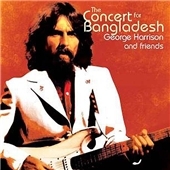
71年8月にジョージ・ハリスンの呼びかけで、マジソン・スクエア・ガーデンで行われたチャリティ・ライヴの模様を収めたLP3枚組。
72年リリース。
だけどこのアルバム、気にはなってたものの、ずーっと聴く機会がなかった。
だって、レコードでは3枚組で、高価だったもん、手を出しにくかった。
それから冒頭のラヴィ・シャンカールの長い演奏。
インド音楽が苦手な僕は触手を伸ばせなかった。
ボブ・ディランがいまいち苦手な僕には、ディランの曲がたくさん入ってるのもあまり嬉しくなかった。
3枚組だというのに、目当てのジョージの曲は8曲と、なんだか少ない気がして。
それから、このアルバム自体、廃盤になってる期間もあったりして、興味を持っても売ってない状態が続いたりと、タイミングが合わなかった。
だけど、グッと興味が増したのは、YouTubeで、偶然「Awaiting On You All」の映像を目にしてから。
それまで、「Awaiting On You All」なんてタイトルを言われても、どんな曲だったか思い出せないくらい、印象になかったのだが、この映像を観たら、すごくエネルギッシュでジョージたちが活き活きしている、素晴らしい曲だなあと思う様になったのだ。
それで、この『The Concert For Bangladesh』を聴かなきゃなあと思う様になっていった。
そこで調べてみたら、再発盤が2枚組2700円で売ってたので、この値段なら買いやすいなあという事で、ポチッと行ってしまったのである。
ジャケットも、子供の写真じゃなくて、ジョージのカッコいい姿になってたのも良かった。
ビートルズを、ジョージを好きになって30年近く経って、ようやく、このアルバムを聴く事ができた。
Disc 1
「Bangla Dhun」。
僕がこのアルバムを長年聴けずにいた理由の一つ。僕の苦手なインド音楽。
いや、ビートルズの様に、ロックの中にインド音楽をスパイスとして取り入れたものならまだ聴けるけれど、こうしてガッツリインド音楽を10分以上も聴かされるのはやっぱり辛い。
BGMとして聴き流すしかない。
「Wah-Wah」。
やっとの事でインド音楽が終わって、聴こえてくるこの曲のロックなギターのイントロには胸が高鳴る。
寡黙なはずのジョージのヴォーカルも熱がこもっていて、演奏も当然熱い。
冒頭からこの演奏をするバンドに、このコンサートは素晴らしいものになるだろうとの期待感で一杯になっただろう。
「My Sweet Lord」。
イントロのアコギの音が、絶妙な硬さがあっていいなあ。
スタジオ音源の様なスペクター・サウンドではなくて、余計なものは付いてない、この曲の持つ本来の良さが浮き彫りになっている。
スペクター・ヴァージョンもいいんだけど、ライヴでのシンプルな良さ。
「Awaiting On You All」。
YouTubeで観た時から、この曲の演奏の良さはわかっていたけど、やっぱりいい。
このスピード感、躍動感、グルーヴはたまらないね。
「That’s The Way God Planned It」。
ビリー・プレストンの曲で、初めて聴いた。
バラードと言うか、ソウルフルなゴスペル。
サビのリフがジョージの「Something」ぽいけど、これは元のスタジオ音源もこうなのだろうか。
それともジョージのバンドだからこうなっちゃったのか。
「It Don’t Come Easy」。
大好きなリンゴの曲。
リンゴも気合いが入ってる様に聴こえるし、ある意味リンゴの絶頂期もこの頃かも。
「Beware Of Darkness」。
穏やかにも聴こえるし、熱がこもってる様にも聴こえる、不思議な曲。
そして、2番でレオン・ラッセルがリード・ヴォーカルをとると、大きな歓声が沸き起こる。レオンも人気あるんだね。
レオンが粘っこいヴォーカルを聴かせると、曲の雰囲気も変わって聴こえ、1粒で2度美味しい感じ。
「While My Guitar Gentry Weeps」。
大好きな曲なんだけど、残念なのは、スタジオ音源のイントロでのピアノの印象的なフレーズが再現されてない事。
このバンド編成ではピアノは無かったのかなあと思いきや、聴き進めると、時々ピアノらしき音が聴こえてくるんだよね。
だったらイントロもなんとかしてほしかった。
クラプトンのギターの音も、結構薄っぺらくヘラヘラしているのもちょっと微妙。
『Layla』のまだ翌年だというのに、この頃既にドラッグでダメになりかけている時期らしく仕方ないのか。
これでもダメだとは言わないけど、『Layla』の時の情熱的で攻撃的なギターだったなら。
ジョージの弾くギターが圧倒的に素晴らしいので、絶頂時の2人のギターの絡み合いが聴きたかったなあ、と思ってしまう。
でも、そんな所を差し引いても、いいライヴ・ヴァージョンだとは思う。
Disc 2
「Jumpin’ Jack Flash~Young Blood」。
レオン・ラッセルによる、カヴァー曲のメドレーだけど、レオンが歌い始めると、この独特の空間が生まれて、いかにもなレオンの世界になる所が面白い。
個性とかオリジナリティって言葉が頭に浮かぶアーティスト。
ぐいぐいとノッている演奏も素晴らしい。...けど、長いメドレー形式にしたのは、いささかダレる気も。
スパッと潔く終わらせた方が良かったかもなあ。
「Here Comes The Sun」。
アコギ2本のシンプルな演奏。
スタジオ音源だと、途中からベースやドラムが入ってきてロックになるんだけど、ここでの演奏はアコギ2本のまま。
弾き語りが苦手な僕にとっては微妙な感じ。
いや、演奏自体は美しく素晴らしいのはわかるんだけど、やっぱり僕はバンド演奏で聴きたかったなあ。
「A Hard Rain’s A-Gonna Fall」。
「It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry」。
「Blowin’ In The Wind」。
「Mr. Tambourine Man」。
「Just Like A Woman」。
ボブ・ディランって、好きになりたい気持ちはあるんだけど、どうにもハマりきれないアーティストだった。
トラヴェリング・ウィルベリーズでディランが作った曲は大好きだったので、期待して3枚組ベストを買ったけど、好きになれる曲が少なくてガッカリ。
レジェンドだから、好きになれたらいいなという気持ちはあれども、僕にとってはまだイマイチなディラン。
このアルバムでのディランのパートも、実はちょっと退屈だったりするのは内緒の話で。
「Something」。
長かったディランが終わり(笑)、ようやくジョージのこの曲。
スタジオ音源よりややテンポが速いか?
キーボードやホーン・セクションが曲に厚みを与えていて盛り上げる。
間奏のギター・ソロが、ソロと言わず3本くらい絡み合ってるのがたまらなく良い。
単なるバラードではない、実は熱いソウルフルな味わいがある。
「Bangladesh」。
憂いのあるイントロのメロディから一転して力強いサビ。これまた大好きな曲。
このライヴのために書かれた曲なので、オリジナル・アルバムには収録されず。
これが入ってるベスト盤持ってるけど、ビートルズ時代の曲と半々な内容が好きになれず、ここで久々に聴けて良かった。
『All Things Must Pass』の直後にこの曲を書いたんだから、「ジョージ、すげえ~っ!」ってなるよね。
さすがにライヴ映えする曲で、会場は盛り上がったんじゃないかな。
なにより、このライヴに賭けるジョージの熱意がびんびんに伝わってくる。
「Love Minus Zero/No Limit」。
ディランのボーナス・トラック。
うーん、やっぱりここでのディランにハマれない僕。
ボーナス・トラック入れるんだったら、このライヴの昼の部のみで演奏されたという、ジョージの「Hear Me Lord」を入れてほしかった。
『All Things Must Pass』の中でも一番好きと言っていいこの曲を、せっかくライヴでやってくれたんだったら...。
でも、昼の部でしかやらなかった事といい、お蔵入りになったという事は、なにか問題でもあったのだろうか。
これまでジョージのライヴって、『Live In Japan』しか聴いてこなかったけど、こなれた感じのクラプトン・バンドがバックの『Live In Japan』よりも、この急造とも言えるチャリティ・バンドの『The Concert For Bangladesh』の方がジョージ色が濃くて、演奏・ヴォーカル共に素晴らしく聴こえる。
やはり、この頃がジョージの絶頂期だったんだなあと実感。
長いこと聴いてこなかったのを反省させられたアルバム。
やはり噂通りの良い作品だった。
ちゃんと聴けて良かった。
(2024.10.24)
『Living In The Material World』
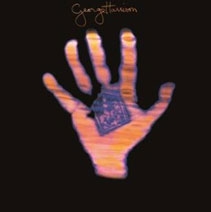
3枚組の超大作『All Things Must Pass』を大ヒットさせ、チャリティのバングラデシュ・コンサートも大成功させ、ロック界の頂点に立ったと言っても良かったジョージ・ハリスン。
ビートルズ解散後は、もっとも成功したのはジョージだと思われるほどの天下獲りだった。
そこから少し間が空いたものの、温かな曲調に癒されるシングル「Give Me Love」も全米1位を獲得し、勢いは衰えてないジョージが次に世に放ったアルバムがコレだ。
前作で諸行無常を説いたが、それでも物質社会で生きねばならぬことを皮肉ってみせた。
そのタイトル曲「Living In The Material World」は威勢のいいドラミングがリードしつつも、インドっぽい展開も見せたりして、風格漂う力強さに説得力があった。
しかし、このアルバムの肝となっているのは、「The Light That Has Lighted The World」「Who Can See It」「That Is All」という、3曲のメロウ・バラードだろう。
「The Light That Has Lighted The World」は深みのあるピアノを軸に、跳ねたギターがアクセント。
しかし、どこまでも穏やかなサウンドとメロディにメロメロになる。
「Who Can See It」はレズリースピーカーを通したようなギターの音色が空気を落ち着かせながらも、力強さがあり、ビートルズの「Something」にも匹敵する魅力を感じる。
「That Is All」は泣いているメロディなのに、どこか涼し気で安らか。
達観したようなジョージの歌い方に惹かれる。
この3曲のような、フワフワとした浮遊感溢れる、不思議な感触を持ったメロウな曲が、ジョージ特有の魅力となった。
この後もジョージの得意技となっていく。
「Sue Me, Sue You Blues」はビートルズ「For You Blue」みたいなドブロ・ギターが印象的。
深刻なメロディを中和させるサウンドの要になっている。
「Don’t Let Me Wait Too Long」はモコモコしたサウンドながらも軽快なフォーク・ロックで、優しくてノリのいい曲で気持ちが洗われる。
「The Lord Loves The One」はビートルズ「Two Of Us」みたいなアコギ・リフから始まって展開していく。
「Be Here Now」は広い海に向かって詠むお経のような、厳かな雰囲気。
「Try Some Buy Some」はビートルズ時代から得意にしていた、ウェットなメロディ。
フィル・スペクター繋がりで、ロニー・スペクターに提供されたけれど、ジョージにはこういう泣きの曲が似合う。
「The Day The World Gets Round」は穏やかながらも壮大で、静かな感動を呼ぶ。
バングラデシュのライヴ盤も含め、3枚組を連発したことからすると、ここで通常の1枚のアルバムになったことは、かなり軽さを憶えた。
デレク&ザ・ドミノスを従えた前作と違って、バリバリのロックを感じさせる曲はなくなった。
その分、メロウだったり穏やかだったり泣き節だったりと、本来のジョージの持つ特性が如実に表れている。
曲名に「World」と付く曲が3曲もあって、世界が向かっていく方向性に大いなる関心、危惧を持っているのが受け取れる。
ジョージらしさが溢れた傑作となった。
(2025.8.1)
穏やかの極致「Give Me Love」が全米No.1になってるけれど、全体的にメロウな感じになってきている。
「The Light That Had Lighted The World」から軽快な「Don’t Let Me Wait Too Long」の流れが好き。
控えめなサウンドがジョージらしくて良い。
(2024.5.30)
『Dark Horse』
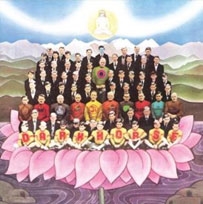
No.1ヒットを連発し、ロック界の頂点に立ったジョージ・ハリスンに、次第にプレッシャーがのしかかってきたのかもしれない。
新レーベルの設立、妻・パティとの別居など、公私ともに多忙を極めていく。
全米ツアー開催を念頭にアルバムが作られ、体調を崩し、声が荒れても、ツアーに間に合うようにと制作は続いた。
前作でメロウな特性を生み出したジョージだったが、ドタバタの制作裏が見える今作では、ヴォーカル、サウンド共に荒れていて、スギちゃん並みに「ワイルドだろぉ?」と開き直ってる印象がある。
ジャケットは一気に宗教臭くなった。
諸行無常とか、現実世界への警句とか、皮肉屋ジョージならではの表現かと思ってたら、信仰上の影響なのかということがわかってきた。
「Hari’s On Tour」は、ツアー開催を念頭に置いて、景気付けに作られたインスト。
ファンキーとメロウが合わさった魅力で、ギターとサックスが暴れまわる。
「Simply Shady」は、メロウが発展し、やさぐれ感満載となったサウンドとメロディが、荒れた声がマッチしていると感じさせる。
「So Sad」の、フワフワと浮遊感があり、落ち着かないメロディはジョージの得意技。
ビートルズ時代を思わせる面や、フィル・スペクターが作った音の厚みの影響も感じることが出来る泣き節だ。
高音で鳴りまくるギター・プレイも見事。
「Bye Bye, Love」も荒れていて、曲のテーマにもピッタリなのか、やけっぱちの様にも聴こえる。
「Maya Love」は、跳ねたメロディが特徴的で、スワンプ・ロックの再演か。
「Ding Dong, Ding Dong」は、童謡並みにキャッチーで親しみやすいメロディをベースに、ドラマチックに展開していく。
「Dark Horse」は、本来はほのぼのとしたカントリー風のメロディなのに、荒れていた声を活かすためか、力強さを強調するサウンドに変更した可能性がある。
「Far East Man」は、ロニー・ウッドとの共作にして傑作。
ジョージのメロウな特性に、やるせなさが加わった。
サックスのトム・スコットも加え、静かなる男たちがジワジワと燃えていく名曲だ。
「It Is “He”」は「クリシュナ・クリシュナ」と、軽快なリズムだけれど、優しく穏やかな歌声。
軽快なパートとほのぼのとしたパートが行ったり来たりする。
慌ただしく制作されたものの、結局ツアーの前にリリースすることは叶わなかった。
荒れた声と、開始したツアーの評判も芳しくなく、セールスは伸び悩んだ。
宗教臭さにもその一因があると思う。
失敗とまでは言わないけれど、ビートルズ解散後、破竹の勢いだったジョージの活動に、陰りが見え始めたのがこの頃だった。
個人的には、荒れた声やサウンドで攻めたワイルドさは、他のアルバムにはない魅力を伴っていて、結構好きなのだが。
(2025.8.5)
ビートルズ解散後、絶好調だったジョージだけど、このアルバムあたりから雲行きが怪しくなる。
新レーベルのごたごた、パティと別居、完成が遅れて宗教臭いジャケット、ツアーで喉を傷めてしゃがれ声。
散々だけど僕は好きよ。荒れた声も攻撃的で、新たな魅力って感じ。
(2024.6.11)
『Extra Texture』

「名作なのに、あまり語られることがない悲運のアルバムだと思っている」
ビートルズ解散後、もっとも成功したと思われていたジョージ・ハリスンだったが、過密スケジュールの中、強行制作した前作『Dark Horse』及び、全米ツアーが不評に終わった。
ソロになってのジョージ、初めての挫折と言えるだろう。
しかし、新レーベルを本格始動させる前に、アップルとの契約がまだアルバム1枚分残っていた。
やや迷いを生じながらも、前に進まねばならない。
そんな経緯で作られたアルバムだったが、止まった勢いを取り戻すことは出来なかった。
セールス的にも前作よりも下回った。
批評家たちの手のひら返しも止まらない。
邦題が『ジョージ・ハリスン帝国』と、自信たっぷりに独自の道を行く感じになっているのが皮肉と言えば皮肉。
「You」は、とことんポップでノリも良くキャッチー。
サックスが華やかで、回転数を上げてテンション高めに聴こえるジョージのヴォーカルもポジティブ。
軽快なのに深みのあるサウンド、『All Things Must Pass』の頃を思い出すじゃないかと思ったら、それもそのはず、『All Things』セッションで録音されたオケだった。
ロニー・スペクター用に制作されるもボツになった曲。
ジョージの勢いが凄かった『All Things』の頃に発表されてたら、もっと大ヒットしてただろう。
こんなに素晴らしい曲なのに、時期が悪かった。
「The Answer’s At The End」は、メロウでも力強い。
ピアノの音が上から降ってくるようなサウンド。
やるせなくて切なくて。
ジョージらしさ全開だ。
「This Guitar」もジョージお得意の泣き節だ。
ビートルズ時代の「While My Guitar Gentry Weeps」の続編のような。
スライド気味のギター・ソロは、ジェシ・エド・デイヴィスがエリック・クラプトンの役割を果たしている。
「Ooh Baby」は、フワフワとした浮遊感サウンド。
この不安定さも、ジョージらしい魅力の詰まったバラードだ。
「World Of Stone」はピアノがサウンドの軸になった、メロウな大作で、じんわりと沁みてくる感覚が感動的。
達観してるとでも言うかな。
「Can’t Stop Thinking About You」はファルセットを活かしたヴォーカルも含めて美メロなバラード。
これも泣き節と言えるけれど、別に狙ってるわけではなく、素直に感動の涙を流せて胸がいっぱいになる。
「Tired Of Midnight Blue」は一転して、怪しい感じがする。
ここだけ異世界に迷い込んだ時のような感触だ。
「Grey Cloudy Lies」もメロウなのだが、地味というか、小粒で印象に残りづらいかも。
でも、こういう曲こそ愛せるのがジョージ・ファンという気がする。
「His Name Is Legs」は威勢がいい。
ファンキーかつコミカルな感もあって、明るくなった「Bangla Desh」のようだ。
重厚かつ華々しさもあるサウンドで、早口の台詞が多用されるなど、仕掛けも凝っている。
前作で落とした評判を覆すことは出来なかったのだけれど、結局これはダメなアルバムだったのか?
いや、そんなことは決してない。
ジョージらしい色になっていたメロウな世界を中心に、あくまでポップに、得意料理を並べてみせた。
後に名プロデューサーになるデヴィッド・フォスターが絡んでいることもあって、AORの文脈で語っても良い。
前作の反省からか、宗教臭さも消えていて、聴きやすいアルバムとなった。
落ち目になったジョージという偏見で見てはダメだ。
アップルに残した置き土産。
もっと評価されてもいいと思う。
(2025.8.18)
力強くポップな「You」で始まるのもいいけど、泣きの「This Guitar」など、メロウなメロディに磨きをかけたジョージ。
荘厳な「World Of Stone」などは、大名盤『All Things Must Pass』の世界観を彷彿とさせるようで。
ジョージのいいとこどりで聴きやすく満足感。
(2024.7.11)
『Thirty Three & 1/3』
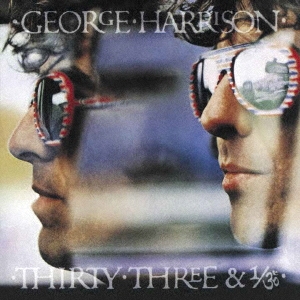
ジョージ・ハリスンが、パティとの離婚、裁判、病気、契約トラブルと、様々な難題を抱えた中で制作、リリースされた作品。
僕は旧盤を持っていなかったので、このアルバムを聴くのは、ダーク・ホース・イヤーズBOXでのリマスター盤が初めてだった。
まず1曲目「Woman Don’t You Cry For Me」に意表をつかれる。
「僕のために泣かないで」なんていうロマンチックな邦題の割に、やけにファンキーでコミカルな曲調。
「ムリにがんばってる感」がジョージらしくないかも。
つづく「Dear One」はどこか宗教臭い。
「Beautiful Girl」も地味で単調...と、この3曲までで、なんとなくこのアルバムに対してネガティヴなイメージの方が先行しちゃうかもしれない。
しかし、しかしだね。
次の「This Song」の素晴らしさをきっちり受け止めようじゃないか。
この元気でキャッチーなポップソング。
ジョージの全曲の中でも、ここまで明るく楽しい曲はなかなかないんじゃないか?と思えるほど。
このアルバム、曲順が悪かったんじゃないかなあ、と。
この「This Song」を1曲目にでも持ってきて、ガッチリつかみはOKてな事にしておけば、評価はまた違ったような気もするなあ。
実際、何度も繰り返し聴いてると、1~3曲目だって、なかなか味わいがある事に気付いてくるんだよね。
さっきはネガティヴなことを書いたけど、それはあくまで第一印象であって、今じゃ結構気に入ってるんだよね。
要は、そこに気付くまで我慢して聴いてもらえるか、が大きい。
特に、後半になれば、またジョージらしい、リラックスしたムードの佳曲が並んでるんだもん。
このアルバム、なかなか捨てたもんじゃないんだよ。
「True Love」なんて、ジョージらしい爽やかでなんともいえない、スライド・ギターのイントロ。
気持ちいい1曲。
「Pure Smokey」は穏やかで、優しく抱いてくれるようなジョージ。
さりげないホーンの響きも好き。
このあたりの曲は、AORと言ってもいいね。
ベスト盤にも収録された「Crackerbox Palace」を挟んで、
本編ラストの「Learning How To Love You」もメロウで、なかなかいい。
これもAOR路線だね。このようなAOR路線を嫌う人もいるみたいだけど、ジョージとAORは合うと思う。
間奏のアコースティック・ギター・ソロも美しい。
そしてボーナス・トラックの「Tears Of The World」は、ジョージならではの泣きメロが光る1曲。
この曲が追加された事で、このアルバムが一段と活力を持ったと思えるのだがどうだろう。
大好きな曲。
てなわけで、前述した通り、曲順にやや難ありな気がして、それがやや散漫な印象を与えちゃってるのではないかと思ってるんだけど、トータルで考えてみれば、ぜんぜん悪いアルバムではなくて、ちゃんといい曲が詰まってるな、と思える。
僕としては、期待以上に良かったアルバムだ。
(2024.9.16)
いよいよ新しいレーベルでの作品作りが可能になるも、レコード会社から訴訟を起こされたり、妻パティとの関係などプライベートも含めて、いろいろとごたごた。
普通なら不振に陥りそうなところだけど、このアルバムでは新しいサウンドを採り入れてるのはもちろん、全体的に明るい印象で、ごたごたを感じさせない。
それがジョージのすごいところ。
「Woman Don’t you Cry For Me」「It’s What You Value」なんかは、今までになくファンキーなノリ。ベースなんかも跳ねちゃってグルーヴィー。
「Beautiful Girl」など、美しいメロディにスライド・ギターがアクセント、というジョージ特有のサウンドを確立。
「This Song」は盗作問題を、とことん明るくキャッチーなポップ・ソングに仕立て上げた素晴らしさ。
逆境での開き直りに、ジョージの反骨精神、ユーモア、芯の強さを見る。
「True Love」は心地良いノリながらも、優しさにあふれている。
「Pure Smokey」は切なく、渋く、ほろ苦くも美しいサウンドが新境地。
「Learning How To Love You」は穏やかで優しく、そしてとびきりメロウ。
虚ろになりそうな一歩手前でとどまっているところに魅力がある。
時代背景もあって、AOR的なサウンドに感じる部分もあるけれど、新味の中にもいつものジョージ節が満載で。
ジョージが抱えている問題なんかは、全然マイナス作用になってない。
むしろ心機一転、やる気に満ちいてるような、元気が出てくるアルバムなんだよね。
(2024.8.3)
『George Harrison』
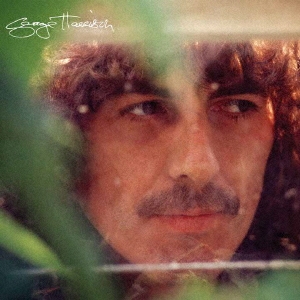
この作品は旧盤CDから持っていたのだけれど、なんといっても、「Love Comes To Everyone」が収録されている事。
この曲、ジョージ・ハリスンの全作品の中で、僕が一番好きな曲と断言していいだろう。
イントロ、Aメロ、サビ、間奏、エンディング、もう全てが完璧、僕のツボ。
初めて聴いた時からもうメロメロだった。
そんな「Love Comes To Everyone」が収録されているアルバムだから、とんでもなく素晴らしいアルバムなのではないかと期待して買ったんだった。
けれど、他の曲に対しても、同じクオリティ、感動を求めてしまったからか、他の曲はあまり印象に残らなかった。
「Love Comes To Everyone」に比べたら、どうしても他が霞んじゃう、という。
だから、このアルバムをジョージの最高傑作に挙げる人も多いと聞いても、僕にしてみたら、「言われてるほど良いアルバムかぁ?」って思っちゃってたんだよね。
でも、ダーク・ホース・イヤーズBOXに入ったリマスター盤を冷静に聴いてみたら。
ある意味、「Love Comes To Everyone」と分けて考えて聴いてみたら。
なんかすごくいいでやんの。
ジョージ、いつの間にこんないいアルバム作ってたんだ?って。
今頃気付いたよ(笑)。
いいアルバムと言っても、ジョージの場合は、さりげなくいい、と言うかさ。
『Cloud Nine』は文句なしの傑作なんだけど、またそれとは違った良さで。
こちらの方が、ジョージ本来の良さを表しているかもしれないけどね。
このジャケットのごとく、穏やかで優しい光に包まれたジョージ。
「Here Comes The Moon」「Blow Away」「Your Love Is Forever」なんかはそうだよね。
「Not Guilty」は、正直言うと、ビートルズ時代の弾き語りデモの方が好きなんだけどね。寂しい感じでさ。
でもまあ、一応これが正規版、って事で。
ちゃんと世に出たという意味では充分OK、かな。
「Soft Hearted Hana」のリズム、コミカルな感じも大好き。
ドブロ・ギターの音が印象的。
この曲って、もしかしてユニコーンの「ブルース」の元ネタか?
それから、「Dark Sweet Lady」における、ハープの響きにはドキッとさせられる。
キーも高くて、「ダイジョブか?」って気になる所もまた良かったりして(笑)。
「Soft Touch」は、眩しい朝日の光、という感じで、キラキラ輝いてるね。
ラストの「If You Believe」は、軽快でノリ良く、キャッチーなサビが印象的で。
自然と笑顔になってしまう。
まあ、穏やかで優しい、というのは、ヘタするとそれが仇となって、地味で印象に残らない、という側面もあるんだけどね。
特に後半は、アレンジが単調な面もあるから。
何度か聴き続けないと、この良さは伝わりにくいかもしれない。
でも、僕はこのアルバムをだいぶ見直したなあ。
以前は、ここまでいいものには思えなかったんだけどね。
毎晩これ聴きながら寝てます。快適安眠。
(2024.9.15)
アーティストがアルバムのタイトルに自分の名前を配する時は、特別な意味がこめられているのだろうか。
それとも、考えるのがめんどくさいからテキトーに自分の名前を付けただけなのか。
日本では、原題がアーティスト名だったことを忘れるくらい、邦題の『慈愛の輝き』というタイトルがしっくり来てる。
このアルバムには、なんといっても僕がジョージの曲の中でいちばん好きな「Love Comes to Everyone」が入ってること。
それだけでもう、充分な価値ありの作品だ。
この曲は、エリック・クラプトンがギターを弾いてる!というトピックだけど、なんでも、イントロのわずかなフレーズだけとか。マジでこれだけ?とガックリも来るけど。
でも、メロウで力強くて、優しくて泣ける。こういう曲を書かせたら、ジョンもポールも敵わない。素晴らしい曲だ。
「愛はすべての人に」。直訳だけど、素晴らしい邦題だ。
虚ろな「Not Guilty」もあるけれど、
「Here Comes The Moon」「Blow Away」「Faster」など、明るいんだけれど、フワフワとして曖昧なコード感が魅力の曲たちが多い。
「Dark Sweet Lady」もAOR的なサウンドだけれど、メロウなところはジョージならでは。
ラストの「If You Believe」は爽やかなうえに、穏やかなノリの良さがキャッチーなメロディに映える。
アルバムのほとんどの曲をハワイで作ったとされていて、その影響が、明るい曲が多いというところで説得力を持つ。
前作も明るい雰囲気だったけれど、あれは新レーベルでの再スタートでイケイケなノリだったのに対し、こちらは穏やかな明るさ。
ジョージの優しさに包まれたアルバムだ。
(2024.8.14)
『Somewhere In England』
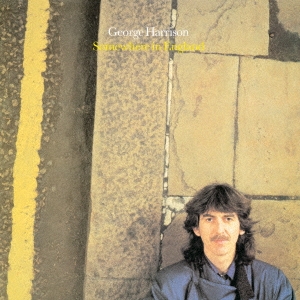
ジョージ・ハリスンが完成させたアルバムにワーナー側がNGを出し、アップテンポのものに4曲差し替えを要求されるという事態に。
さらに、ジョン・レノンの死により急遽、追悼歌「All Those Years Ago」を加えるという経緯を持つアルバム。
ジャケットに関しても、いろいろゴタゴタがあったアルバムで、ダーク・ホース・イヤーズBOXのリマスター盤に際し、当初ジョージの意図してたジャケットに戻された。
ワーナー側の要求に応えた形である通り、アップテンポな、または明るいイメージを持った曲が多いなあ、というのが印象。
冒頭の「Blood From A Clone」「Unconsciousness Rules」からそうだしね。
「ジョージがんばってるなあ、ちょっとムリしてない?」てな気も。
明るくて、どこなくファンキーな香りが、前作『George Harrison(慈愛の輝き)』よりも前々作『Thirty Three & 1/3』に似てるかな。
そんな、多数あるアップテンポなナンバーの中で、一番好きなのは、「Teardrops」。
「This Song」あたりを髣髴とさせる、ポップでキャッチー、憶えやすくて楽しい曲。
でも、たしかにね、アップテンポのものもいいんだけれど、そればっかりで攻められてもねえ。
ジョージの良さは穏やかな曲にあったり、泣きメロの中にあったりもするからねえ。
そういった意味では、明るい曲が多いこのアルバムは、僕の好みか?と問われると、「うーーん」と唸らざるをえないかも。
「おっ、ジョージ得意の泣きメロか?」と嬉しくなる「Baltimore Oriole」は、実はカヴァー曲だったり。
イントロのホーンの響きがやや大袈裟で、演歌かムード歌謡か、という気がしないでもないが(笑)、好きな曲。
さらに、「このアルバムの中では僕好みかな...」と思った「Hong Kong Blues」。
これもカヴァー曲なんだよね(苦笑)。
2曲とも、ホーギー・カーマイケルの曲との事で、この名は憶えておく必要があるかも。
でも、どちらもジョージの作品と思い込んでしまったほど、違和感がなく、ジョージの味を醸し出している。
穏やかなイントロに導かれた後は、タブラの音が印象的で、インドっぽさも若干漂う「Writing’s On The Wall」。
でも、邦題の「神のらくがき」というほど宗教臭さは感じられず、リラックスした雰囲気で聴けるのは好感。
ラストの「Save The World」は、タイトルほど危機感は感じない曲で、ややコミカルな印象さえ。
そんなわけで、全体を通して、やはり明るいイメージのアルバム。
「All Those Years Ago」が入ってるので、話題になることも多いんだけど、暗いのが好きな僕は、いまいちハマりきれないかなあ、という気はする。
いい曲もあるんだけどね。好みの問題というか。
ジョージ自身も、差し替え要求とかジョン追悼とか、いろいろ重なったので、もともと意図してたものとは違ってしまった所に、不満を持ってたかもね。
なんとなく「突き抜けた」感がしないのはそんな所にあるのかな。
(2024.9.17)
ジョン・レノンへの追悼曲「All Those Years Ago」を初めて聴いた時は面食らった。
ジョンが亡くなったというのに、ジョージ・ハリスンはどうしてこんなに明るく朗らかな曲を歌ってるんだ?と。
僕はポールの「Here Today」を先に聴いてたから、ポールがあれだけしんみりと、失った親友への思いを寂しげに歌ってるのに比べて、ジョージの能天気さはどうしてだ、と感じたんだよね。
でも、そこが皮肉屋ジョージ。
楽しさに浮かれ気分の時は、現実の厳しさをチクリとしたり。
逆に悲しい時は、気丈にふるまって、なんてことないさ、と。
それがジョージなんだ、と。
「All Those Years Ago」は、ポールやリンゴも参加して、ジョンの死から5ヶ月後というスピードで世に出た。
ジョージにしてみれば、ほぼ完成していたアルバムが「もっと明るくヒットを狙える曲を入れろ」とレコード会社からNGを食らい、発売延期になって差し替えの曲を練っていたところ。
そこにジョンの訃報があって、元々はリンゴのために書いてあった「All Those Years Ago」を練り直して完成させた。
ジョンが亡くなって、元ビートルズの3人で過ぎ去りし日々を懐かしく思いながらも、僕らは大丈夫だ、というメッセージを出した。
3人の共作に、悲しみに暮れていたビートルズ・ファンも力強く励まされたことだろう。
「All Those Years Ago」はジョージ久々の大ヒット曲となり、それに引っ張られる形で、明るい印象となったアルバムの方も売り上げを伸ばした。
ジョンの死がきっかけとなったのは皮肉なことではあったけれど、レコード会社の思惑通りの結果となった。
冒頭の「Blood From A Clone」「Unconsciousness Rules」からして明るく跳ねまくったサウンド。
しんみりと落ち着いた味わいのメロディとギターなのが「Life Itself」。
泣き節が行き過ぎて、日本のムード歌謡みたいになってる「Baltimore Oriole」も印象的。
明るくポップでキャッチーな曲と言えば、「Teardrops」が筆頭。
カントリーかレイドバックかといったトロピカルな印象の「That Which I Have Lost」。
ジョージらしくメロウで、隠れた佳曲なのが「Writing’s On The Wall」。
胸締め付けられるのが「Hong Kong Blues」。
シビアなテーマも明るく締める「Save The World」。
良い曲も多いし、ヒットしたのも嬉しいけれど、本来ジョージが意図しなかった形で、何かに導かれるように作らされた感のあるアルバムなので、どことなく複雑な気分が抜けないものでもある。
(2025.1.20)
『Gone Troppo』
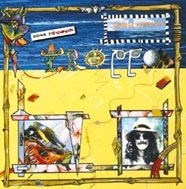
前作はレコード会社にダメ出しされ、作り直した挙句のリリースだったりもあって、だんだん音楽活動に嫌気が差してきていたジョージ・ハリスン。
だからまったくやる気がなく、アルバムが出来上がっても、ジョージはプロモーション活動をせず、レコード会社もまったく宣伝せずで、セールスは散々な結果。
その後、ジョージは隠遁生活に入った。
……というのが、このアルバムにまつわる定説。
やる気もなく、全然売れもしなかっただなんて、よっぽど酷いアルバムだったんかな。
そういうイメージだった。
しかし、そんな思いこみはすべて間違っていた!
どの曲も明るく、素晴らしい内容。
やけっぱちにしては傑作すぎる!
いきなり響き渡る派手なシンセサイザーに導かれる「Wake Up My Love」の突き抜けた感。
ほのぼのとしつつも吹っ切れた感のある「Gone Troppo」。
あまりにもキャッチーなメロディで唱える呪文「Dream Away」。
この3曲が軸になっていて、ワクワクさせてくれる。
「That’s The Way It Goes」はゆったりとトロピカルなサウンドでレイドバック。
「Greece」はスライドやリフなどギターの音色が心地良く、コミカルなメロディや展開の妙もジョージらしい。
「Unknown Delight」はメロウで美しいサウンドとメロディ、スライド・ギターと、ジョージの得意技が詰まっている佳曲。
唯一、ラストの「Circles」だけが憂いのあるメロディでピリッと締める。
売れなかったことが駄作である証拠だということは、まったくのデタラメだというのは、このアルバムを聴けばわかる。
陽気で、聴いてて終始良い気分でいられる。
『Cloud Nine』に繋がるクオリティがここでも保たれているのだ。
「売れなかったやつでしょ」と軽視してはならない。
こんなに売れなかった傑作はなかなか他にない。
(2025.2.2)
『Cloud Nine』

これが初めて聴いた、しかもリアルタイムで体験できた、ジョージ・ハリスンのソロ・アルバム。
そしてその第一印象が「だ、誰だよ、近年のジョージはパッとしないって言ったのは。ものすごい良いじゃないか!!」だった。
僕が高校1年の頃だ。
このアルバムの大きなポイントは、プロデューサーに、ジェフ・リンを迎えた事にある。
ジョージとジェフが出会ったのは運命でもあったと思うけど、やはり奇跡でもあったと思う。
この出会いには心から感謝したい。
僕がこの作品を手にしたのはレコードだった。
CDでも出たけれど、買い直すのはなんとなくためらってそのままに。
だから、こうしてちゃんとCDを手に入れるのは、BOXセットのリマスター盤が初めてとなる。
まず冒頭の「Cloud 9」を聴いた時、「ああ、こんなジョージが聴きたかったんだよ」と感じたのを憶えてる。
ジョージのソロに求めていたものが、ピッタリ合った快感。
いかにもジョージとクラプトン、というイメージの、「While My Guitar Gentry Weeps」的な、マイナー・メロにゾクゾクしたね。
続く「That’s What It Takes」。
1曲目がジョージとクラプトンなら、今度はジョージとジェフのイメージだ。
アコギの響かせ方がいかにもジェフ。
メロディも綺麗で、ジョージのさりげない優しさもにじみ出ている佳曲。
この2曲を聴いただけで、「これは名盤だぞ」と確信を持ったよね。
「Just For Today」は、ジョン・レノンを髣髴とさせるバラード。
ジョージとジョンが共作しているようで、なんだか嬉しかったな。
「This Is Love」はとことんポップでキャッチー。
シングルとして相応しい出来だよね。大好き。
「When We Was Fab」も大好きな曲。
中期ビートルズをイメージさせる仕掛けが一杯。
何度聴いても飽きない。
レコードではここからB面となって、「Devil’s Radio」。
この曲もポップで楽しく、派手。
ある意味、ジョージらしくないかもしれない。
でも、これがまたいいんだよな。
「Someplace Else」は、実は以前はあまりピンとくる曲ではなくて、よく飛ばしてた(笑)。
でも、このBOXのDVDの中で、この曲についてジョージがコメントしているのを聞いたら、なんだか急にいい曲に思えるようになったんだよね。
ギターもすごくいいし。
ジョージらしい、穏やかな感じがさ。
そう思ってからは、もうメロウなこの曲の虜となった。
「Wreck Of The Hesperus」と、それから、書き忘れたけれど、前半の「Fish On The Sand」なんかもそうだけど、すごく元気で力強い曲も多いんだよね、このアルバムって。
非常に前向きなんだよな。それがいい所なんだろう。
それから、東洋的な臭いのする「Breath Away From Heaven」は『上海サプライズ』の延長線にあるのかな。
そう思って聴くと、味わい深い。
そして本編最後の「Got My Mind Set On You」。
この曲も明るく楽しく、とにかく調子のいい曲。
いかにもアメリカ受けしそうで。
MVも何回も観たなあ。
年末年始前後だったかなあ、全米1位を獲得した時は、ホント嬉しかったね。
「そらみろ、ジョージはすごいんだぞ」って。
オリジナル・アルバムとしてはここまでなんだけど、とにかく、何度も書いたように、ジョージが非常に明るく元気で輝いてるアルバム。
ジャケットの笑顔そのままなんだ。
そして、全体的に明るいアルバムではあるんだけれども、「Cloud 9」「When We Was Fab」のような、マイナー調ロックも渋くキメてるあたりが最高で。
だからもう、僕の中ではやっぱりこのアルバムが一番思い入れの深いものになっているんだよね。
捨て曲なし。とにかく素晴らしい、の一言だ。
でもって、ボーナス・トラックが2曲。
「Shanghai Surprise」も素晴らしい曲。
いかにも、怪しげな中国風イントロで始まって...女性ヴォーカリストを起用して、ジョージとヴォーカルを分け合ってるのも、なかなかスリリングでいいんだよね。
まともに聴いたのは初めてだったんだけど、すごく気に入っちゃってさ。
今まで埋もれてたのがもったいないよ。
「Zig Zag」の方は、「When We Was Fab」のドーナツ盤を持ってたから、そのB面として既に持っていた。
いかにもB面曲といった感じの、実験的な面白い曲。
これもなかなか好き。
というわけで、もともと素晴らしかったアルバムに、聴き応え充分のボーナス・トラックが加わり、さらに魅力的な盤となった。
久々に通して聴いたけど、その輝きは失ってないどころか、増しているように思える。
ついついリピート押しまくりなのだ。
(2024.9.14)
『All Things Must Pass』とバングラデシュ・コンサートでロック界の頂点を極めたものの、「Give Me Love」が全米1位を記録したのを最後に、売り上げは徐々に下降し、離婚や盗作騒ぎや、喉を傷めて強行したツアーも不評、どんどん低迷していき、『Gone Troppo』なんて全く宣伝する気にもならなくて、その後は隠居状態。
僕がビートルズを聴き始めた1987年、ジョージ・ハリスンのソロ活動の歴史と現況のイメージはそんな感じだった。
ジョージはもう終わったのか?
そんな時に、突如NEWアルバムをリリースするという知らせが。
低迷してるというジョージ、どうなのよ、と不安混じりで買ってみた。
しかし、堂々と笑顔でギターを構えているジャケットの姿に、これはけっこう自信ありなのでは?と期待が膨らんで、レコードに針を落とした。
エリック・クラプトンが参加すれば、こんなクールなギター・サウンドになるのは当然とばかりの「Cloud 9」でいきなりノックアウト。
アコギとスライド・ギターの音が優しい「That’s What It Takes」は胸キュンなメロディで、コーラスもキャッチーで心に残る。
ジョン・レノンを想起させるバラード「Just For Today」に涙。
ようやく吹っ切れたのか、ビートルズ・サウンドに真正面から向き合った「When We Was Fab」の粋なこと。
ジョージの穏やかでメロウな魅力が最大限引き出された「Someplace Else」「Breath Away From Heaven」には胸がいっぱいになる。
そして、このアルバムの特徴として、「Fish On The Sand」「This Is Love」「Devil’s Radio」「Wreck Of The Hesperus」「Got My Mind Set On You」と、ポップで力強さを感じる曲が満載なことが挙げられる。
やる気がない人には出せない、圧倒的なパワーを感じる。
美メロ、煌びやかなサウンド、力強いリズム。
一度聴いただけで、すっかりやられた。
凄いじゃん、ジョージ。
ぜんぜん低迷なんかしてないじゃん!
こんな素晴らしいアルバムでも売れないというのだったら、世の中間違ってる!
そう思ってたら、あれよあれよという間に大ヒット。
ジョージ復活の大傑作との評価を得ることとなり、そうだろうそうだろうと、とにかく嬉しかった。
ジョージをやる気にさせ、底力を引き出したのは、やはりジェフ・リンの力と采配によるところが大きいんだろうけど。
でも、いったい誰がジョージとジェフをひき合わせ、プロデュースする運びとなったんだろう、と。
僕はすっかり、ビートルズ・フリークとしても有名だったジェフの方から売り込みに来たんだと思ってた。
そして、ジョージの尻を叩いて、なんとかやる気にさせたのだと。
でも事実は逆で、ジョージの方がジェフに興味を持って、なんとか伝手を辿って会うことが出来たらしい。
そして余程ウマが合ったのか、親友と呼べる間柄になり、この信頼できる友とアルバムを作りたい、という決断に至ったという。
『Cloud Nine』のビートルズっぽいサウンドは、ジェフの趣味だけでそうなったのではなく、ジェフの音作りがそういうものであることを承知の上で、ジョージが接近したわけだから、ジョージが望んで出来たサウンドだったのだ。
(2025.3.31)
『Live In Japan』

ジョージ・ハリスンのダーク・ホース・イヤーズBOXセットを手に入れて、どういう順番で聴こうか...やっぱり年代順?とか考えてたのだが、まずはコレに手が伸びた。
一聴して、グッと音が良くなったとわかる程ではないのだが、全体的にマイルドな音になった感じ。
そう思って旧盤を聴き返してみると、高音がややキンキンして聴こえるかもしれない。
それが、今回は落ち着いた感じになっているし、各楽器の音量バランスにも手が加えられ、ハッキリ分離して聴き取れるし、臨場感も増している。
普通のCDヴァージョンで聴いてもこれだから、SACDで聴いたら、さぞ良い音なんだろうなあ。
そしてこの盤、5.1chサラウンドのSACD対応のため、実はミックスし直してあるとの事で。
だから、リマスターどころか、リミックス盤らしい。あまり大きく語られてないけど。
だから、実はいろんな所に違いがある。
たとえば、「Something」。
この曲は、イントロがギター・ソロから入るのだが、その部分では、観客は何の曲やらわからず、反応イマイチ。
そこへ、本来の「Something」のイントロ・フレーズが弾かれて、観客が理解し大歓声...というのが、旧盤の形だった。
しかし今回は、イントロのギター・ソロが始まった時点で、観客が歓声を上げる形になっている。
そのため、通常のイントロ・フレーズが弾かれた時の大歓声はナシ。
うーん、これは...。
実際にライヴを観た者の感覚としては、前者が正しい反応なんだよねえ。
見事に、歓声が処理されちゃっている。
歴史を改ざんされた感?
他にも、「Cheer Down」の曲前のMCがカットされていたりと、ちょいちょい手直しされているのだ。
僕が確認できただけでも、これだけあるのだから、マニアが聴けばわかるであろう、リミックスされた結果の「違い」はもっとたくさんあるのだろう。
となると、廃盤状態の時に高値で取り引きされていた旧盤、再発で価値を落とすかと思いきや、実は細かな違いのあるレア盤という事で、手放せないよね。
まあ、この作品の内容そのものは改めて言うまでもなく。
とにかく、ジョージの代表曲のオン・パレードといった感じで、クラプトンらと共に、リラックスした演奏を聴かせてくれる。
ただ...実際にライヴを経験した僕からすると、「実際のライヴの感動はこんなもんじゃなかった」という思いがあるからか、旧盤は、それほど聴き込まなかったんだよね。
クラプトンとジョージのギター・プレイを交互に楽しめたりするし、【あの時の良き思い出】として永遠に残しておきたい作品。
(2024.9.13)
『Brainwashed』
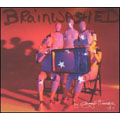
あまり「これが最後の...」と思わず、いつものジョージ・ハリスンのアルバムを聴くように、気楽に楽しもうという気持ちで臨むのがいいかもしれない。
ジョージも、ファンにそうあってほしいとでも言うように、いつものジョージを出してくれていた。
僕がイメージしてた通り、期待してた通りの音がそこにあって、非常に安心感のあって、満足できたアルバム。
『Cloud Nine』時に感じたような「これは売れ線!大ヒット確実!」というような曲はないけれど、佳曲揃いだし、アルバムとしてとてもよくまとまってる、いい作品だと思う。
1曲目の「Any Road」から楽しい。
バンジョーのようなウクレレのような【バンジュレレ】の軽快な音に乗せて歌うジョージ。スライド・ギターも当然のように登場。ジョージの存在をアピールするに相応しい素晴らしいオープニング。
新作はトラヴェリング・ウィルベリーズっぽい音になるだろうとの予想通り、オープニングのこの曲からウィルベリーズを思い出させてくれる。
「The Devil’s Been Busy」っぽいかな。
転調するところなんかでは、ついディランあたりとリード・ヴォーカル交代するんじゃないか、って錯覚さえ(笑)。
病気がどの程度レコーディングに影響あったのかという事で、特に心配されていたヴォーカルも、「いつものジョージそのもので、元気」との情報で安心していたのだが、唯一「P2 Vatican Blues」だけは、僅かだが違和感を感じた。
曲自体は、これまた軽快でとてもジェフ・リンらしいアレンジ。
「Pisces Fish」はほんのりと憂いの漂うバラード。
「Just For Today」と重なる部分もあるのだが、あそこまで暗くなってなくて。
「Come Together」を髣髴させる「シュッ」が入るあたりも面白いけど、全体的にはゆったりとした流れが心地良いこの曲、ハミングのパートも含めて、なんだかジョージの「余裕」を感じてしまう。
かなりの名曲なのでは??
「Rising Sun」で、ウクレレかバンジュレレに聴こえる音の主はなんだろう。
この音はもちろん、スライド・ギター、ストリングス、コーラスの使い方がジョージの曲らしく、また、歌われているテーマを含めると、ジョージの代表曲になるのでは?という気が。
インストにはあまり興味のない僕だけど、「Marwa Blues」はついつい聴き入ってしまう、不思議な魅力がある。
美しいだけではなく、次はどんな音が飛び出すかな?と真剣に耳を傾けてしまう。
「Strawberry Fields Forever」的フレーズが飛び出すところにはニッコリ。
「Stuck Inside A Cloud」もいいなあ。
サビのじわじわとした盛り上がり方。
これぞジョージ。思わず胸が熱くなってしまう。
「Run So Far」は、昔、クラプトンのヴァージョンを聴いた時、あまりジョージっぽくないなあと思ったのだけれど、ここでこうして聴くと、いかにもジョージっぽいじゃん。
「Rocking Chair In Hawaii」は、トロピカルなリフが印象的。
現代版「For You Blue」?
こういう雰囲気の曲、ジョンが好みそう。
ジョンだったらもうちょっとレゲエっぽくするだろうけど。
最後の「Brainwashed」がまたカッコいいんだわ。
重いイントロからして「来た来た~っ!」って感じ。
キレ気味に歌うジョージに、「♪ God God God」のコーラス。
一旦ブレイクして、美しいハープの音とスライド・ギターに心和ませられた後、タブラが入ってインド風になる間奏も聴き所。
それからまたAメロに戻るあたりにも感動するし、ラストはジョージならではのマントラといった展開も素晴らしい。
アルバムのラストを飾るに相応しい大作だ。
というわけで、非常に満足して聴き終わった。
しかし、何故か「15年振りの新作」というような気はしなかった。そうか、15年も経っていたのか、と。
一度聴いただけで「いいな」と思ったけれど、二度目、三度目と聴く度に新たな良さがわかってくる。「期待してた以上」に楽しんでいるかもしれない。
たまに、『All Things Must Pass』や『Cloud Nine』のような会心の一撃を繰り出した事もあったけれど、基本的には「パンチ力のなさ」が愛すべきジョージ。
だから、このアルバムも、あえて傑作や名作とは言わずに、「いいアルバム」と言いたいな。
とにかく、ジェフ・リン、ダニー・ハリスン、いい仕事してくれたよ。
親友・父親を失った悲しさが癒えていない中、こういう仕事をするのは大変だったと思う。辛い作業だったと思う。
でも、「このアルバムを仕上げる事がジョージの願い」という使命感で乗り切ったのだと思う。この出来には絶対ジョージも満足するはず。
この素晴らしいアルバムを作り上げたジョージにはもちろんのこと、この二人にも大きな拍手を贈りたい。
(2024.8.27)
『Best of Dark Horse 1976–1989』
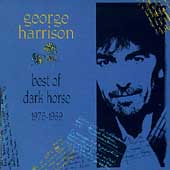
僕が初めてジョージ・ハリスンのソロを聴いたのは『Cloud Nine』。
そのあまりの素晴らしさに、すっかりジョージのファンになったものだ。
それまでのジョージのソロは、76年までのEMI期、レコード会社を移してのワーナー期と分かれていたのだけれど、ロック界の頂点にまで昇りつめたEMI期に比べたら、ワーナー期はかなり売り上げが落ちて、寂しい作品の連続、というイメージがあった。
そんな折、『Cloud Nine』とトラベリング・ウィルベリーズの大成功によって、ジョージに再び注目が集まっていた89年に、ワーナー期の曲を集めたベスト盤が出ることになった。
ジョージのソロに興味を持っていても、この当時はまだワーナー期のオリジナル・アルバムはCD化されてなかったから、とりあえずのベスト盤は渡りに船だった。
とはいえ、売れなかった時期の曲たちなので、どんなもんかいな?という疑義の念はあったのだけれど。
目玉と言えたのが、3曲の新曲。
「Poor Little Girl」「Cockamamie Business」、どちらもマイナーな泣きメロのうえ、力強くてカッコいい。
前者のアルペジオとか、いかにもジョージらしいギター・プレイにも惹かれた。
「Cheer Down」はトム・ペティとの共作で、ジェフ・リンが共同プロデュース。
スライド・ギターが炸裂し、明るい未来へ連れて行ってくれるような曲。
3曲とも、『Cloud Nine』に入っててもおかしくない、充実したジョージの延長線上にある素晴らしいものだった。
既に知っていた曲は『Cloud Nine』収録の3曲。
それから、ジョン・レノン追悼でヒットした「All Those Years Ago」。
それくらいだったと思う。
派手な「Wake Up My Love」には少々驚いたけれど、他の曲は概ね穏やかで、心が軽くなるような素敵な曲ばかりだった。
そして、なんといっても「Love Comes To Everyone」。
優しくてやるせなくて、絶望から希望へと誘ってくれるような、なんとも心が温かくなる曲。
ジョージに、こんなに素晴らしい曲があったのかと。
この1曲に出会えただけでも幸せなことだった。
ワーナー期は売れなかったということだけれど、曲はこんなにも素晴らしいものに満ちていた。
ジョージはいつの時代も凄いじゃないかと感激した。
思い入れのありすぎるベスト盤だ。
コレが出たのが89年10月。
僕が大学受験のテストを受けたのが11月。
試験直前に、ジョージに大きな力をもらっていたんだなと、いま改めて気付いた。
ありがとう、ジョージ。
お蔭で、今の僕がある。
(2025.4.16)
『Dark Horse Years』
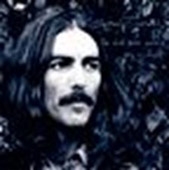
うーん、すごい。
このジョージ・ハリスンのダーク・ホース・レーベルBOX。
CD再発うんぬんじゃなく、DVDだけでもものすごい価値があるぞ。
観た事ないMVたくさんあるし、ライヴ4曲は、クラプトンとの日本公演だし。
絶対欲しい!欲しい!
しかし、日本盤は、CCCD。
頼りは輸入盤だけど、どうやらUK盤はDVDがPAL方式なので×。
で、US盤がリージョンフリーらしい。
よって、US盤購入決定。
BOXものって、なんだか手に入れただけで嬉しい。
豪華な装丁を眺めながら、何度もCDを出し入れしたりするだけで至福の時を過ごせる。うーん、幸せ。
しかし、やはり、肝心のDVD。ちゃんと観れるのかどうかが心配。
一応、日本でも再生可、という情報だったけれども、なんせ輸入盤、やはりこの目で確かめるまでは安心できない。
早速、DVDをプレイヤーに差し込む。
映った!!
ジョージが動いてる!
「皆さん、こんにちは。ジョージ・ハリスンです。覚えてる?」
この言葉に、早速ジ~ンと...。
無論、覚えてるよ。
でも、そうだよな、ジョージはもういないんだよな...。
改めて、ジョージがこの世にいない事を実感しながらも、こうして観ていると、今でも生きている、と思えてならない、不思議な気分。
冒頭の10分間は、様々なインタビュー映像を交えながら、ダーク・ホース時代のソロ活動の歴史を振り返る。
このDVDに収録の映像が、ダイジェスト的に挟み込まれる。
来日時、空港に到着した時の模様を伝えた、フジテレビの映像まである。
そして、MV集やライヴ映像となるのだが、各曲ごとに、ジョージのコメントが入ってるのが嬉しい。
各曲にまつわる(或いは、つながる)話が聞けて、興味深い。
「This Song」は、MVを観るのはもちろん、もしかしたら、曲自体聴くのこの時が初めてだったかも。
とてもポップでキャッチーな曲で、一発で気に入った。
何故こんないい曲がベスト盤に入ってなかったのだろう?
「Got My Mind Set On You」は、2種類のMVが収められている。
僕が見慣れている、暖炉の前でジョージがギターを弾いたり踊ったり(家具も踊って楽しいね)、というのはヴァージョン2の方だった。
で、ヴァージョン1の方は、カップルがゲームセンターで遊ぶ姿に、ジョージたちのバンド映像が挟み込まれるものだけど、これ、僕はまったく観た事なかったなあ。
そのバンドには、ジェフ・リンの姿もあって、すごく嬉しかった。
ジョージとジェフって、『Cloud Nine』以降、かなり活動を共にしてきたけれど、こうして一緒に演奏してる映像ってのは、意外と少ないんだよなあ。
というか、そもそも、何故2パターンのMVが作られたんでしょ。
何度観ても面白いのが「When I Was A Fab」。
これ、大好き。
さすがゴドレイ&クレーム。
間奏後、ジョージのアップからカメラが引いて、リンゴと、『Imagine』のレコードと、セイウチ「ポール」の姿が映る瞬間は、いつもゾクゾクする。
そして、一番のお楽しみの日本公演のライヴ映像。
正直言って...かなりの期待をしてた割には、という感じではあった。
アップの映像が多く、会場全体を映してる映像がないから、東京ドームだ、という気があんまりしなくて。
収録されているのが、何日の公演の模様なのかクレジットもないから、僕が観に行った日なのかどうかもわからない。
なので、「ああ、あの時のライヴなんだ...」みたいな感動はいまいち得られなかったな。
でも、一番見応えがあったのは「Cloud Nine」。
この曲では、ジョージもギター・ソロ弾いてたんだね。すごいカッコいい。
クラプトンがギターのヘッドにタバコを挿しているのもハッキリわかるし。
で、この日本公演の映像、ブックレットのクレジットと、実際に収録されているものとは曲順が違うんだよね。
何故?単なる間違いか?
そして、最後に、映画『上海サプライズ』に関する映像とインタビュー。
「Shanghai Surprise」も「Hottest Gong In Town」も、ちゃんと聴くのは初めてだったけど、いい曲だよね。
売れなかっただの何だの言われるけど、ジョージにハズレ曲はないよ。
そんなわけで、75分間、感動たっぷり見応えたっぷりのDVD。
このDVDを観るためだけに12000円を払ったのだとしても、惜しくはないよね。
日本語解説書?んなの、どーでもいい(笑)。これで充分満足。
このDVDは、単なるオマケではないよ、うん。
なんだか、ジョージに対する愛情がたっぷりこもったBOXセットだなあ、と思ったよ。
ホント、買って良かった。BOX万歳、US盤万歳。
そして、長らく廃盤だったアルバムもリリースされたわけだけど、あの曲やこの曲はどーなったの?と、未だ完全収録されたわけではない、ジョージ・ハリスン公式音源。
行方が気になります。
(2024.9.12)
『Quiet N’ Loud』
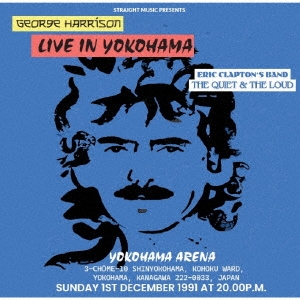
ジョージ・ハリスン&エリック・クラプトン、1991年の日本公演。
その初日、横浜アリーナの音源。
もちろん、公式に録音されたものではないと知ってたから、海賊盤の類であることは承知してたんだけど、わざわざ解説書まで付けた日本盤が2025年、リリースされた。
それならもしかしたら、音質もかなり良いものなのでは?と、おそるおそるだけど買ってみた。
それで、期待を込めて再生してみると。
なんじゃ、この音は。
演奏の音よりも、観客の声や拍手の方が大きい。
かなりボリュームを上げないと、演奏がよく聴こえない。
あー、これはハズレだわ。
やっぱりブートはブート。
期待しちゃいけなかったか、と落胆。
ただし、これを買ったのは大きな理由がある。
この横浜アリーナだけで演奏された曲があるからだ。
「Love Comes To Everyone」。
ジョージのソロの中で、いちばん好きな曲。
これをしかと聴きたかったのだ。
始まり方はモタモタして、締まりがなかった。
でも、さすがに名曲。
演奏が進むうちに良くなっていく。
温かで切ないジョージのメロディ。
間奏のギター・ソロはジョージが弾いてるのだろうか。
その後のキーボード・ソロにも胸が高まる。
エンディングのギター・ソロがクラプトンということなのかな。
たしかに、たしかに「Love Comes To Everyone」は日本で演奏されていた。
ていうか、ライヴで演奏されたのは後にも先にもこの日限り。
それが確認できただけでも、買った価値はあったかもしれない。
でも、何故2日目以降はセットリストから外したか。
そんなに悪い出来にも思えないけど。
ウケが悪かった?
うーん、どうなんだろう。
何度聴いても理由はわからない。
その他も、セトリから外されることになる「Fish On The Sand」、
ジョージがいったん引っ込んでる間に、クラプトン・バンドで演奏された4曲。
そして、短いながらも曲紹介やMC、日本語での挨拶など。
正規盤の『Live In Japan』ではカットされた、あれやこれやが聴こえてきた。
ラストの「Roll Over Beethoven」では、観客とコール&レスポンスしてたり。
あれ、これって東京ドームでもこうだったっけかなあと、思いを巡らせる。
音質はやっぱり良くなくて、特にキーボードの音がかなり小さかったりとか、気になるところは多々ある。
これはスピーカーのボリューム上げても改善しそうもないので、ヘッドホンで聴いてみるのがいいかもしれない。
もちろん、さらに音の酷さに愕然とさせられる可能性もあるのだけど。
最初は、音の悪さにガックリ来て、買ったことを後悔もしたけれど、聴くに堪えないほどではない。
それならそれでと割り切って、これは「Love Comes To Everyone」が演奏されたことを証明する、貴重な記録だ、と。
よくぞ残ってた、と思えば印象も変わる。
編集がされてないことで、ライヴの良い面も悪い面もリアルに浮き彫りになってる。
最後のジョージの「オツカレサマデシタ!」は、笑えるし、なんだか泣けてくる。
(2025.2.25)


コメント