
セルフ・カヴァーではなく、再定義とは?
2024年初頭。
過去の曲をコヨーテ・バンドでレコーディングしているというニュースが入った。出来ればアルバムとしてまとめたい、と。
次のアルバムはセルフ・カヴァー集か。
セルフ・カヴァー・アルバムなら、過去にもホーボーキング・バンドとして『月と専制君主』や『自由の岸辺』があった。
あれの、コヨーテ版ね。
そんな印象だった。
しかし、その後の声明で、佐野さんは「これはセルフ・カヴァーではない、コヨーテ・バンドによる再定義だ」と発言。
僕も最初は、そっかそっか~なんて、わかったような気でいたけれど。
でも、そもそも、セルフ・カヴァーと再定義、その決定的な違いは何なんだろうか。
そう突き詰めると、なんだかわからなくなって、モヤモヤしてしまった。
これは、佐野さんにしかわからない呪文のようなものなのか?
どうにも釈然としないのは、それがわかった時に、我々ファンは、その再定義曲を芯から楽しめるようになる気がするからだ。
そして、第1弾の配信シングルとして「Youngbloods (2024)」がリリース。
「ハロー、エヴリワン、ヤングブラッズ2024、カモン!」という挨拶に胸が高鳴ると共に、そのサウンドの変貌ぶりに、佐野さんの言わんとしていたことがぼんやりわかりかけてきた。
それから夏に行われたツアーで、「Youngbloods」以外の再定義された曲のいくつかを耳にすることになる。
大きくイメージが変わったもの、それほど変わらないものとあったが、どれもがパワー・アップしているということは実感した。
アルバムとしてまとめられることに期待が高まる。
そして2025年元旦。
第2弾の配信シングルとして「つまらない大人にはなりたくない」がリリース。
このタイトルを聞いて、一瞬戸惑いを見せた後、「あの曲か!」と、ファンの誰もが思ったことだろう。
今回の再定義は、場合によっては曲のタイトルまで変更されるのだ。
英語だったタイトルが日本語になったりとかは、今までにもなかったわけではないけれど、この曲のような大胆な変更は、誰しもが驚いたはずだ。
今回の再定義における、佐野さんの並々ならぬ意志の強さのようなものが、これだけでも伝わってくる。
そうしてまとめられたアルバム。
タイトルは『HAYABUSA JET I』。
ファンにはお馴染みの逸話だが、テレビ番組『ダウンタウンなう』に出演した際、「佐野元春という名前に飽きた、隼ジェットにしたい」と発言して、ダウンタウンのみならず、視聴者を大爆笑させた。
いかにも天然らしい佐野さんだなあと思っていたけれど、佐野さんはいたって本気だった。
過去の曲でまとめたアルバムにHAYABUSA JETと名付ける。
まさしく、佐野元春が隼ジェットになるということではないか!
そして、収録曲は全10曲。
セルフ・カヴァー集というと、採り上げる曲としては、隠れた名曲にスポットを当てるものになることが多いのだけれど、今回は6曲がシングルとしてリリースされたもの。
つまりは、代表曲を集めたような豪華さがある。
逆に言うと、そんなに代表曲ばかり作り直してしまって大丈夫?という不安も首をもたげる。
代表曲とはその名の通り、佐野元春のイメージを作り上げて来た曲の代表なわけだから、それらを多く改変することによって、今までの佐野さんが築き上げてきたものを否定する意味合いだとかが含まれないか。
現代のサウンドに迎合するあまり、せっかく普遍性をもった原曲の素晴らしさが損なわれてしまうようなことはないのか。
そんな思いもあったのは事実だ。
しかし、僕たちは信じていた。
なんといっても、相手は佐野元春だからだ。
ファンを裏切るようなことは絶対にしないアーティストであることを知っているからだ。
サポートするのは、20年間、佐野さんと行動を共にしてきたコヨーテ・バンド。
もはや、ハートランド、ホーボーキング・バンドを超えて、佐野元春というアーティストの魅力をいちばん引き出せるバンドだ。
悪くなるはずがない。
もう、そこには期待しかなかった。
待望のリリース、歌詞カードにおける新しい表現
そして、佐野さんの誕生日の前日、2025年3月12日、待望のアルバムがリリースされた。
冒頭の「Youngbloods」、配信版と違って、ハローエヴリワンの挨拶が消えていた。
早速のサプライズでもあったが、ここにも意味があるのだろう。
熟慮を重ね、完成したこのアルバムには、至るところに佐野さんの意図が含まれているのだろう。
それを読み解くのもファンとしての喜びだ。
アルバムは、想像以上に聴きやすく、すんなり体に沁み込んでくる。
原曲と、どこがどう違うとか比較したり、難しく考えたりしなくても、いま聴こえてくる音が心地良いと本能でわかる。
日本語にこだわって、歌詞カードは縦書き。
詩集を読んでるかのよう。
それを目で追いながら聴いていると、歌詞カードに書いてある通りに歌ってない!
でも、言ってることは同じだ!
英語で歌われてる部分が日本語で書かれていて、聴きながら、言葉が脳内で変換され繋がる感じが面白い。
中には、特に「街の少年」のように、歌詞カードに書かれている字面と、実際に歌われている言葉の並びとはまったく別物とも思えるものが多々あって、だけど意味合いは同じであるという感覚は、挑戦と言うより、新たな発明と言える表現方法だ。
現在の日本の音楽シーンは世界に目を向けているけれど、佐野さんはむしろ、80年代や90年代よりも、日本語の重要性に目を向けているように思える。
音と言葉が膨らませるイメージから浮かび上がる、僕たちへのメッセージ。
間違いなく今を生きていると実感するサウンドに興奮する。
『HAYABUSA JET I』全曲解説
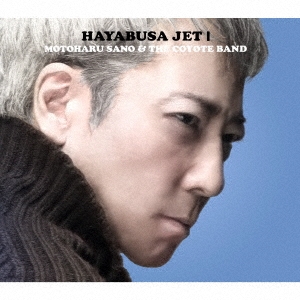
「Youngbloods」。
イントロ、さらにスタイル・カウンシル「Shout To The Top」に寄せてきた!
よりジャジーでシリアスなピアノにして、あえてスタカン感を強調した。あっぱれ!
ところどころ歌詞を変え、ビートがクールで無駄な音は一切なし。
新たなグルーヴ、カッコいい。
いまだに原曲「ヤングブラッズ」をスタカンのパクリだと馬鹿にし批判している人がいるが、このNew Versionを聴け!と言いたい。
さらに似せてきたぞ!
だけど、2024年最新形サウンドになってるというマジック。
これが批判に対する佐野さんの回答だ。
カッコいい!
そして、原曲よりキー下がってる?
「♪ 君だけを固く抱きしめていたい」のところ、原曲だと僕はあんな高い声は出せないのに、今度のヴァージョンは楽に一緒に歌える!
逆境にあっても、立ち向かえる若さが眩しい。
愛しい人といれるなら、どんなことでも出来ると思える心。
でも、それは若さの特権だと思わないで、何歳になっても忘れてはならない。
その時の思いを絶えず胸に秘めていれば、エネルギーは湧いてくる。
そんなことを佐野さんは教えてくれてるんじゃないかなと、いま感じる。
「つまらない大人にはなりたくない」。
ご存知の通り、「ガラスのジェネレーション」をコヨーテ・バンドとして再定義した楽曲だ。
タイトル変更は、佐野さんが想定してた以上に独り歩きしすぎた「つまらない大人にはなりたくない」というキラー・フレーズを、しっかり捕まえたという感じだ。
今度は僕の思惑通りに届いてくれよと、佐野さんが自分のコントロール下に置いた。
この新しいヴァージョンは、配信リリースされた時から、ネット上では「胸アツ」とばかりに賞賛の声が多いのだけれど、「正直、ピンと来ない」という意見が見られたのも事実だ。
たしかに、「ガラスのジェネレーション」にあった、若さほとばしる、つい飛び跳ねたくなるような躍動感は失われている。
「つまらない大人にはなりたくない」は、地を這うような唸るビートを軸に、スペイシーなピコピコ・サウンドが彩を添える。
「境界線」「銀の月」などを思い出す、まさにコヨーテ・バンドお得意のポップ・ビート・サウンドになっている。
個人的には、これはこれで良いアレンジだし、なにしろ、もう長い間ライヴで採り上げることがなくなっていた「ガラスのジェネレーション」が、生まれ変わってライヴで聴けると思うと、良かったなあと思う。
歌詞カードを見ると「Maybe」を「たぶん」ではなくて「たぶんね」と表記したところが良い。
壊れやすい心を持った者たちは、革命を起こすようなパワーもないし、そんな時代でもない。
革命どころか、愛するひとりの人を変えることさえ出来ないのだから。
だけど、そのままだと、行きつく先はつまらない大人。それをどう打破すべきか。
その答えを明確に提示してくれてるわけではないけれど、この曲を聴いてると、なんだか目指すべき場所がわかってくるような気がするんだ。
それは、いま何歳の人が聴いても、きっと同じだと思う。
ラストの佐野さんの「アギャギャギャギャ....」という叫びを聴いてると、そうだ、負けていられないと、パワーが漲ってくる。
このコヨーテ再定義アルバム、原曲とイメージが変わらない曲と、ガラッと変わった曲とがある。
大きく変わったものの1つが、
「だいじょうぶ、と彼女は言った」だ。
柔らかくも虚ろなイントロの音に惹きこまれる。
浮遊感溢れるアレンジが戸惑いを表現している。
こんなに切ないメロディの曲だったとは!
マイナー・キーになったことが功を奏した。
やがて強い意志が込められた演奏に固まっていく。
狂乱と言ってもいい現在の世の中には、本当に戸惑うことばかりだ。
でも、何があっても、夜明けは来るし、助けてくれる人も現れる。
悲しむ必要はない。
新しい明日へと希望の目を向けていけば大丈夫だと教えてくれる。
素晴らしく生まれ変わった、お気に入りの曲だ。
このアルバムは、現代の音楽として捉えられるように、全体的に、ビートとかリズムに特に気を配ってることがわかる。
「街の少年」。
原曲「ダウンタウンボーイ」も疾走感溢れる曲だったが、ここではさらにテンポ・アップして、よりスピード感が増している。
それだけでも、好きな曲がさらにテンション上がるところだ。
普通の人は歳を取ると、動きは遅くなるんだよ。それは当たり前なんだよ。
音楽だってそうだ。
ベテランのミュージシャンの奏でる音楽は、総じてゆったりとしたテンポになっていくものだ。
しかし、佐野さんは違う。
現実では70歳近い佐野さんが、この曲では更なるスピードを追い求めた。
街の少年がテーマのこの曲に、より説得力を持たせるためだ。
そして、それが見事に成功しているのだから凄い。
でも、僕が気になったのは、佐野さんの歌い方。
ファルセットに近いウィスパー・ボイスなんだよね。
キーが高くて、高音が出ないからという理由でそうなったのではない気がする。
先のライヴ(Rockin’ Christmas 2024)では普通に歌ってたし。
どうして普通の歌い方をしないで、ウィスパー・ボイスにしたのか。
スピード感を増したサウンドにも関わらず、ヴォーカルは抑えた。そのスピードに抗うかのように。
その意図を想像すると、かなり気になる歌い方ではある。
「虹を追いかけて」。
ザラついたリズムにサイケなギターが絡むも、それでいてホーンやストリングスが穏やかに響き、感触としては優しい音色。
『Cafe Bohemia』に収録されてた原曲は、はて、どんなアレンジだったっけ?と、思い出すのにも一苦労するほど、特に佐野さんの代表曲というわけではない、地味な立ち位置だった。
それを今回わざわざ採り上げたのには何か大きな理由があるのか?と勘繰ってしまう。
もちろん、元々メロディには光るものがあったのは、今回のヴァージョンを聴いて、改めて感じるところだけど。
「冬の空」、そしてサビの「冬の天使(エンジェル)」と繰り返し歌われることでもわかる通り、冬の曲。
先の名盤『今、何処』に収録されてた「冬の雑踏」を思い出す。
あの曲も、こんなソウルフルな味わいのサウンドだった。
佐野さんの中での冬の音は、こんな感じなんだな。
表面はひんやりしているけれど、だからこそ芯の温かさに気付かされる、みたいな。
コヨーテ・バンドは、ギターを中心としたモダン・ビートだけでなく、こういった流麗でしなやかなサウンドも得意としている。
背伸びして、取り繕ったようなものは長続きしないし、すぐにメッキが剝がれる。
それよりも、今できることを地道にやっていく。
じっくりと、大地に根を張るような生き方をすることが大切なんだ。
佐野さんはささやくように歌っているけれど、実はファルセットも含め、何重にも重ねられたヴォーカル・ワークが凝っている。
ビートやコード感を変えることで、曲の持つ雰囲気がまるで違って聴こえる。
「欲望」も、そんな変化があった曲だ。
ここでは、エレクトロ、EDMといったモダン・ビートを採り入れた。
サウンドのキーを上げて、佐野さんは1オクターブ下げた歌い方をしてるという。
原曲は熱い歌唱で、ともすれば重たい印象だった曲が、天国のダンスホールで舞うかのように、ある意味軽やかさを伴っているようになった。
今の若い世代にも受け入れられるような解釈での演奏というのが、このアルバムの命題だが、いちばん現代音楽の感覚を採り入れているのはこの曲ではないかと思う。
何をすればいいのかわからない、何をしたいのかもわからない。教えてくれる人は誰もいない。
片っ端から思いつくものに欲望と名を付けるけれど、すべてが叶わないような気がしてならない。
混乱と失望で頭がおかしくなりそうで、誰かに助けを求めたい。
「欲望」が「夢」に変わる時、自分の心は安定感を得られるだろう。
けれど、原曲にあった「Dream」というフレーズが、今回は省かれた。
今は、夢見ることも出来ない世の中なのだろうか。
昨年のZepp Tourで一足先に聴いてはいたが、レコーディングされたものは、その時の感触とも違って聴こえる。
ライヴでの生演奏では熱が入りすぎたのかもしれないが、ここでの耳触りは、終始まろやかなものになっている。
人の心の欲望を表現するのでも、悪魔の叫びから天使のささやきへと、主体が変わったようだ。
欲望をさらけ出すことの罪悪感は感じられず、むしろそれは甘い快楽とさえ思える、価値観の逆転だ。
「インディビジュアリスト」から改題となった「自立主義者たち」。
「個人主義者」と解釈されることへの訂正の意味が込められてるという。
ひとりだけの世界ではなくて、ひとりひとりの世界。
独りでも熱い魂をもって自立し、強いものに抗い、戦い続けること。
そんな人たちが多くなれば、世の中の風向きは変わってくるのだと教えてくれる。
原曲はスカ・ビートが痛快で、踊りだしたくなると言うよりも、つい走りだしたくなってしまうほどのパッションを持ったものだった。
そのサウンドは、スタイル・カウンシル「Internationalists」の影響下にあって、スタカン好きの僕も、そんなところが大好きだった。
コヨーテ・バンドも今までのライヴでたびたび採り上げ、原曲になるべく忠実なアレンジで演奏してきた。
でも、原曲のアレンジの良さをいちばん感じるのは、感情を煽るホーンの音色だったんだよね。
しかし、ハートランドやホーボーキング・バンドと違って、コヨーテ・バンドには、ホーン奏者はいない。
ライヴでも、どことなく物足りない面があるのは僕も気になっていた。
どうしても、ここにホーンの音があれば!と思ってしまっていた。
よって、コヨーテ・バンドらしさを出すために、ホーンに頼らない、新しいアレンジにする必要性を感じたのではないか。
この新しいコヨーテ・ヴァージョンは、ポリスのようなギターのコード感で、空間が広がりを見せる、怪しいジャングル・ビートになった。
インパクトは全体的に控えめで、粘っこくまとわりついてくるサウンドだ。
早く踊らせてくれよというこちらの願いを焦らすかのようでもあり、サビでバッと弾けるか!?と思った途端に、また肩透かしを食らうような感じ。
これはこれでいい感じなんだけど、強力なスカのリズムで押し通した旧アレンジが僕は好きすぎるので、まだちょっと違和感があるのは否めないかな。
「君をさがしている(朝が来るまで)」。
今回のアルバムで再定義したと言うよりも、今から10年前、35周年ライヴでのコヨーテ・アレンジそのままだということが、DVDを観ればわかる。
原曲のキラキラした青春モッズ・サウンド味はかなり薄れ、力強くブルージーでワイルドな演奏。
主人公を演じる役者が変わった感だ。
ポップなビート・ロックだけでなく、こんなオルタナティブな演奏もコヨーテ・バンドは出来る。
夜通し探し求める君とはどんな存在なのか。
探すということは、行動を起こすということ。
どんなリスクがあろうと、あえて踏み出す勇気だ。
10年前、この曲をこのアレンジに仕立てたのが、今回のプロジェクトの起点になっているのではないかと思う。
つまりは、HAYABUSA JETは、 10年前から既に始まってたんだ。
元春クラシックスをコヨーテ・バンドで再定義したというアルバムだけど、原曲と比べて、大きな変化がないように思われる曲もある。
「ジュジュ」。
かなりモータウン・ビートが強調されたとはいえ、既に聴き慣れた感がある。
「約束の橋」。
よりダイナミックな演奏になってるなとは思うものの、いつものアレンジと言われればそれまでだ。
この2曲は、近年のライヴでもよく採り上げられてた定番曲。
歌詞の変化もほとんどない。
佐野さんとコヨーテ・バンドのライヴに通ってるファンからすれば、お馴染みのサウンドに映るはずだ。
つまり、これらは、このアルバムのために再定義したと言うよりも、近年、コヨーテ・バンドで演奏してきたグルーヴを記録しておきたかった、ということだけなのかもしれない。
でも、大きな変化がない曲があることで、アルバムに安心感のようなものが宿っている気がする。
再定義とは何かがわかった
ベスト盤を聴いてるような、新曲ばかりのNEWアルバムを聴いてるような、その両方がない交ぜになった気がする、新感覚のアルバムだった。
単純なセルフ・カヴァー集とは、やはりどこか違う。
リリースに際し、様々なメディアで、佐野さんにインタビューが行われ、セルフ・カヴァーと再定義の違いを訊かれた佐野さんは、こう答えている。
「セルフ・カヴァーは再解釈。今回のアルバムは再定義」
解釈となれば、いろんな解釈が出来る。
気分を変えて、こんなアレンジ、こんな解釈はどう?と、ある意味、軽さを伴って何度も取り組めるのがセルフ・カヴァー。
しかし、再定義するとは、あらためて定めるということである。
これが答えだと、断言する覚悟や責任がある。
作詞作曲をしたのが80年代、90年代ではなくて、今の佐野元春が新しく作った曲だとしたらという仮定の基に、コヨーテ・バンドと、今ならこう料理すると答えを出した。
そして、45年あまりの歴史の中で、ファンそれぞれに様々な解釈でイメージが分散されてたものを、これが今の形であると、再び佐野さんのコントロールできる状態に正したものだ。
つまりコレは、佐野元春の新たな教科書と言っていいアルバムだ。
だけど、こうして新しいヴァージョンが出来上がったということは、コヨーテ・バンドのライヴではもう、昔のアレンジで演奏することはほぼないだろう、ということを意味するわけで。
そう考えると、寂しい気がしてくる。
昔のアレンジに思い入れが強い、昔からのファンほど、そういう気持ちを抱くのは自然なことだろう。
今回のアルバムは素晴らしいアイデアで、素晴らしいアルバムと言えるのだけれど、そういった功罪も含まれているのは確かだ。
音楽評論家のスージー鈴木さんが、セルフ・カヴァーは苦手、と言ってたけれど、僕も同じ。
9割方はオリジナルの方が良かったなあと感じてしまうからだ。
そのスージーさんが「つまらない大人にはなりたくない」を、「ノスタルジーではなく、現代に響く音にもなっている」と言っている。
僕には現代にも響く音なのかどうかは、正直わからない。
だって、現代の流行りの音楽なんて、ほとんど聴いてないんだもん。
最新のチャートやランキングなんて興味が湧かなくなり、昔の音楽でも、最近出会ったものは、僕にとっては今の音楽として響いているのだ。
そんな僕には、現代の基準がわからない。
歌詞の内容が現代に響くかどうかなら、それなりにわかるけどね。
でも、音楽理論を勉強したわけでもないし、サウンドの流行りがどうなってるのかは、やっぱりわからないな、というのが本音だ。
スージーさんが「現代に響く音にもなっている」と言い切っているのはさすが音楽評論家。
現代の音楽を、好きも嫌いも関係なく勉強しているからこそ言える言葉だと思う。
毎日、Xやブログで音楽レビューを書いている僕だけど、昔の曲を中心に、好きな音楽だけを聴いている僕の言葉は単なる素人の感想にすぎないことを実感する。
しかし、今回の再定義。
そんな僕でも、「オリジナルの方が良かったなあ」と思う曲は少なかった。
原曲も再定義曲も、どちらも素晴らしいと、1粒で2度楽しめる構造になった。
さすが佐野元春。
さすがコヨーテ・バンド。
僕は、歳と共に、最近流行りの音楽にはなかなか付いていけなくなってきたので、あえて「古い」ロックが好きだと公言するようにしてきた。
でも、佐野元春『HAYABUSA JET I』を聴いて、自信を持って言うことが出来るようになった。
「最新型のロックが好きだ」と。
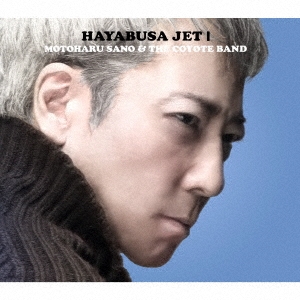
当ブログ管理人・カフェブリュは、X (Twitter)にて、毎日発信を行っています。
サザンオールスターズ、佐野元春、ビートルズを三本柱に、60’s~90’s ロック&ポップスの話題。
購入したCD・レコード紹介、 ロック名盤レビューなどをポストしています。
よろしかったらこちらもチェックしてみてください。


コメント