
大好きなアーティストのアルバムをランク付けするシリーズ企画。
今回は、エリック・クラプトン。
好きなアーティストのアルバムをランク付けするのって、非常に難しい。楽しいけど。
その日の気分によっても違ってくると思うし、はっきり優劣があるものもあるけれど、そもそも好きなアーティストの作品なんだから、どれも好きで、順位なんて紙一重のものが多いでしょう。
それでもやっぱり、ランク付けしてみたくなります。楽しいから。
好きなアルバムの定義ってなんだろう?と思います。
大好きな曲が入ってる、全体の流れや空気感が好き、ジャケットが好き、リアルの生活における思い出とリンクしている...など、いろいろあると思うんですが、僕が重要視するのは「ワクワク度」ですね。
そのアルバムを聴いている時はもちろんなのですが、「それを聴いてない時でも、そのアルバムの事を考えると、ワクワクしてしまう」ものが自分にとって上位なんだと思うんです。
個人的に思い入れの深い順ではありますが、それこそがみなさんへのおすすめ順。
好きなものをおすすめしたいです!
コメントの次には、各アルバムの中で1番好きな曲を、No.1 Songとして表記しました。
ジャケット写真をクリックするとTOWER RECORDSへのリンクになってます。
第1位~第10位

第1位 『Layla And Other Assorted Love Songs』
Derek & The Dominos
とにかくアルバム全編を通して感じられる圧倒的な情熱がハンパないです。
カヴァー曲もありますが、クラプトンのソングライティング力が上がり、ヴォーカル、演奏ともにエモーショナルな表現が出来るようになったのが大きい。
コンビを組んだデュアン・オールマンの存在も大きく、スライド・ギターが心地良く炸裂してます。
親友であるジョージ・ハリスンの妻、パティ・ボイドという一人の女性への思いがこもった、というか、その熱き告白だけで作られているという、ある意味特異なアルバムでもあります。
なんと言っても「Layla」での胸をかきむしられる程の魂の叫び。イントロのギターからして燃えますが、後半の美しすぎるピアノ・インストも素晴らしい。
軽快に高みを目指す「I Looked Away」から、うだるような熱さの「Bell Bottom Blues」の落差にやられます。
「Keep On Going」は涼し気なギター・バトルの嵐。
「Nobody Knows You When You’re Down And Out」「Key To The Highway」「Have You Ever Loved A Woman」などのブルース曲では、野太く艶のあるギターの音色が心を震わせます。
「Tell The Truth」はシングル・ヴァージョンよりテンポを落として、ブルース色を濃く。
「Layla」に引けを取らない上に、さらにスピードをアップさせた「Why Does Love Got To Be So Sad?」で興奮は最高潮。
ジミ・ヘンドリックス版よりも気怠いブルースになっていて、熱量で溶けそうなほどのギター「Little Wing」で昇天。
ロックとブルースが見事に調和していて、コレを好きになれないなら、エリック・クラプトンというアーティストは好きになれるはずがないと言っても過言ではないでしょう。
僕は長い間ブルースが苦手だったのですが、このアルバムにブルースとはどういうものか教えてもらい、好きになれました。
とにかく熱く、興奮の1時間20分。
No.1 Song 「Layla」

第2位 『There’s One In Every Crowd』
ジャケットから、なんか地味な空気が漂ってきていて、長らく聴く気が起きなかったアルバムでしたが、どうしてもっと早く聴かなかったんだと後悔したほどの素晴らしさ。
前作『461 Ocean Boulevard』からのレイドバック・サウンドをより進めました。
力の入ったロック・ナンバーはなく、稲妻のように弾きまくるクラプトンはいません。
リラックス・ムードで平和な空気が続くので、熱くはなれないかなと思ってたら、終盤の流れがドラマチックで、良いものを聴いたなあという満足感でいっぱいになるのです。
レゲエからの進化形、ほのぼのとしたレイドバック「Swing Low Sweet Chariot」。
リラックスした中でもブルースの魂は忘れない「The Sky Is Crying」。
「Singin’ The Blues」はファンキーな女性コーラスとギター・ソロが印象的。
「Better Make It Through Today」は寂しくて切なくてやるせなくて、憂いのあるメロディがたまらない。
「Pretty Blue Eyes」は突然現れる美しいコーラスの波にハッとさせられます。
「High」は終盤のギターが聴きもの。
「Opposites」は「Layla」後半のインストを思い出させる昇華具合が美しく、穏やかに高揚していく感じが最高です。
原題がピンと来ないものなので、『安息の地を求めて』という邦題の素晴らしさが沁みます。
その名の通り、安息の地へクラプトンが誘ってくれるアルバムです。
『Layla』とは対極にあるような世界観で、クラプトンの振り幅の大きさにも魅力を感じますね。
No.1 Song 「Better Make It Through Today」

第3位 『From The Cradle』
前作『Unplugged』が大ヒットし、好きなことをやるのは今しかないとばかりに作ったのが、ブルースのカヴァー・アルバム。
『ゆりかごから』という意味で、生まれた時からブルースが嗜好であると宣言。
クラプトン自身、ずっとこういうのがやりたかったんだとばかりに気合いが入ってます。
とにかく、ギターが吠えています。
ソロ、ストローク、フレーズがどれも痺れます。
突出した曲があるわけではないけれど、アルバム通してレベルが高いです。
いきなり「Blues Before Sunrise」での爆裂ギターと力の入ったヴォーカルが、このアルバムの行く末を示しています。
「Third Degree」は泥臭いですが、光沢のあるピアノと艶のあるギターに深みがあります。
「Five Long Years」はギターの歪み抜群で、稲妻のような鋭い速弾きに痺れるスロー・ブルース。
「I’m Tore Down」や「Goin’ Away Baby」のような軽快なリズムのブギも。
「Blues Leave Me Alone」は、これぞブルース!というお手本のようなノリと演奏。
「Motherless Child」はシャラシャラと鳴るアコギ(マンドリン?)が涼し気です。
「It Hurts Me Too」はズズズズと唸る低音からキュイ~ンと響き渡る高音まで、ギターの高低差が魅力の狂気のブギ。
「Someday After A While」は華々しいサウンドの中で色気のあるギターを弾きまくるクラプトン。
「Groaning The Blues」は骨太に弾き倒す姿は重厚感たっぷりで、ラストを締めくくるに相応しい曲。
僕はそれまでブルースは苦手だと思っていたのですが、クラプトンのこのアルバムは、すんなり受け入れられたんですよね。
古典のブルースをエレクトリック・ブルースとして特化し、ロックとの調和を図ったのが功を奏したのでしょう。
クラプトンの趣味全開で作ったのに、これまた大ヒットという結果を残しました。
No.1 Song 「Five Long Years」

第4位 『Live In San Diego』
05年にクリームの再結成があり、次はデレク&ザ・ドミノスの再現とばかりに、組み立てられた07年のライヴ。
オールマン・ブラザーズのメンバーの甥でもあり、その名をドミノスから採られたというデレク・トラックスが参加しているのが大きいです。
デレクのスライド・ギターが全編に響き渡り、ドミノスが全盛期にデュアン・オールマンを伴ってライヴを行なってたら、こうだったんじゃないかという夢を現実ものにしてくれたかのようです。
「Got To Get Better In A Little While」から「Little Wing」の流れは特に胸アツ。
また、前年に共演アルバムを作ったJ.J.ケイルを招いてのコーナーがあり、そこからの渋い楽曲から、「After Midnight」を通って「Cocaine」に至る流れも素晴らしい。
後半も、スライド・ギタリストがいることでひときわ光る「Motherless Children」。
「Little Queen Of Spades」「Further On Up The Road」「Crossroads」といったブルース。
そして「Wonderful Tonight」といったクラプトンの代表曲がズラリと並んだうえでのハイライトはやはり「Layla」。このバンド編成で魅力を最大限に発揮させています。
憧れの先輩、そして縁ある後輩に負けじとクラプトンが張り切るのも頼もしいし微笑ましい。
しかし、これだけギタリストがいると、どの音が誰のプレイだか分かりづらいのが悩ましいんですけどね。

第5位 『Goodbye』
Cream
ライヴ録音とスタジオ録音で構成されるという、前作『Wheels Of Fire』のコンパクト版といった趣。
解散発表後の作品なので、急ごしらえというか、ムリヤリ寄せ集めた感があります。
しかし!
内容的には、クリームの魅力を伝えるに充分な、最高傑作と言ってもいい出来なのです。
ライヴ曲では、1曲目「I’m So Glad」から、前作の「Crossroads」に匹敵する3人の炎のバトルに興奮します。このスピード感はたまりません。
スタジオ曲もクラプトン、ブルース、ベイカーそれぞれの曲が素晴らしいんです。
代表曲ともなった「Badge」は、ジョージ・ハリスンの色が濃く、「While My Guitar Gentry Weeps」の兄弟曲のような雰囲気の泣きメロが素晴らしい。
ブルースの「Doing That Scrapyard Thing」はコミカルに跳ねています。
ベイカーの「What A Bringdown」は切迫感あるサウンドで、メロディも引き締まっていて、ベイカーってこんなに良い曲書けるんだ?と驚きました。
なんとかアルバムの体裁を取るのがこれで限界だったのでしょうが、収録時間の短さが、物足りないとはまったく思いません。
クリームというグループ、メンバー各人の才能がギュッと凝縮されたアルバムだと思います。
これで最後とは惜しい。
もし、この後も続いていたら...と妄想しますが、ここらで華々しく散るしかなかったのもクリームの定めだったのでしょう。
No.1 Song 「Badge」

第6位 『The Definitive 24 Nights』
ロイヤル・アルバート・ホールで24日間行われたライヴは、4ピース・バンド、ブルース・バンド、9人編成バンド、オーケストラをバックに従えたバンドと、異なる志向で行われ、それらの演奏からピックアップしたものを2枚組にまとめた『24 Nights』というライヴ盤が91年にリリースされていました。
しかし、長らくCDも在庫切れ、サブスクでも聴けない状態が続いていたので、どうしてなんだろうと思っていたら、23年にボリューム・アップして新装発売されました。
4ピースと9ピースの演奏を【Rock】とし、他の編成は【Blues】【Orchestral】として、その3種類をそれぞれフル・ライヴに近い2枚組としてまとめ上げました。
3種類、バラでも発売になりましたが、すべてをまとめたBOXが『The Definitive 24 Nights』という形で配信にもなってますので、とりあえず、それを挙げることにします。
90年と91年のライヴなので、『Unplugged』の大ヒットの前夜ということになるのですが、それまでのクラプトンのライヴの形を、様々な形態で特化してみせた、面白い試み。
4ピースはクリームのように引き締まった感じだし、9人編成は近作中心に華やかさを増してるし、ブルースはクラプトンの趣味全開だし、オーケストラはゴージャスなサウンドながらも落ち着きがあるし。
クラプトンの歴史をブロック分けして、様々な角度で振り返れるのが魅力。
【Rock】、【Blues】、【Orchestral】、どれも甲乙付け難く、聴き応え充分の満足感でいっぱい。
どんな編成でもクラプトンのギターが堪能できるのが凄いところです。

第7位 『Live From Madison Square Garden』
Eric Clapton & Steve Winwood
クリームの再結成を経て、ドミノス再現ライヴをやった後は、ブラインド・フェイスだってやりたいじゃないか。クラプトンは思ったのかもしれません。
08年、今度はスティーヴ・ウィンウッドとの共演ライヴです。
僕はそれまでブラインド・フェイスがそれほど好きではなかったから、ウィンウッドとのこのライヴ盤も、初めは軽く見ていました。
しかし、ここで初めてブラインド・フェイスの良さに気付いたというか。
そして、ブラインド・フェイスのレパートリーだけでは少ないということで、その他に採り上げた曲も素晴らしかったのです。
「Hard To Cry Today」でビックリしたのは、ウィンウッドもギターを弾いてること。クラプトンとのツイン・ギター・バトルが熱いのです。
そして「Presence Of The Lord」での心のこもったウィンウッドのヴォーカルとクラプトンのギター。
ブラインド・フェイスのライヴはこんな感じだったのかと感動します。
クラプトンの持ち曲としては「Forever Man」「Double Trouble」「Little Wing」辺りを採り上げてくれたのが嬉しい。
その他、ウィンウッドの持ち曲以外にも、ブルースやソウルのカヴァー曲を採り上げて、バラエティ豊かなセットリストにしています。
ウィンウッドに遠慮することなく弾きまくるクラプトンのギターの音色が、ツヤ、歪み具合、とにかく良いんです。僕好みでした。
ウィンウッドにほとんど思い入れがなかった僕でもこれだけ興奮するなら、ウィンウッド好きにはたまらないのではないかと思います。

第8位 『Back Home』
成功と挫折を繰り返し、大ヒットの連発でキャリアを盤石なものにした後に向かえた21世紀。
しばらくすると、クラプトンは今までの自らを振り返る気分になります。
クリームの再結成があり、忘れ物を取り戻した感覚になったところで、安定した心持ちの中で制作したアルバムは、【家へ帰ろう】というものでした。
ギター・プレイの良さだけでなく、曲自体のメロディの良さも際立った勝負が出来るようになったクラプトン。
前作『Reptile』までの穏やかな空気感を保ちつつも、静かな力強さを秘めた温かなアルバムとなりました。
ユラユラとリラックス・ムードの「Say What You Will」。
力強いホーンやコーラスにギターが絡む「I’m Going Left」。
優しさを畳み掛けるような「Love Don’t Love Nobody」は温かなバラード。
派手なレゲエの「Revolution」。
最大の聴きものは、亡き親友・ジョージ・ハリスンの「Love Comes To Everyone」で、ジョージのオリジナル版に忠実ながらも、当時は少ししか弾けなかったギターを、こんな風に弾きたかったんだとリベンジしたようなところがあります。
「Lost And Found」はギターの嵐吹き荒れるブルース。
「Piece Of My Heart」は枯れた音色に濡れたメロディの妙。
「One Track Mind」はアコースティックからエレキへのギター・ソロが静かな闘志を燃やすかのよう。
ラストへ向かっていく「Ran Home To Me」も聴き応え充分。
緩急自在に使い分け、渋み、苦みも含めたギターが随所で効果的。
心温まる、安寧の時間をクラプトンと共に味わいたいです。
No.1 Song 「Love Comes To Everyone」

第9位 『Journeyman』
サウンドに深みが増し、バラエティ豊かな曲が並ぶ。
混迷の80年代を立て直した、それまでの集大成的な、クラプトンのいいとこ取りといったアルバムです。
カヴァー曲や提供曲が多いものの、クラプトンが曲作りに関わった2曲が「Bad Love」と「Old Love」という神曲で、そのソングライティングの才能を再認識させると共に、どちらもラヴ・ソングというところが胸を熱くさせます。
徐々にエンジン温めていく感じの「Pretending」。
「Bad Love」は、新しい「Layla」とでも言えるほど、熱い魂が蘇ってます。
ブルースにゴスペルを塗したような「Running On Faith」。
「Hard Times」はブルースとジャズの融合。
古いロックンロールの「Hound Dog」。
ジョージ・ハリスンと共演した「Run So Far」は、リゾート感満載で心地良い風に吹かれます。
「Old Love」の虚ろなメロディでのギター・プレイの応酬は、クラプトンの才能が枯れてないことの証左。
最後は「Before You Accuse Me」という力強いブルースで締め。
80年代の最先端のサウンドを追うのではなく、あくまでクラプトンならではの音楽を見つめ直した復活のアルバム。
好きなブルースを好きなようにやったりしながらも、お洒落な空間作りにも挑戦し始めていて、90年代における大ブレイクの兆しがあるのも興味深いです。
No.1 Song 「Bad Love」

第10位 『Reptile』
「Tears In Heaven」や「Change The World」のような優しい世界が広がっています。
それというのも、幼少期のクラプトンに音楽の素晴らしさを教えてくれた、亡き叔父さんに捧げたアルバムであるからです。
お洒落な感覚を引き継ぎつつ、ギターの音色はよりまろやかになっていて。
温かみの中に何故か哀しみが見え隠れするような味わいのアルバムです。
お洒落なフュージョン・インスト「Reptile」で幕開け。
「Travelin’ Light」はささやくようなヴォーカルに、逆に闘志を感じます。
「Believe In Life」は穏やかな軽快さがあって、甘みと安心感を同時に味わえます。
「Broken Down」は憂いを帯びたR&Bソウル。
とびきりノリのいいのが「I Ain’t Gonna Stand For It」で、キャッチーなメロディにギターが絡んでいくと、どんどん勇気が漲ります。
ドゥーワップを採り入れたブラック・ミュージックみたいな「Don’t Let Me Be Lonely Tonight」は優しくて温かいのに、心の中の辛さが伝わってきて涙。
「Modern Girl」は素朴で控えめながら、じっくりと心に入りこんできます。
祈りを捧げるようなギター・インスト「Son & Sylvia」は美しい思い出を懐かしむような光景。
もちろんブルースやゴスペルも適度に配置され、クラプトンのキャリアにおける幅の広さを垣間見ます。
ただ、熱く歌ってギター弾きまくる姿はほとんど見せず、とことん優しいクラプトンに徹しています。
No.1 Song 「Don’t Let Me Be Lonely Tonight」
第11位~第20位

第11位 『Riding With The King』
B.B.King & Eric Clapton
ブルース大好きクラプトンにとっては、『From The Cradle』の夢よもう一度という思いはありましたが、まったく同じことはできません。
そこで、憧れのB.B.キングとがっぷり四つに組んでのブルース・アルバムの制作に撮りかかりました。
御大に臆することなく、共演できる嬉しさが爆発し、張り切るクラプトン。
キング、クラプトン、どちらかが前面に出るわけではなく、あくまで対等な関係で作られていて、それでいてお互いのリスペクトの気持ちが滲み出ているのが、なんとも良いんです。
いきなりのデュエットに嬉しくなる「Riding With The King」。
2人が交互にソロを弾く「Ten Long Years」。
クラプトンのお馴染みのレパートリーである「Key To The Highway」や「Worried Life Blues」はアコースティック・アレンジで。
「Marry You」は、しっとりしたメロディに乾いたギターが魅力。
「Help The Poor」は踊れるブルースといったところ。
ゴージャスでノリがいい「Days Of Old」。
クラプトンの泣きのプレイが光る「When My Heart Beats Like A Hammer」。
深みのあるジャズ・スタンダード「Come Rain Or Come Shine」。
キングとクラプトンがヴォーカルを分け合ったりするのもいいし、骨太の2人のギターが絡み合うのも素晴らしい。
お互いの魅力を引き出し、コラボ作品の見本とも言えるアルバムです。
No.1 Song 「When My Heart Beats Like A Hammer」

第12位 『I Still Do』
腕を組んだクラプトンの肖像画がなんとも渋い。
オリジナル曲、カヴァー曲とあるけれど、トータル的にはブルース色が濃いと感じます。
こういったアルバム作りはいつものクラプトン。
突出した曲があるわけでもないし、何がどうってわけじゃないけど、なんだか惹かれるアルバムなのです。
「Alabama Woman Blues」は唸るギターのスロー・ブルース。
涼し気なヴォーカルとギターの「I Will Be There」。
ブルージーな渋みがたまらない「Spiral」。
アコースティックな肌触りの「Catch The Blues」はピリリと辛い。
「Cypress Grove」は重たく暑苦しいブルース。
「Little Man, You’ve Had A Busy Day」は温かなお風呂でのんびりしている感じ。
「Crossroads」を思い出させる「Stones In My Passway」。
様々なブルースを並べたコース料理のようなアルバム。
俺、今でもこんなことやってるよと、あらためてファンに宣言しているかのようです。
そして、ファンもそんなクラプトンを喜んで受け入れるのです。
No.1 Song 「Spiral」

第13位 『John Mayall Blues Breakers With Eric Clapton』
John Mayall Blues Breakers With Eric Clapton
クラプトンにとってのキーワード、ヤードバーズが「原点」なら、ブルースブレイカーズは「開花」です。
あくまでジョン・メイオール&ブルースブレイカーズの作品だし、クラプトンはリーダーじゃないし、いちギタリストとしての客演みたいなものだと思ってたので、こんなに良いアルバムだったとは驚きました。
ブルース・ナンバーで弾きまくってるクラプトンが躍動しています。
「All Your Love」はいきなり色っぽいブルース。クラプトンのソロに鮮やかな色が見えてブギになります。
「Hideaway」はノリもいいし、野太い音色のギター・インスト。クラプトンが弾きまくる姿に、インストが苦手な僕でも興奮します。
「Double Crossing Time」はピアノも印象的なスロー・ブルースで、そこに甲高いギター・ソロが流暢に鳴り響きます。
「What’d I Say」はハモンド・オルガンからのドラム・ソロの展開に、ビートルズ「Day Tripper」のフレーズも飛び出す仕掛け。
ブルースと言うよりロックンロールなのが「Key To Love」で、稲妻ギター・ソロが唸ります。
ハーモニカが先導する「Parchman Farm」の突っ走るリズムもたまらない。
「Have You Heard」はホーンとギター・ソロが一緒に熱を帯びて盛り上がっていく様が圧巻。
スタンダード・ブルース「Ramblin’ On My Mind」「Steppin’ Out」はブルースブレイカーズの集大成的なサウンド。
ジョン・メイオールの甲高いヴォーカルは、ハード・ロック向きかも。
アップ・テンポ・ナンバーもスロー・ナンバーもあって、ブリティッシュ・ブルース・ロックの古典。
師匠・ジョン・メイオールがクラプトンを温かい眼差しで見守ってるのがわかります。
そんな環境をお膳立てされ、水を得た魚のように、アルバム全編に渡って自由に弾きまくるクラプトンが勇ましい。
クラプトンはこれで神になった、と感じる瞬間です。
No.1 Song 「Hideaway」

第14位 『Blind Faith』
Blind Faith
以前は「Presence Of The Lord」1曲しか良い曲ないじゃん、なんて思ってました。
しかも、スティーヴ・ウィンウッドが主役で、クラプトンはあんまり目立ってない、とも。
ウィンウッドが好きかどうかで、このアルバムの評価が分かれるんじゃないか。
クリームに似ているけれど、ウィンウッド色で、よりソウルフル。
僕はウィンウッドにあまり思い入れがなかったので、スーパーグループと言われてる割にはちょっと期待外れというか、以前は軽視してました。
それが最近聴き直したら、結構クラプトンもギター弾いてることに気付いたし、このバンドでしか出せない味わいが大好きになりました。
「Hard To Cry Today」における、渋いギター・バトル。
風で波がざわめくような「Can’t Find My Way Home」。
そしてなんと言っても「Presence Of The Lord」。悟りきったようなメロディから、一転してクラプトンのギター・ソロが炸裂する間奏。
混沌とした「Do What You Like」。
どの曲も渋いですね。
スーパーグループと言われた割には、派手さはなくて、静かな佇まいが魅力です。
No.1 Song 「Presence Of The Lord」

第15位 『Happy Xmas』
タイトルが示す通り、クリスマス・アルバムなんですが、あくまでブルースに仕立て上げています。
楽しく甘いムードはどこへやら、むしろ、これのどこがクリスマスなんだ?という気さえします。
そんなところがクラプトンらしいですね。
「Christmas Tears」は太いサウンドのギターでソロを弾きまくるクラプトンに、プレゼントを配るサンタを思わせます。
「Lonesome Christmas」はノリ良いブルース・ブギ。
「Merry Christmas Baby」も思いっきりブルース。
ここまでクリスマスをブルースで表現できるアーティストは他にいません。
このようなブルースの心は、パーティーのような華やかさよりも、ひとり孤独をふと感じるクリスマスに似合います。
No.1 Song 「Christmas Tears」
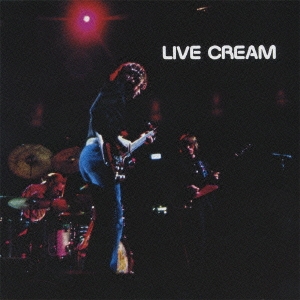
第16位 『Live Cream』
Cream
解散後にリリースされたライヴ盤。
採り上げられた曲はキャッチーとは言い難く地味で、昔はあまり印象に残りませんでした。
それでも、3人の緊張感ある演奏に聴き入っているうちに、好きになりました。
「Sweet Wine」など、別の曲になった?とも思えるくらい長尺の展開になっているけど飽きさせない。
クラプトンが吠える、ブルースが唸る、ベイカーが暴れる。
クリームの魅力が存分に発揮されるのはやはりライヴなんだなと思わせられるのです。

第17位 『Eric Clapton』
クリームの後、デラニー&ボニーらとも活動を共にする中で、ソウルやゴスペル、サザン・ロックをうまく吸収し、それでいてギターも弾きまくるという自分のロックに落としこんだ1stソロ・アルバム。
ソングライターとしてはキャッチーなメロディを生み出すようになり、シンガーとしても自立したのが嬉しい。
デラニー&ボニーのバンド・メンバーがバックを務め、デレク&ザ・ドミノスへと発展していく過程が楽しめます。
スワンプ・ロックの「Slunky」。
ウキウキするスピード感で躍動する「After Midnight」。
「Easy Now」は後のアンプラグドなお洒落路線の萌芽を見るような新機軸。
華々しいエネルギーに満ちた「Blues Power」。
流麗なメロディを疾走感溢れるサウンドで畳み掛ける「Let It Rain」。
クリーム時代と比べたら、クラプトンの世界観が一気に広がったのがわかるアルバムです。
気負ったところがないのもいい感じなんですよね。
No.1 Song 「Let It Rain」
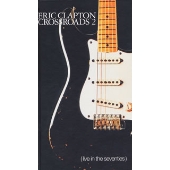
第18位 『Crossroads 2』
まず、88年にベスト盤とも言えるBOX『Crossroads』が出ました。
それが好評だったことを受け、今度はライヴ・テイクばかりを集めた続編的BOXとして96年にリリースされたのがこの作品。
70年代のライヴ音源がびっしり詰まっています。
Disc 1は、ちょっとトロいかなという印象。
Disc 2で一気に熱くなります。
Disc 3では弾きまくったり、まったりしたりと様々な顔を見せます。
Disc 4になると、安定感抜群。
4枚組でお腹いっぱいになるライヴ集です。
30代のクラプトンは、ある意味全盛期と言えるけれど、ドラッグやアルコールに溺れた時期でもあり、クラプトン自身の記憶に残ってないくらいの、微妙なプレイの幅があるのが逆に魅力。
若い頃のクラプトンのライヴ、観てみたかったなあと思ってしまうのです。

第19位 『Just One Night』
ロック、ブルース、レイドバックと、様々な魅力を持つクラプトン。
ジャケットの姿もカッコいいです。
ドラッグに溺れた日々からも抜け出し、自分のサウンドを確立した70年代クラプトンの集大成的なライヴの記録。
とはいえ、今度はアルコールに溺れていた時期なのですが(笑)、ここでは、その影響は見受けられないプレイを見せています。
武道館での録音というのも、日本人としては嬉しいポイントですよね。
「Lay Down Sally」「Wonderful Tonight」「After Midnight」「Cocaine」など、ソロになってからの代表曲が網羅されているので、初心者でも聴きやすい。
スタジオ・テイクよりもギター弾きまくってる曲も多く、「Double Trouble」とかマジ泣ける。
でも、セットリスト的には豪華でも、全体的には渋い演奏のライヴかもしれません。

第20位 『Live Cream Volume II』
Cream
前ライヴ盤に比べたら、「White Room」や「Sunshine Of Your Love」などのヒット曲も収録されていて華やかさが増しました。
しかし、期待値も上がりすぎたためか、実際に聴いてみると、期待を上回るほどのものではなかったかなとも思っちゃう。
でも、1曲目「Deserted Cities Of The Heart」とラストの「Steppin’ Out」は特に良くて、長いソロも含めて激しい演奏。
クラプトンのギターが野太い音でズルズル言ってるのも快感ポイントです。
第21位~第30位

第21位 『Rainbow Concert +8』
ドラッグでボロボロの状態にあったクラプトンを、なんとか表舞台に引き戻そうと、ピート・タウンゼントやロニー・ウッド、スティーヴ・ウィンウッドらがバックアップしたライヴ盤。
元々は73年に全6曲でリリースされていましたが、95年に曲数が増えて(しかも良い曲ばかり)、グッと聴き応えが増しました。
中途半端だったアルバムが豪華なものに生まれ変わって好印象です。
プレイに精彩を欠き、まだまだ本調子ではないと言われていたクラプトンですが、このメンバーでのお膳立てのお蔭で、あまり気になりません。
しかも、いきなり「Layla」から始まり、「Badge」「Roll It Over」「Little Wing」「Bell Bottom Blues」「Presence Of The Lord」と、泣きメロの曲多し。
大人数のバンドなので、演奏はもったりしてるし、著名なギタリストがたくさんいて、肝心のクラプトンのギターの音がどれなのかわからないといったマイナス要素もあるのですが。
今のところ、コレはクラプトンの黒歴史だからか、権利の関係からか、サブスクには無くて、なんだか軽視されてるのが逆に愛おしくなるアルバム。
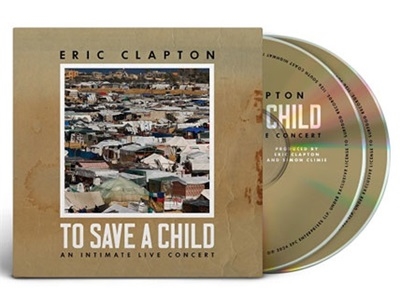
第22位 『To Save A Child』
23年に行われた、小規模な会場でのチャリティー・ライヴの記録。
近年のクラプトンのライヴを凝縮したようなセットリストになっていて、コンパクトでありながらも充実した内容。
物悲しいインスト「Voice Of A Child」で始まります。
前半は、かつての『Unplugged』的な雰囲気でライヴが進むのですが、「Layla」は『Unplugged』でのヴァージョンよりも好き。
アコースティック・ライヴになるのかと思いきや、「Key To The Highway」からエレクトリックになり、「Hoochie Coochie Man」ともども、徐々に力が入っていきます。
「River Of Tears」で静かに盛り上がる様は、子供たちに祈りを捧げるような神聖さ。
「Got To Get Better In A Little While」はブルージーでスリリングなロックの魂が変わらないところを見せつけます。
エレクトリック・ブルースの「The Sky Is Crying」はクラプトンの真骨頂。
ライヴの締めは、ジョージ・ハリスンの息子・ダニーを迎えて「Give Me Love」。
最後には、1曲目のインストにヴォーカルを付けた「Prayer Of A Child」のスタジオ録音をおまけに収録。
チャリティーを名目に、フットワークの軽さでサッとこなした感じのライヴの雰囲気がいいです。
深刻な問題を抱えている人たちを救済するといっても、重たすぎるライヴにならないように、コンパクトにまとめたのが功を奏しています。

第23位 『Nothing But The Blues』
94年の『From The Cradle』を伴ったツアーの音源が、22年になって発掘、リリースされました。
当然、『From The Cradle』収録曲を中心に、さらに「Crossroads」「Have You Ever Loved A Woman」などのブルースの古典ばかりを取り揃えました。
ブルース好き、『From The Cradle』好きにはたまらないライヴ盤となってます。
好きなことやってるクラプトン、かなり力入ってます。
ノリ良いブルースもあれば、粘っこいブルースもあり。
クラプトンの気合いの熱量、ホントにブルース好きなんだなというのが伝わってきます。
「It Hurts Me Too」なんて、どうすればライヴでこんな太いギターの音が出せるのか、感動すら憶えます。
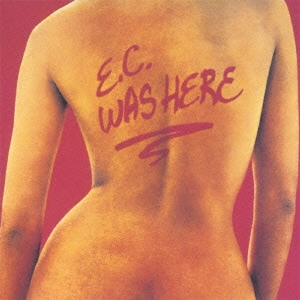
第24位 『E.C. Was Here』
オリジナル・アルバムではレイドバック・サウンドを確立させていた頃なんですが、ここでのライヴはブルースを弾きまくる元来の姿をアピール。
ブラインド・フェイスの「Presence Of The Lord」と「Can’t Find My Way Home」の2曲以外は、ブルースで固めました。
全6曲ということで、以前は、曲数も少ないし、地味なセットリストだなと思ってたけど、いま見ると、割とクラプトン王道のセットリストだと思えます。
レイドバックだけじゃなくて、ブルース好きのクラプトンを忘れないでねと制作したのは、レコード会社の思惑かもしれません。

第25位 『Another Ticket』
レイドバックにハマっていたクラプトンが、それを基調としながらも、再びブルースやロックに回帰し始めていきます。
それ故、割とバラエティに富んでる気がします。
弾きまくるギターを楽しめる曲もあり、捨て置けないのです。
「I Can’t Stand It」はキャッチーなメロディの上にキレがあり、熱いグルーヴが戻ってきたかのよう。
「Catch Me If You Can」はスティーヴィー・ワンダー的なファンキー・サウンド。
「Rita Mae」のスリル溢れた性急さにもゾクゾク。
いかんせん、ジャケットのイメージが地味さを助長していて、忘れられがちな作品なのですが、アルバムとしてはなかなか味があって好きなのです。
No.1 Song 「I Can’t Stand It」

第26位 『461 Ocean Boulevard』
ドラッグで身を滅ぼしかけたクラプトンが大復活を成し遂げたのは、レイドバックという新ジャンルでした。
レゲエを軸に、気楽に生きようよと語りかけてくるようなサウンドが大衆の心を掴みました。
とはいえ、ボロボロの体の傷が癒えてないクラプトンには、昔のような炎のギターを弾くことがままならず、速度を落としてみるしか手が無かったというのが真相なのではないかと邪推してしまうのですが。
リラックス・ムードでいっぱいのアルバムですが、1曲目だけはイケイケな「Motherless Children」だということを忘れずに。涼し気なスライド・ギターの応酬が心地良い響き。
ボブ・マーリーの「I Shot The Sheriff」を全米1位にして、レゲエを世界的なものにしましたが、あくまでロックの範疇で料理したところに技があると思います。
「Let It Grow」はよくレッド・ツェッペリンを引き合いに出されますが、それでも美しく憂いのあるメロディはクラプトンの新味だし、このアルバムに収録されたという重要性を感じます。
ドラッグ漬けから復帰、肩の力を抜いた新しいクラプトン・サウンドには、明るい未来を感じます。
アルバムのタイトルも、なんともカッコいい響きで大好きなんですよね。
No.1 Song 「Motherless Children」
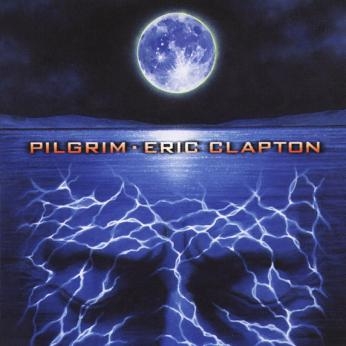
第27位 『Pilgrim』
『Unplugged』『From The Cradle』での大ブレイクを経て、企画物が続いた後に、落ち着いた環境で充実したオリジナル・アルバムを作り出しました。
穏やかさ、奥行き、深みなどが増して、一聴して気に入るというより、ジワジワと心に染み入るものになりました。
「River Of Tears」はジャケットのように、広くて大きな河をゆっくり漂うイメージのサウンド。
「Circus」はさりげないメロディが切なくも粋な屈指の名曲。
「Needs His Woman」はお洒落な空間。
全体的にはマイルドなレゲエ多し、といったところだけど、力を入れるところには入れて、これからのクラプトンが進む道を示しているアルバムになっていると思えます。
No.1 Song 「Circus」

第28位 『August』
前作『Behind The Sun』に続いてフィル・コリンズのプロデュース。
よって、これもあまり評判は良くないんだけど、僕は好き。
大袈裟なサウンドの中でクラプトンが元気なのがいいんです。
「It’s In The Way That You Use It」は冒頭のコーラス・ワークからして耳に残るフレーズ。
ティナ・ターナーとのデュエットが熱い「Tearing Us Apart」はとびきり跳ねています。
「Bad Influence」はスティーヴィー・ワンダー的な青春ファンク。
「Take A Chance」はホーンのノリがEW&F的。
「Miss You」は諦観溢れて気合い入れて乗り切るしかないといった感じ。
YMOの「Behind The Mask」はテクノをシンセ・サウンドで装飾し、ヴォーカルも入れて曲の良さを倍増させました。
このようなサウンドを聴いていると、いかにも景気のいい80年代といった感じで、パワーが漲ってくるんですよね。
No.1 Song 「Miss You」

第29位 『No Reason To Cry』
これは『461 Ocean Boulevard』『There’s One In Every Crowd』から続くレイドバック3部作の最終章と言っていいだろうけど、ここまで来ると、レイドバックと言うよりカントリー風かな。
しかも元気なカントリーだ。
それというのも、ザ・バンドやボブ・ディランがアルバム作りに強力に関わっているからですね。
「All Our Pastimes」なんて、モロにザ・バンド。
激情の「Double Trouble」。
女性ヴォーカルが入ってゴスペル風の「Innocent Times」。
「Black Summer Rain」は穏やかなのに何故か感情を揺さぶられ泣けてきます。
3部作の中では少し小粒になった印象ですが、長年のザ・バンドへのクラプトンの思いが結実した、コンセプチュアルなアルバムです。
No.1 Song 「Black Summer Rain」
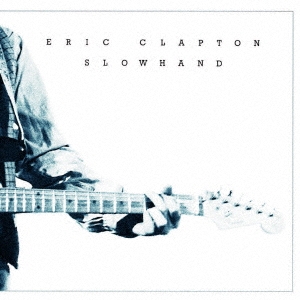
第30位 『Slowhand』
クラプトンの愛称を冠したタイトル、そしてジャケットがカッコいい!
高校生の僕はジャケ買いしました。
そして、とにかく冒頭3曲の流れが素晴らしい。
レイドバックから、ロックなクラプトンが戻ってきた感がありますが、どこか軽やかなんですよね。
その軽さが好きになれるかが評価の分かれるところ。
イントロのリフがループする「Cocaine」は今もライヴで盛り上がる、クラプトンの代表曲となりました。クールです。
うっとりする美しいバラード「Wonderful Tonight」を書かせたパティ・ボイドって、どこまで魅力的な女性なんだろう。
「Lay Down Sally」の軽快に力が抜けていく様に体が疼きます。
「The Core」はギター・リフからソロへと、ホーンを伴って渦巻いていきます。
「Mean Old Frisco Blues」は新しいタイプのブルース。
「Peaches And Diesel」は美しいインスト。
序盤が素晴らしかっただけに、期待がどんどん膨らむのですが、聴き進むにつれて、味が薄くなっていくようなのが惜しいところ。
そういう意味ではガムのようです。
悪いわけではないんだけどね。
やっぱりレイドバックの余波はあって、急には熱いロックにはなりきれないアルバム。
No.1 Song 「Wonderful Tonight」
第31位~第40位

第31位 『Backless』
クラプトンの代表曲と言えるような曲はなくて地味目。
だけど、明るいタイプの曲が多く、陽気で温かい雰囲気です。
クラプトンのギターも滑らかな音を出していて、聴いてて気分が良く、割と好きなアルバム。
「Tell Me That You Love Me」は心地良い風に吹かれているよう。
「If I Don’t Be There By Morning」は、タイトルの意に反して、朝起きた時から楽しくなるようなメロディ。
「Early In The Morning」のようなブルースもあります。
「Promises」は、軽いタッチで進む感じ、心もポカポカしてきます。
暖炉の前で、軽くギターをつま弾いて、家族や友人をもてなしているようなイメージ。
ジャケットには暖炉なんて写ってないですけど、僕にはそう見えるんです。
No.1 Song 「If I Don’t Be There By Morning」
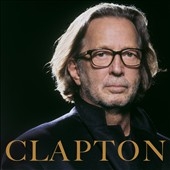
第32位 『Clapton』
クラプトンの音楽はブルースが軸なんだけど、この辺りからジャズやスタンダードの要素が強くなってきた気がします。
枯れた味わいも顕著で、そしてそれらをクラプトン色に染めてる渋い1枚。
カヴァー曲で固めたというのに、アルバム・タイトルを自分の名前にしているところが意味深です。
「Travelin’ Alone」はモコモコブルース、陽だまりブルース、裏道ブルース。
「How Deep Is The Ocean」はいかにもスタンダードなナンバーの響きで、ギターやホーンの音色もマイルド。
「Run Back To Your Side」は明らかに他の曲と違うノリの良さ。ギターも鳴いて、泣いています。
最後の「Autumn Leaves」は、このアルバムのコンセプトを象徴してる仕上がり。
なかなか曲が書けなくなってきて、こういう企画物が出るのは自然なことかもしれませんが、クラプトンにしては異質というか、なかなか新感覚のアルバムになってます。
ただ、こういう路線もいいけど、やっぱりオリジナル曲を書いてほしいよね~と思っちゃいます。
No.1 Song 「Run Back To Your Side」

第33位 『Old Sock』
ジャケットの通り、好々爺になったクラプトン。
レゲエ、ジャズを陽気に、のんびりと。
渋めのスタンダードもありますが、ぽかぽかな曲が目立つ、和むアルバムです。
温かめの曲としては「Further On Down The Road」や「Every Little Thing」など。
「Born To Lose」や「Goodnight Irene」などのカントリー系も和みますね。
逆に気合いが入るギターの嵐なのが「Gotta Get Over」。
フェンダー・ローズの音が印象的で、ピアノ、ストリングス、ブラシといった楽器が渋いのが「Still Got The Blues」。
そして、ラストのスロー・ジャズ「Our Love Is Here To Say」の明るさが沁みます。
アメリカの雄大な土地で農作業をして暮らしているようなイメージがあります。
穏やかな日々に感謝したくなります。
No.1 Song 「Still Got The Blues」

第34位 『Behind The Sun』
フィル・コリンズ・プロデュースのアルバム、ものすごく評判悪いんですよね。
いかにも80年代のゴテゴテしたサウンドが、普遍性を持ってないということなのかも。
クラプトンがソロを弾いてても、キーボードなどの大袈裟なサウンドで薄れてしまうのも気になります。
でも、曲自体は好きなのが多いし、僕は決して嫌いではないです。
「She’s Waiting」から、力強く歌ってるクラプトンよりも、シンセの大袈裟な響きが耳に残ります。
「Same Old Blues」もブルースの割には煌びやかで重厚なサウンド。
評判悪いこのアルバムでも、決して駄作とまでは言いきれないのは「Forever Man」というヒット曲を生み出しているから。「Layla」以降にここまで熱き情熱をぶつけた曲は久々ではないでしょうか。
「Tangled In Love」はデジタル・サウンドのノリの良さが良い方向に転びました。
「Just Like A Prisoner」はフィル・コリンズらしいシンセと、クラプトンのギター・ソロの応酬が嵐を呼びます。
曲は悪くなかったのに、トレンドを追いかけたサウンド作りが悪かったのかもしれません。
80年代のクラプトン迷走期を象徴するアルバムとなってしまいましたが、秘かに愛してるファンも多そうです。
No.1 Song 「Forever Man」
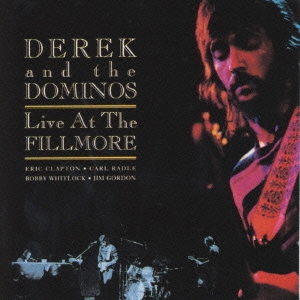
第35位 『Live At The Fillmore』
Derek & The Dominos
73年にドミノスのライヴ盤として『In Concert』が出てましたが、94年に完全版のこのアルバムが出て、今やこちらがスタンダードになってます。
僕、アルバム『Layla』が大好きですから、このドミノスのライヴ盤にはめっちゃ期待したんですよね。
しかしコレ、1曲1曲がムダに長くて。
『Layla』という名盤を作り上げた新バンドなのに、ジャズ・インプロビゼーションの要素が強かったクリームの頃と同じやり方のライヴをやってます。
デュアン・オールマンがいない分、がんばろうとしてるのか、クラプトンは弾きまくってるんだけど、空回りしてる感じで、いまいち熱くなれなくて、なんだかダレてしまうのです。
あの名盤の完成度を知ってるだけに、ここにデュアンがいたらなあと強く思ってしまいます。
しかも、ドミノスいちばんの代表曲「Layla」がないというのも、画竜点睛を欠き、大きなマイナス・ポイント。
期待が大きかっただけに、ガッカリ度も大きな印象となってしまいました。
クラプトン自身もライヴがうまくいかなかったと感じたのか、この後バンドを解散し、ドラッグに溺れていくことになるのです。
でも、一人でギター弾きまくるクラプトンという観点から見ると、一定の魅力があるアルバムではあります。

第36位 『Rush』
映画音楽ということで、インスト多いし、純粋なオリジナル・アルバムとカウントされないかもしれません。
でも、ギターはかなり弾いてるし、しっとりと泣きのメロディが多く、哀愁を含んだドラマチックな構成、全然悪くないです。
そして、なんと言っても「Tears In Heaven」が入ってますからね。
『Unplugged』で有名になった感がありますが、元々ここが原典でした。
なので、しっかりクラプトンのディスコグラフィーの中に入れておきたいアルバムなんです。
物悲しいインストが並んでいって、このまま終わるのかなと思ってたら、終盤の「Help Me Up」で、いきなりクラプトンが歌い出してビックリ。R&Bソウル風の力強いノリでなかなかの佳曲。
続く「Don’t Know Which Way to Go」はブルースですが、歌ってるのは誰??となります。
そしてラストに「Tears In Heaven」が配置され、ここに至ってすべてが昇華されていく感じとなっています。
何度も何度も聴きたいとまでは思いませんが、このアルバムの存在は決して忘れてはいけないなと思っています。
No.1 Song 「Tears In Heaven」

第37位 『Unplugged』
ギターの神様だったクラプトンが、渋くてお洒落なオジサマへ。
クラプトンをそれまでと違う次元へ導いた大ヒット・アルバム。
ジョージ・ハリスンとの来日公演を終えた直後に収録されたMTVの番組。
これを機に、世界中でアンプラグド・ブームが巻き起こりました。
愛息・コナー君をなくして消沈していたクラプトンが、新たな一面を見せて大きな結果を残したというのは嬉しかったです。
ただ、僕的には、アコギによる弾き語り系は1、2曲ならいいけど、アンプラグドだけで攻められるのは苦手なんですよね。
ちょっと飽きちゃうというか、やっぱりエレクトリックな音を求めちゃうのです。
なので、世間の過熱ぶりにはちょっと距離を置いていて、あまり思い入れの持てないアルバムです。
『Unplugged』の大きな功罪としては、「Layla」のアコースティック・ヴァージョンをヒットさせてしまったこと。これはこれで良いアレンジではありますが、ヒットしすぎて、この後のライヴでエレクトリック、アコースティック、どちらのアレンジで演奏するかの選択を迫られることになってしまいました。ファンによっても好き嫌いがあるだろうし、ライヴで聴けるのはどちらなのかという当たりハズレの世界を作り出してしまいました。
「Tears In Heaven」は、ここで大いに注目され、大ヒットに至りました。コナー君も喜んでいるかも。
「Lonely Stranger」は天にも昇るようなメロディが素晴らしい。
「Old Love」のアレンジも良くて、これも「Layla」並みにヒットしてほしかったところです。
アコースティック編成でも意外と迫力あるバンド・サウンドの中、粒立ったアコギの音色がとても良いんです。
クラプトンのオリジナル曲に限らず、ブルースの古典も、渋いアレンジでサラッと決めれば、お洒落な大人の音楽として、多くの人に受け入れられるのだということを証明しました。

第38位 『The Road To Escondido』
J.J.Cale & Eric Clapton
J.J.ケイルが相手ということで、もっとブルース色が濃いのかと思ってたら、意外とカントリー系の軽快さが強めでした。
なんだ、J.J.ケイルはブルース・シンガーじゃなかったのか。
「Heads In Georgia」は諦めを含んだ憂いあるサウンド。
「When This War Is Over」はポンコツ車で軽快にドライブするような幸福感を伴っています。
「Dead End Road」は性急なカントリーにゴキゲン。
「It’s Easy」での適度な力の抜け具合。
「Hard To Thrill」は乾いたギターが渋く、ピアノも印象的。
「Don’t Cry Sister」は、小気味良い「Cocaine」といった感じで疼きます。
B.B.キングの時と違って、今度はどちらかと言うとJ.J.ケイル主導のコラボになりました。
それ故、クラプトン贔屓の僕としては、ちょっと歯がゆいというか、強く推せないところがあります。
ただ、ギターの音色が生々しく録音されているのは隠れた長所だと思います。
No.1 Song 「Don’t Cry Sister」
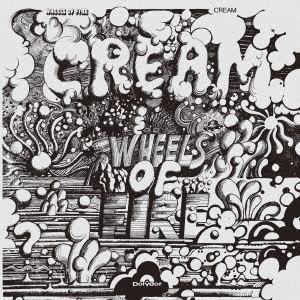
第39位 『Wheels Of Fire』
Cream
サイケの次は、なんだか怪しい感じのサウンドが目立つようになってきたクリームの3rdアルバム。
ジャケットの色もカラフルからモノクロになって、モコモコした不思議なデザイン。
しかし、ここからクラプトンのギターが火を噴き始めるのです。
スタジオ録音とライヴ録音の2枚組。
スタジオ盤もいいけど、クリームはやはりライヴに魅力があることを実感するのです。
おどろおどろしく妖艶な世界の「White Room」。
緩急自在ながらも、ヴォーカルが不気味な「Passing The Time」。
ブルージーなリフで勝負の「Politician」。
「Born Under A Bad Sign」は間延びしたブルース。
「Deserted Cities Of The Heart」は荒れ果てた街を目にする切迫感に溢れています。
「Crossroads」のスピード感にゾクゾクします。スロー・ブルースをスリル溢れるロックンロールに変えたクリームの素晴らしさがわかります。
「Spoonful」はメンバー三者三様、好きなようにプレイしながら、緊張感が張りつめています。
メンバー間の確執が、不思議なアイデアや緊張感あるプレイを生み出していることは事実で、アルバムごとに方向性を変えてきたクリームも、いよいよ袋小路に差し掛かってるかのような危険な匂いもあります。
しかし、そんなギリギリのところにいるのが魅力でもあるんですよね。
No.1 Song 「Crossroads」
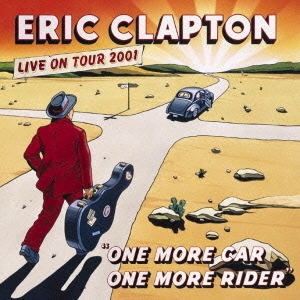
第40位 『One More Car, One More Rider』
ロック、ブルース、バラード、アンプラグド、それまでのクラプトンの代表曲をしっかり抑えて、新旧のバランス良く、ベスト盤のような良いセットリストで、充実したライヴなのがわかります。
だけど、期待したほど、聴いてて燃えないのは何故だろう。
これが無難なところだろう、と感じちゃうんですよね。
手堅くまとめてきた感があるからですかね。
時期的にも、曲もプレイも脂が乗ってるのは間違いないです。
初めてクラプトンを聴く人に薦めてみるのも悪くないとは思います。
ただ、個人的な感覚なんですかね。
熱くなれない自分がいます。
クラプトンのツアー止める止める詐欺が始まったのもこの頃ですね(笑)。
第41位~第51位

第41位 『Meanwhile』
今のところの最新作は、ギターも歪んで良い音。
しかもお洒落な雰囲気を忘れず纏っているし、一時期枯れていたクラプトンに、熱意が蘇った感じがするのも嬉しいポイント。
ただ、完全に街ブラしているお爺ちゃんになっているジャケットをどう思うかですが。
冒頭「Pompous Fool」から野太い音色のギターが唸る、まさにクラプトンの音だとわかるブルース・ブギは新しいレイドバック。
「Heart Of a Child」は芯の通った渋いセッション風の演奏で、なかなか長尺の曲で聴き応えたっぷり。
「Moon River」は超有名曲で、亡くなる直前のジェフ・ベックとの共演。ですが、2人のギターの音色の違いが聴き分けられず、困ってます。
「Sam Hall」は牧歌的なアメリカン・ロックで、2023年の来日公演でも披露されました。
「One Woman」は「I Shot The Sheriff」を彷彿とさせる熱いレゲエ・タッチのナンバーで、お洒落なクラプトンの本領も発揮。
「The Rebels」「This Has Gotta Stop」「Stand and Deliver」という、ヴァン・モリソンとの3曲の共演も話題。おおむねノリが良く、クラプトンも活き活きとソロを弾いています。
「You’ve Changed」は艶のあるギターに心奪われ、低音ボイスで歌うクラプトンとジャズっぽいサウンドが粋で、とても魅惑的な曲です。
全体的には、とても落ち着いた味わいです。
もはや、ガッツリとしたロックンロールもなく、縦横無尽にギターを弾きまくるようなブルースもない。
かと言って、枯れた感じでもなく、リラックスしすぎてる風でもない。
とにかく、とてもいい塩梅で、長いキャリアから来る余裕のプレイを見せている、主張しすぎないクラプトン。
さじ加減が絶妙でした。
No.1 Song 「You’ve Changed」
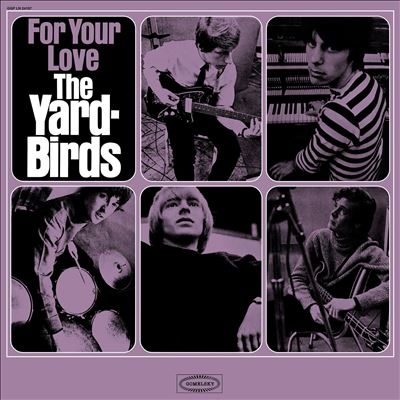
第42位 『For Your Love』
The Yardbirds
ヤードバーズがポップになって聴きやすくなったというのに、そのポップさを嫌ってクラプトンは脱退したということがショックでした。
その要因となった「For Your Love」の作者がグレアム・グールドマンだというのも、10ccファンとしては複雑なところです。
コレはその「For Your Love」の予想外のヒットによって編まれたアルバムで、クラプトンのあずかり知れるところではないのかもしれないけど。
よって、クラプトンは全面参加じゃないけど、クラプトンらしいソロも聴けるし、1stよりずっといいじゃないかと思ってしまうのです。
「For Your Love」は切ないメロディで引き締まってるし、良い曲だと思うんだけどなあ。どこがポップすぎるっていうんだよ、クラプトン。
「I Ain’t Got You」は勇ましいリズムとリフ。ハーモニカも効果的で楽しい曲です。
「Good Morning Little Schoolgirls」のスピード感は一聴に値。
クラプトンが、このバンドではやっていけないと決断した理由が知りたいのですが、永遠に理解出来なさそうです。
No.1 Song 「For Your Love」

第43位 『Disraeli Gears』
Cream
『カラフル・クリーム』とはよく言ったもので、サイケとはカラフルなんだと。
一聴してわかるクラプトンのギター・サウンドの原点はこの辺りにある気がします。
ジャック・ブルースと張り合うためか、ギタリストとしてだけでなく、シンガーソングライターとしても開眼し始めたクラプトン。
1stと違い、このアルバムではブルース色はやや薄れ、ポップ寄りになって聴きやすいです。
サイケ・ロックというのはこれで知った気がする「Strange Brew」。
イントロのギター・リフが命の「Sunshine Of Your Love」。
「Dance The Night Away」は全然踊れるものではありませんが、キューッと締め上げるようなメロディがたまりません。
小気味よく進んでいき、ちょっとコミカルな面も見せたりして、クリームの可能性を広げました。
No.1 Song 「Dance The Night Away」

第44位 『Fresh Cream』
Cream
クリームの1stアルバムは、渋いブルース・ロック。
なんとも玄人好みな感じです。
まだクラプトンが弾きまくってるイメージはなくて、ジャック・ブルースが曲作りとヴォーカルで、いちばん活躍してます。
ただ、ブルースが1人目立つようなこともなく、あくまで3人が対等な関係だったことが窺えます。
「Spoonful」はヴォーカルとギター、ベース、ハーモニカのユニゾンで攻めるのが印象的。
ギタリストだったクラプトンが、「Four Until Late」で本格的に歌い始めます。
「Rollin’ And Tumblin’」は激しいを通り越して、騒がしいです。
「I’m So Glad」はスリルがありながらも、3人のバランスのいい演奏が楽しめます。
お子様だった僕は、このアルバムをなかなか聴こうとしなかったし、渋みを理解することができませんでした。
大人になって、ようやくブルースが好きになり始めて、このアルバムに対する印象が変わってきたのを感じます。
No.1 Song 「I’m So Glad」

第45位 『Money And Cigarettes』
アルコールに溺れた代償も高く、妻・パティともうまくいかなくなってきていて、そんなプライベートの問題が作品にも影響を与えました。
カントリー風ノリの良さが目立つアルバムで、全然悪くないけど、これぞという強みがないかもしれません。
こういうアルバムを作りたいという明確なイメージや、強い意志がなく、なんとなく作ってみただけで、焦点が定まってない感じがします。
「Everybody Oughta Make A Change」はレイドバックかと思ったら、意外と跳ねてるビート。
「The Shape You’re In」はたくさんギターを弾きながらノリが良いです。
「Ain’t Going Down」での切迫感あるギター・アンサンブルは、ダイアー・ストレイツみたいです。
「Man Overboard」は温かい風に吹かれるサザン・ロック風。
穏やかなバラード「Pretty Girl」はギターがキラキラしています。
「Crosscut Saw」は強力リフが鳴る裏で弾きまくるソロ。
アルバムのタイトルはいいんですけどねえ。
テーブルの上のギターが溶けているように、クラプトンの心もダラッとしてるというか、音楽に身が入らない心境だったのかもしれません。
No.1 Song 「Crosscut Saw」

第46位 『The Lady In The Balcony』
副題に【Lockdown Sessions】とあるように、コロナ禍で中止になったライヴの代わりに、仲間たちだけで行われた観客のいないスタジオ・ライヴ。
アコギ、ピアノ中心で『Unplugged』第2弾的な雰囲気が漂う演奏形態。
とはいえ、『Unplugged』とは違ったアレンジも見せています。
お馴染みの「Nobody Knows You When You’re Down And Out」からゆっくりエンジンに火を付けます。
「Key To The Highway」も定番曲ですが、軽快にドライヴするようなアレンジになっています。
「Believe In Life」はお洒落に施されていて、このライヴの雰囲気をいちばん象徴しています。
「Layla」と「Tears In Heaven」は『Unplugged』とほとんど変わらないアレンジ。
このままアコースティック主体で行くのかと思いきや、「Long Distance Call」「Bad Boy」はエレクトリック・ブルース。
やっとクラプトンの本領が発揮された感のある終盤3曲がいいんですよね。
コロナ禍にオンライン配信されたりしたライヴって、こういう小ぢんまりとした、日常を感じさせるようなライヴを見せるアーティストが多かったですよね。
クラプトンも然りで、細々ながらも、今できることをやってますよ的なアピールをしていました。

第47位 『Me And Mr. Johnson』
ブルースといえば、伝説のロバート・ジョンソン。
全曲ブルースのカヴァー曲で固めたアルバムを作ったりしたクラプトンだけれど、こうなったら、全編ロバート・ジョンソンの曲でアルバム作ってしまえ、というノリになりました。
元々ロバート・ジョンソンがそうだったように、アコギやハーモニカを中心に添え、アコースティックな響きを大切にしたサウンドとなりました。
「When You Got A Good Friend」「Me And The Devil Blues」「Kind Hearted Woman Blues」が、これぞ直球のブルース。
「Little Queen Of Spades」は今でもクラプトンのライヴで重要なレパートリーになってる曲。でも、ここではライヴとはちょっと違うアレンジ。
「They’re Red Hot」「Last Fair Deal Gone Down」あたりは軽快で、ブルースの範疇から飛び出してる感も。
「Milkcow’s Calf Blues」でのエレクトリック・アレンジは良いな。
ストーンズも採り上げた「Love In Vain」はリズム感が違うものの、ホンキー・トンク・ピアノが入ったりして。
こういうアルバムを作ってる時が、クラプトンはいちばん楽しいのかもしれませんね。
ただ、ロバート・ジョンソンのCDも聴いて思ったのですが、そもそも僕はあんまりロバート・ジョンソンが好きではないみたいなんですよね。
どうして、そこまでクラプトンが入れこむのか理解できない。
よって、このアルバムにものめりこむところがないのです。

第48位 『Royal Albert Hall London May 2-3-5-6, 2005』
Cream
05年、まさかのクリーム再結成。
金銭面で苦しむメンバーにクラプトンが手を差し伸べて企画したとも言われています。
クラプトンも弾きまくってるし、ピリリと緊張感のある演奏は相変わらず。
ただ、昔はとびきりスリリングだった「I’m So Glad」などが、めちゃくちゃスピードが遅くなったりしていて、なんじゃこりゃ、やっぱり歳取ったな、と感じる場面も多々あります。
演奏が終わる度にお互いを紹介しあったりしていて、リスペクトしてるのが伝わってくるのが、クリーム現役時との違い。
ジャック・ブルースもジンジャー・ベイカーも、いがみ合ってた昔のことは忘れたか、クラプトンが上手く仲介役を果たしたか。
奇跡の再結成を目撃出来たファンは幸せだったと思います。
ただ、こうしてランキングを作成してきましたが、クリームの作品が軒並み下位なのに気付きます。
決して嫌いではないんですけどね。
ただ、クリームはブルースが主導しているというイメージが強くて。
僕は根本的にクリームがあまり好きではないのかなという気がしてきました。

第49位 『On Tour With Eric Clapton』
Delaney & Bonnie & Friends
デラニー&ボニー、二人の熱いデュエットが主軸。
ホーンが煽ったり、スリリングでエネルギーを感じる演奏のライヴ盤です。
これに参加したクラプトン、クリームまでの路線とは違う音楽性で、化学反応を起こしているのが楽しめます。
「Things Get Better」からグルーヴィーなソウル。
「I Don’t Want To Discuss It」では、クラプトンが火の玉ソロを弾いていて、ひときわ熱い演奏とヴォーカルに興奮します。
「Coming Home」の狂乱のスワンプ・サウンドは、後にこのバンドがデレク&ザ・ドミノスに発展していく兆しが見えます。
それまでクラプトンが奏でてきた音楽とはかなり違うので、デラニー&ボニーのどこに惹かれて、クラプトンはツアーに参加したのか、その真意は謎なところがあります。
いい曲もあるんだけど、全然クラプトンを聴いてる気はしないんですよね。

第50位 『The Breeze – An Appreciation Of J.J. Cale』
Eric Clapton & Friends
クラプトンは過去何度もJ.J.ケイルの曲を採り上げて、「Cocaine」などを代表曲にもしました。
後年はコラボ・アルバムを作ったり、ライヴで共演したりしました。
その恩人・J.J.ケイルが亡くなったことを受けて制作された追悼アルバム。
トム・ペティ、ウィリー・ネルソン、デレク・トラックス、マーク・ノップラー、ジョン・メイヤーらが集まりました。
まずはクラプトンが軽快に歌う「Call Me the Breeze」。
「Someday」はマーク・ノップラーの抑え気味の渋さ。
クラプトンのささやきボイスが粋な「Cajun Moon」。
「Magnolia」のジョン・メイヤーは落ち着いていて優しい。
「I Got the Same Old Blues」など、最多の3曲に参加したトム・ペティ。クラプトンとのギターが痺れる音を出しています。
J.J.ケイルがどんなアーティストだったのか、どんなジャンルの音楽と言っていいのか、未だに掴みどころがないんですよね。
これ聴いて、なんとなくわかってくれば御の字。
ただ、この作品も、純粋なクラプトンのアルバムとは言えないんですよね。

第51位 『Five Live Yardbirds』
The Yardbirds
エリック・クラプトンの名を最初に世に知らしめたライヴ盤。
ただ、もう一人のギタリストと共に、リズム・ギターをかき鳴らしている印象が強くて、あんまり強烈なソロを弾いてるイメージはないです。
なので、これがクラプトン?
クラプトンどこにいる?
と、何度も迷子になります。
「Five Long Years」などのブルース曲はありますが、ヤードバーズはどういうジャンルに属するバンドなのか、いまいちわからないところがあります。
純粋にブルース・バンドと言い切れない感じだし。
とにかくコレは、勢いで走りまくってるライヴという印象。
クラプトンのギターよりも、キース・レルフのハーモニカが目立ちます。
さて、いかがでしたでしょうか。
まずは、50枚以上のアルバムについて、最後まで読んでくださった方がいらっしゃるなら、お礼を申し上げたいと思います。
読んでくださってありがとうございました。
あなたの好きなクラプトンと僕の好きなクラプトンには、どれだけ違いがあったでしょうか。
同じアーティストを好きでも、同じアルバムが好きとは限らないのが面白いところだったりします。
いろんなファンの方の意見があると思います。
僕は、そういうファンの意見の違いを面白がったりしたいので、まずは自分の好みを披露してみました。
とにかく、60年以上のキャリアを持つクラプトン。
いくつかのバンド時代も含めて、アルバム数が多いので、順位を決めるのは大変でした。
基本的にはどれも好きなので、順位なんて紙一重、その瞬間の気分によるものだったりします。
同じアルバムでも、聴くタイミングによって印象が変わったり、何度か聴き続けたりする事によって良さがわかっていったりするものもあります。
ベスト3とワースト3あたりはこれで変わらないような気がしますが、中盤のランキングは、これからコロコロと入れ替わる可能性がありますね。
実はまだあまり聴きこんでないアルバムもあったりしますので、これからもっと聴きこんで、もっとクラプトンを好きになっていきたいと思います。
当ブログ管理人・カフェブリュは、X (Twitter)にて、毎日発信を行っています。
サザンオールスターズ、佐野元春、ビートルズを三本柱に、60’s~90’s ロック&ポップスの話題。
購入したCD・レコード紹介、 ロック名盤レビューなどをポストしています。
よろしかったらこちらもチェックしてみてください。


コメント