
ジャケット写真が TOWER RECORDS の商品にリンクしています。
『BACK TO THE STREET』
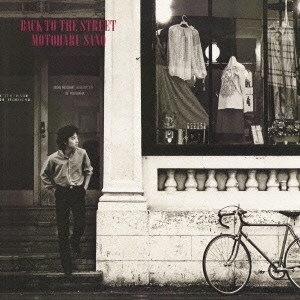
佐野さんが「シティじゃないんだ、ストリートなんだ」と言ってたのが目から鱗というか、なんだか腑に落ちて。
「アンジェリーナ」の疾走感とかね、全体を俯瞰するでなく、目の前のものしか見てない若さが最高。
(2024.3.6)
『VISITORS』が出た時、「佐野さんが歌わないで喋ってる!」とみんな驚いたそうだけど、このアルバムから既に「夜のスウィンガー」とか「アンジェリーナ」とか、早口で喋ってるようじゃないか。
歌詞を目で追うと実感する。
『VISITORS』の衝撃の萌芽は既にあったんだ。
(2024.6.27)
ブルース・スプリングスティーンなど、アメリカン・ロックからの影響を感じさせることで有名な、初期の佐野さんだけど。
1stに収められている「グットタイムズ&バットタイムズ」だけは、アイルランド~イギリス系のギルバート・オサリバンの音楽の香りがする。
リズム楽器と化しているピアノのアタック、さり気なく細かい雨粒が落ちてくるようなアコギ、気分を徐々に高揚させるストリングス。
オサリバンの「Alone Again」あたりを想起させる、繊細なアレンジだ。
この志向は佐野さんによるものなのか。
それとも、初期の佐野さんを支えた名アレンジャー・大村雅朗によるものか。
B面1曲目の弾けたロックンロール「アンジェリーナ」の1歩手前のA面最後で、ポツンと佇んでいるかのような味わいを見せている。
(2024.11.10)
『Heart Beat』
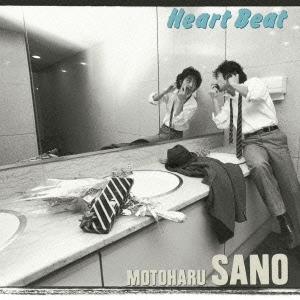
ジャケットがお洒落。
発表当時の代表曲は間違いなく「ガラスのジェネレーション」だったけど、現在でも歌い続けられることになってるのは「悲しきレイディオ」。
同じくラジオ賛歌のクイーンの「Radio Ga Ga」より3年早い。
この曲のライヴ映像を観て佐野さんにハマった。
(2024.3.9)
歌詞を目で追いながら聴いてたら、今まで気に留めてなかった「ナイトライフ」の輝きに気付いた。
若き恋人たちの物語が微笑ましい。
「君をさがしている」は華やかなモッズ・サウンドだし、青春の熱い鼓動がほとばしってる。
「ガラスのジェネレーション」含め、若者の代弁者。
「イッツ・オーライト」「悲しきレイディオ」と、ポップで軽快なロックンロールもあるんだけど、「バルセロナの夜」「彼女」そして「ハートビート」と、3曲のバラードの存在感が大きくて、アルバムの半分くらいがバラードだったようにも感じる。
(2024.7.1)
「ガラスのジェネレーション」と「ナイトライフ」がシングルだったわけだけれど、どちらの曲も近年のライヴではやってなくて。
となると、今も歌い続けられている「悲しきレイディオ」や「ハートビート」などが、このアルバムを代表する曲となっている印象だ。
特に「悲しきレイディオ」は、後半にメロディが付け足されて「♪ 愛する気持ちさえ分け合えれば I Love You」「♪ You Love Me」という観客とのコール&レスポンスが恒例となっている。
僕も初めて観たライヴDVDで、このシーンに感動して、僕も会場で佐野さんにレスポンスしたい!と思ったのだけれど。
でも、僕がファンになってすぐコロナ禍になってしまった。
以降、ライヴでこの曲を演奏したとしても、コール&レスポンスは封印されてしまった。
もちろん、原曲だけでも素晴らしい曲なんだけれど、ファンの間ではお馴染みになった、このコール&レスポンスをすることで、佐野さんと観客の距離がグッと縮まる場面になってると思うんだよね。
とても心が温まる感じで。
僕もいつかはコール&レスポンスしてみたい!
できれば、来年の45周年記念ライヴで、コレを復活させてほしいと願っているのですが、どうでしょう。
(2024.10.21)
このアルバムを思春期に聴けたあなたはつくづく幸せだ。
僕は最初、このアルバムを舐めていた。
リリース当時はあまり売れなかったみたいだし、聴きどころは「ガラスのジェネレーション」くらいなんじゃないの?って。
たしかにね、「ガラスのジェネレーション」の存在感は凄い。
ポップに跳ねまくる躍動感の中で、つまらない大人になりたくないというメッセージ。
思春期に出会ったら、刺さらないはずがない。
何かと語られるのはこの曲だ。
でもさ、アルバムを何度か聴いていくと、それだけじゃないとわかってくるんだよね。
まず、「悲しきレイディオ」の疾走感にやられた。
動かずにはいられない、若いエネルギーの行き場所を教えてくれるのはコレだ。
ノリの良さという点では「イッツ・オーライト」も負けてない。
ステップ踏んで踊りたくなる。
「ナイトライフ」は、シングルの割にはのっぺりしたメロディだし、ちょっと地味かなあと思ったけれど、サビになったら起伏が激しくなって、「11時までに」あたりのメロディは最高。
門限を気にする若い恋人たちの歌詞も良いよね。
「君をさがしている」は、キラキラとした青春のモッズ・サウンドだと気付いてからは愛聴曲。
バラード3曲もなかなか強力で。
「バルセロナの夜」はボサノバ・タッチで、なんともお洒落で都会的。
「彼女」はピアノ弾き語りから、徐々にストリングスが入って、いつのまにか盛り上がっていく。
「ハートビート」は都会の夜を生き抜く恋人たちの重厚な物語。
いつか言ってみたいね「まだ4時半だぜ」。
「グッド・バイブレーション」はなかなか掴みどころがなくミステリアス。
おやおや、こうして、どんどん聴きどころが増えていく。
「ガラスのジェネレーション」1曲に頼るわけではなく、アルバム全体が大きな魅力に溢れていることに気付いた。
舐めててごめんなさい。
こうして佐野さんは若者の心を掴んでいったんだなあというのが、後追いでもしっかり感じ取れるアルバムだ。
(2025.1.27)
『SOMEDAY』
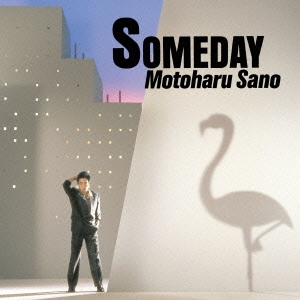
ベスト盤『No Damage』から入った人は、このアルバムに遡るのを躊躇した人もいたかもしれない。
「サムデイ」を筆頭に結構な曲が被ってたから。
でもコレには「ダウンタウンボーイ」が、「ヴァニティ・ファクトリー」が、「ロックンロール・ナイト」がある。
安心して手を伸ばせ。
(2024.5.22)
甘いメロディの「シュガータイム」、気分が高揚する「ハッピーマン」、清々しく甘酸っぱい「ダウンタウンボーイ」と、冒頭3曲だけで多幸感でいっぱい。
メイン・ディッシュの「サムデイ」の前にこれだけの満足感とは!
しかもその後にも「ヴァニティ・ファクトリー」「ロックンロール・ナイト」などの名曲が控えてるなんて、名盤すぎるにもほどがある。
(2024.7.9)
『VISITORS』
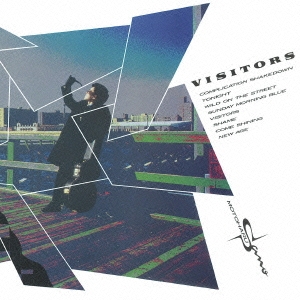
コレ聴いて思ったコト。
1. 「トゥナイト」の女性コーラスは同時代に出たプリファブ・スプラウトのウェンディみたいだな。
2. 「ワイルド・オン・ザ・ストリート」はベースやドラムのビートの裏でパーカッションの音が生々しくて良い音。
3. 「ヴィジターズ」のアレンジに影響受けて、翌年、中村あゆみの「翼の折れたエンジェル」が出来たんじゃないか?
4. 「カム・シャイニング」「ニューエイジ」などは佐野さんのラップがハモってるから心地良いのでは。厳密に言うとライヴでは再現不可能?
いつ聴いても刺激に溢れたアルバムだなぁ。
(2024.7.16)
『Cafe Bohemia』
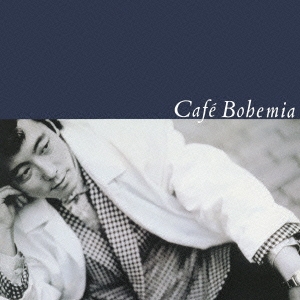
『VISITORS』の衝撃を経て、佐野さんの興味はNYのヒップホップからUKお洒落サウンドへ。
特にポール・ウェラーに着目。
「ヤングブラッズ」「インディヴィジュアリスト」など、影響を隠さずも、佐野さんのメロディに落とし込んで聴きやすいものに。
洋楽と邦楽を繋いだ名盤。
(2024.3.21)
スタカンのパクリだと散々言われたけど、たしかに、フォーマットは頂いてる。
まずタイトルも『Cafe Bleu』から。
ジャケット写真も、スーツの上に白いコートを羽織ってるのはポール・ウェラーのそれ。
音楽的には「Shout To The Top」から「ヤングブラッズ」が、「Internationalists」から「インディビジュアリスト」が生まれてるのは明白。
そしてミック・タルボットが弾いてるようなオルガンをフィーチャーした、ジャジーな雰囲気のインストがあったり。
とにかく、様々なタイプの曲をお洒落に並べてるのがね。スタカンの姿勢そのもの。
自分より年下のポール・ウェラーをリスペクトして、いいところを自分なりに咀嚼した佐野さん。
でも、これをパクリだと軽くみてたら、名盤を聴き逃して、人生損することになる。
だいたい、「ヤングブラッズ」が「Shout To The Top」のパクリだって言うけどさあ、似てるのはイントロのリズムの取り方。
でもスタカンはマイナーコードだけど、佐野さんのはメジャーコードじゃん。
それから、歌い始めた時に流れるストリングスの音。
……みんな「雰囲気」だけじゃん。
メロディは全然違うし、よく聴いたら、似てるかコレ?ってレベルだよ。
コヨーテ・Newヴァージョンの「Youngbloods」はマイナーコードにして、ミック・タルボット風のピアノにして、さらにスタカンに似せてきたのがとても痛快だったけど、それ聴いたら、ますます元の「ヤングブラッズ」はスタカンに似てないじゃんと思うようになったよ。
パクリだってバカにしてた人はちゃんと耳の穴かっぽじって聴いてみてよ!って感じ。
(2024.7.19)
佐野さん最大のヒット曲「約束の橋」を収録したアルバム『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』がサブスクでは聴けない大問題は有名だけれど。
実はこの『Cafe Bohemia』も、全曲サブスクで聴ける訳ではなくて、聴けない曲が2曲ある。
これも、微妙に嫌な話だ。
アルバムはコンセプトがある場合もあるし、やはり1曲目から最終曲までの流れがアートだと思っているので、こういう抜けがあるのは許せない。
何故サブスクで聴けないのか。
『ナポレオンフィッシュ』はロンドン・レコーディングのため、制作に関わった外国人の権利の問題なのでは?と想像してきた。
実は『Sweet 16』も1曲、「エイジアン・フラワーズ」が聴けないようになっていて、これはゲスト参加したオノ・ヨーコとショーン・レノンの権利関係ではないか?と容易に想像できる。
それでは、『Cafe Bohemia』の場合は?
海外でレコーディングしたという話も聞かないし、どこに理由が?と思ったら。
ミックスを担当しているのが3人の外国人だった。
その中のジョン・ポトカーが担当しているのが、まさしくサブスクで聴けない「インディビジュアリスト」と「99ブルース」の2曲だったのだ。
ジョン・ポトカーが原因か!
サブスクを容認しない方針でも持ってるのか?
と疑ったんだけれど。
でも、なんと、このジョン・ポトカーなる人物。
前作『VISITORS』では全曲ミックスを担当しているではないか!
ご存知の通り、『VISITORS』はサブスクで全曲しっかり聴けるようになっている。
こうなると、『Cafe Bohemia』の2曲が聴けない理由がわからなくなってくる。
ジョン・ポトカーがカギを握っているのは間違いないだろうけど。
こういう、権利の関係でサブスクで聴けないという場合。
解決することは永遠にないのだろうか。
関係者の努力で問題がクリアになり、いずれサブスクでも聴けるようになる日が来る場合もあるのだろうか。
こういうことがあるから、サブスクには全幅の信頼を置けないところがある。
大好きなアルバムは、CDなりレコードなり、フィジカルで所有しなければならない必然性を感じる。
でも、それはそれでめんどくさいことで。
世の中すべての音楽がサブスクで聴けるようになる日が来るのを願うばかりなのだが、たとえば山下達郎のように、自分の音楽をサブスクで配信したくないというポリシーを持っている人も多いから、そんなアーティストの意志を踏みにじるわけにはいかないし。
なんとも微妙な問題だ。
(2024.12.2)
『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』

『Cafe Bohemia』は日本からUKサウンドを眺めた結果だったけど、今度はロンドンへ乗り込んでレコーディング。
「ナポレオンフィッシュと泳ぐ日」「新しい航海」の華々しさときたら!
「雨の日のバタフライ」はとても心地良いサウンド。控えめなメロディと歌声もいい。
風変わりな「俺は最低」、物語を語る「ブルーの見解」も新機軸でいいアクセント。
中盤の「ジュジュ」「約束の橋」がポップ面としてのハイライト。
「雪 -あぁ世界は美しい」は、ジョン・レノンの「Love」みたいな、俳句的な美しさを持つ、フワフワとした優しいバラード。
今までにも増して、いかに日本語を刺激的に響かせるかに重きを置いているアルバム。
ロンドンで作ったからこそ、逆に日本的なものに意識が向いた。
ただ、このアルバムはサブスクで聴けない状態というのが難点。権利関係の問題が原因でしょうか。
(2024.7.22)
佐野さんの最大のヒット曲「約束の橋」がサブスクでは聴けないという由々しき問題。
これを
「佐野さんが頑なにサブスク解禁しない」とか、
「佐野さんにとっては黒歴史なのかも」
みたいな意見をネットで見かけたけど。
断じてそんなことはない!
そんなわけで今日は、実はサブスクで『編集版』として聴ける、このアルバムの別テイク群を聴いた。
ハートランドの演奏によるデモ・ヴァージョンやスタジオ・ライヴ。
これらのテイクならサブスクでも聴けるということは、やはり公式テイクのサウンド面に何かクリアできない問題があるのだろう。
おそらく、権利の問題だよね。
公式テイクでの演奏をした、英国のミュージシャンたち。
かなりの人数がいそうだ。
その辺りがごちゃついてるのか?
でも、「おれは最低」と「雪 -あぁ世界は美しい」の公式テイクの演奏はハートランド。
それなのに、この2曲もサブスクで聴けないというのなら、演奏者の問題ではないのかも。
となると、これはプロデューサーのコリン・フェアリーが重要なカギを握っているような気がしてならない。
はたして真相は...。
で、『編集版』の別テイク群ですけど。
「新しい航海」が、歌詞が違ってて新鮮だった。
未発表の「枚挙に暇がない」が面白い。
とにかく、「それ言いたいだけですよね?」と言いたくなるようなほど(笑)、タイトルの連呼。
スカのリズムでノリも良く、楽しい曲だ。
この曲に出会えただけでも価値があった。
「愛することってむずかしい」は、こんなのアルバムに入ってなかったよね?
と思ったけど、これは確実に聴いたことある。
なんでだ?と思ったら、シングルのB面曲で、『Moto Singles』に入ってる曲だった。
どの曲も、ハートランドの演奏は、瑞々しくて、なんだか透明感があった。
バリバリのロックという感じはしない曲が多い。悪い意味ではなくてね。
デモ・テイクだからか?
(2024.7.24)
ニューヨークに渡って『VISITORS』を作り、帰国後はヨーロッパに思いを馳せた『Cafe Bohemia』を作り。
そして次はロンドンに渡ってのレコーディングとなったのが、この『ナポレオンフィッシュ』だ。
そんな流れで作られたものは、アルバム・タイトルはもとより、曲名も多くが日本語で構成され、歌詞もとりわけ日本語の響きを大切にしたものとなっている。
さらには、J-POPを代表する「約束の橋」が生まれている点も面白い。
洋楽的な要素を持ちながらも、いかにして日本語ロックに落とし込むかが佐野さんの大きなテーマであるのがわかる。
もっとも、リリースの時点では「約束の橋」は大きなヒットに至らず、3年後にTVドラマの主題歌となったことで、佐野元春史上最高のヒットを記録したという点も、いかにも日本的で面白い。
シティ・ポップからJ-POPへ。
佐野さんが意図したわけではないだろうが、このような認識の移り変わりが見て取れるアルバムでもある。
(2024.11.26)
『No Damage』
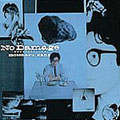
初期3枚のアルバムからの代表曲に、「スターダスト・キッズ」「ソー・ヤング」「彼女はデリケート」「バイバイ・ハンディ・ラブ」と圧倒的なポップ・ビートの曲などが加わった事で、極上のゴキゲンなベスト盤になった。
オリジナル・アルバム以上に愛着持ってる人多いでしょう。
(2024.3.15)
この素晴らしいベスト盤。
初期の佐野さんの魅力のエッセンスをまとめていて、オリジナル・アルバム以上に深い思い入れを持っているファンも多いことだろう。
この珠玉の作品集にはなんの文句もない、と言いたいところだけど。
A面が【Boy’s Life Side】、B面が【Girl’s Life Side】と銘打たれていることは有名で、なるほどと思うような選曲で配置されている。
だけど、どうしても解せないのが、【Boy’s Life Side】に、「ダウンタウンボーイ」が収録されてないということだ。
シングルにもなった人気曲なのに、ベスト盤に入れないのはどうして?
佐野さんのファンになりたての頃は、A面が【Boy’s Life Side】と呼ばれていると聞いて、ああ、「ダウンタウンボーイ」が入ってるんだろうなあと思いこんでた。
なんだったら、「ダウンタウンボーイ」が入ってるからこそ【Boy’s Life Side】と名付けたんじゃないの?と思ったくらいに。
でも、入ってなかったんだな、これが。
「ダウンタウンボーイ」は、シングル・ヴァージョンに納得できなかった佐野さんが、アルバム『SOMEDAY』には再録音したものを収録したという経緯がある。
もしかしたら、それすらも納得できなかった?
いずれにせよ、「ダウンタウンボーイ」に対して、佐野さんが他の曲とはちょっと違う思いを抱いていることは想像できる。
だけどなあ。
【Boy’s Life Side】と銘打つんだったら、「ダウンタウンボーイ」は入れてほしかったよなあ。
コンセプトがより確固たるものになっただろうに。
どうして?との思いが消えない。
(2024.9.18)
コレは1st~3rdアルバムの代表曲に、アルバム未収録曲をプラスしたベスト盤だと思ってたんだけど。
でも、収録曲をよく見てみると。
それまでにリリースしたシングル10枚のうち、表題曲が8曲。
B面曲が5曲入ってる。
それで全14曲だから、これはほぼシングル・コレクションじゃないか。
佐野さんがこだわりを持って選び抜いたようなイメージがあったのだけれど、単にシングルの曲を集めたと言ってもいいくらいだったのには驚いた。
ドーナツ盤になってないのは「情けない週末」だけ。
むしろ、数あるアルバム曲の中で、何故この1曲だけが選ばれたのかが興味深い。
佐野さんは「パーティー・アルバムだ」と言った。
これはベスト盤ではないと言うファンもいる。
実態は、ほぼシングル・コレクションのこの作品なのに、なにやらコンセプトのようなものを感じさせ、オリジナル・アルバム以上に意義深い作品であるとの印象をファンに抱かせたのは、特別な魔法がかかっているとしか言いようがない。
(2024.11.16)
『Moto Singles』

僕が初めて買った佐野元春のCDはコレだった。
1992年か93年だったと思う。
目当ての1つは「サムデイ」。
高校卒業の時に、TVのCMで流れてきて、とても胸を打たれたんだ。
うわぁ、これは卒業生へのエールだな、と。
だけど最近、博多大吉・華丸の大吉先生も、まったく同じことを言ってた。
大吉先生は僕より1つ年上。
となると、僕自身の卒業の時じゃなくて、先輩の卒業シーズンに聴いたのだったんだろうか。
2年連続でCMで使用された可能性もあるけど。
ま、そんなわけで、「サムデイ」をちゃんと聴いてみたいと思った。
もう1つの目当ては「約束の橋」。
ドラマの主題歌となってヒットしたのを知ってたからだ。
この曲も入ってるなら、ちょうどいいんじゃない?と思って、このベスト盤を選んだ。
目当てというよりも、きっかけだね。
そうして手にしたこの2枚組。
既にポール・ウェラーのファンになっていたので、「ヤングブラッズ」とか「インディビジュアリスト」のサウンドがとても嬉しかった。
他にも、いい感じの曲が多くて、満足した。
でも、そこで終わっちゃってたんだよなあ。
気に入ったのなら、もっと深掘りしていれば、もっと早くに佐野さんのファンになってたのになあと、悔しく思ってる。
その後の約30年の空白はとても大きい。
(2024.8.20)
アルバム中心に後追いで聴いた僕にとっては、
80年『BACK TO THE STREET』
81年『Heart Beat』
82年『SOMEDAY』
という情報が先にあったので、デビューから「サムデイ」が出来るまでは3年かかったんだなというイメージが強かったのだけれど。
でも、シングルで見ると、「アンジェリーナ」の半年後くらいに「ガラスのジェネレーション」が出てるし、「サムデイ」が出るまでには1年3ヶ月しか経ってない。
デビュー当初から才能ダダ漏れだったというべきか。
でも、1年ちょっとの間にこれだけ凄いものを作ってたのに、ホップ・ステップ・ジャンプがあまりにも早すぎて、リスナーが全然追いついてなくて、ヒットに至らなかった。
この後、佐野元春の名が売れたから良かったものの、もうちょっとで悲劇になるところだった。
それにしても、アルバムで見るのとシングルで見るのとでは、佐野さんの足跡のスピード感が全然イメージ違う。
(2024.10.25)
『THE LEGEND』

佐野さんのベスト盤もたくさん出てますが、佐野さんにハマった時によく聴いて、1番好きだったのがコレ。
EPICソニーの25周年の時に、所属アーティストのベスト盤がこぞって出ました。その時の佐野元春版。
初期の佐野さんの良い曲ばかりが1枚に収まってます。
1枚もののベスト盤というのがポイントで。
『No Damage』も素晴らしいですが、あれには僕が最初にハマった「ヤングブラッズ」が入ってないのでね。
80年代の佐野さんを俯瞰するという意味では、こちらの方が良い感じ。
シングルだけに注目してるわけではなくて、「悲しきレイディオ」とか「ロックンロール・ナイト」とか、重要なアルバム曲も抑えてるのがいいですね。
ただ、『VISITORS』の曲が全然入ってないのは難点かも。
「アンジェリーナ」から始まって、「サムデイ」を経由し、「約束の橋」で終わる。
まさに王道。
2枚組じゃないので、気軽に聴けるし、初心者にとっても、佐野さんの魅力をサラッと触れられる感じなのはいいと思います。
で、僕にとってもホント、好きな曲ばかりが集まってる感じで、無駄がないのがお気に入りです。
ちょっと時間がない時に、でも佐野さんを聴きたい、という時に重宝します。
(2024.8.15)
『ROCK & ROLL NIGHT LIVE AT THE SUNPLAZA 1983』
初期の佐野さんのライヴ盤。
BOX『THE COMPLETE ALBUM COLLECTION』に収録のディスクで初めて聴いた。
「バック・トゥ・ザ・ストリート」のアレンジが全然違うので、気付かなかった。
「イッツ・オールライト」はレゲエ風に始まって、途中からスウィング・ジャズのようなグルーヴに。 これまた凝ったアレンジだ。
「サムデイ」までもがアレンジを変えてくるのか!と思ったけれど、最初の方だけだった。
MCで、このライヴはフィルムに残すと言っている佐野さん。
おそらくコレの一部が『FILM NO DAMAGE』として公開されたんだろうけど、やっぱりフル・ライヴの映像が観たいよなあ。
残ってるんでしょ?
「ガラスのジェネレーション」は、「サムデイ」よりも歓声が大きかった。
この当時の人気としては、そういう位置付けだったんだろうか。躍動感に溢れた演奏だ。
「ソー・ヤング」は、学園祭の女王に負けじと、佐野さんもライヴで披露してくれてるのが嬉しい。
「ハートビート」は若さゆえのバラード。
深夜にとどろくサックス・ソロの後は、佐野さんのハーモニカ・ソロが寂しげに響く。
「ロックンロール・ナイト」を聴いてると、佐野さんの純粋無垢な魅力が際立つ。
「悲しきレイディオ」は心踊るイントロではなくて、しっとりとしたピアノのフレーズで始まったのが印象的。
「ハートビート」「R&RN」「レイディオ」は、どれも10分超えで、3曲だけで30分以上の熱演。
しかし、どれも間延びすることなく、めくるめく展開と情熱で惹きつけ、たっぷりと聴かせるんだから圧巻だ。
MCで、このライヴの後に、ニューヨークに旅立つことを宣言する佐野さん。
あまりにもあっさりと言うので、ファンも事の重大さがわかってなかったような節もある。
そして、佐野さんからのお別れの曲で「グッドバイからはじめよう」。
若き佐野さんが一気にファンを増やした、1度目の絶頂期のライヴの模様だ。
MCでの喋り方が、今の佐野さんとはかなり違う。絞り出すような声の出し方だ。
ハートランドの演奏も、佐野さんの魅力を最大限に引き出す。
佐野さんもファンもとにかく若い。
そのほとばしる熱気がヒシと伝わってくる。
(2024.10.10)
『LIVE ‘VISITORS’ 1985』
『THE COMPLETE ALBUM COLLECTION』BOXの中の1枚として聴いたライヴ盤。
衝撃作『VISITORS』を携えて凱旋した佐野さんのツアー。
はたしてファンたちはどのように迎えたのか。
「ウェルカム・トゥ・ザ・ハートランド」は、ブルージーなライヴのオープニング・テーマ。
よく聴くと、ライヴで「悲しきレイディオ」の後半に付け足すことでお馴染みの歌詞とメロディが。
アレンジが違うので、雰囲気も違うけど。
いつもはライヴ終盤で感謝の意をこめて歌ってるものだけど、ここでは始まりの曲に。
「ナイトライフ」はラップ調の歌い方。
早速、『VISITORS』の影響が、以前の曲にも及んでる。
「夜のスウィンガー」はモータウン調で、盛り上がるガールズ・グループのノリになってる。
これも渡米したことでヒントを得たアレンジか。
「シャドウズ・オブ・ザ・ストリート」は聴いたことない曲...。
と思ったんだけど、シングルB面曲で、『Moto Singles』にも入ってるらしいから、聴いたことはあるはず。
アレンジが違うからかな?全然馴染みがない感じだった。
キラキラとした青春ソングに聴こえた。
「ヴィジターズ」は、いくらかテンポが遅く感じる。
ライヴ初披露だというのに、早速原曲とはアレンジを変えてくるのか。
その他の『VISITORS』収録曲も、原曲とはやや違う感じが。
ライヴ用に練り直したか。
「ワイルド・オン・ザ・ストリート」は、演奏にキレがあり、とにかくファンキー。
パーカッションの音も生々しいノリが特筆もので、ホーンに煽られて、佐野さんの熱も上がっていく。
『VISITORS』収録曲の中では、やはり目玉は「コンプリケイション・シェイクダウン」。
新曲なのに、既に手慣れた感じの演奏。
ヒップホップ・サウンドだけれど、ファンク色を強めたことで、今までの佐野さんの曲の延長線上にあることが、よりわかる。
ライヴでラップを聴くのは、おそらくほとんどの人が初めてだったんじゃないかと思うけど、大きな戸惑いはなく、興奮している観客の様子が伝わってくる。
「アンジェリーナ」は、まさかのスロー・ヴァージョン。
あの疾走感はどこへやら。
これまたヒップホップ的なサウンドと言ってもいいのかな。
歌い方も、ややラップ調。
ちょっとダークな仕上がり。
『VISITORS』を受けてのツアーなので、これまで、ライヴ全体がヒップホップ的な方向に向かっていたけれど、ラストの「ヤングブラッズ」だけは、原曲そのまんまのアレンジで安心感。
しかし、それもそのはず。この曲はこの時点では最新シングルだった。アレンジ変えてないのは当たり前か。
でも、新曲を最後に持ってくるあたり、佐野さんの自信の表れ。
しかも、それがホントにお客さんのウケが良くて。
当時、いかにこの新曲がファンに愛され、求められていたかが手に取るようにわかる。
そういったわけで、ライヴ全体を覆う、ヒップホップの空気。
しかし、その新しいサウンドを、いかに既存のお客さんに違和感なく受け入れてもらえるか、アレンジを工夫した跡が見える。
新旧が融合した音世界は、多くのファンを魅了した。
『VISITORS』を聴いて、その変貌ぶりに失望したファンも多かったと聞いているけれど、このライヴを観れば、そんなファンでも納得がいったのではないだろうか。
(2024.10.13)
『HEARTLAND』

初期の佐野さんのレコードはかなり集まったと思ったけれど、この2枚組ライヴ盤のことを忘れていた。
店頭でも見かけたことないし、高額なレア盤となってるのだろうか。
デビューから8年、なかなかいいタイミングでのライヴ盤のリリースだったのではないだろうか。
ハートランドとの信頼関係もバッチリで、レパートリーも幅広い。
ベスト盤みたいな感覚で聴ける。
唸るビートの「アンジェリーナ」。
終始サックスが絡んでくるサウンドが爽快な「ワイルド・ハーツ」。
「君をさがしている」は速射砲のような佐野さんの歌声はラップ並み。
バラードの「ハートビート」は原曲ほどの重たさはなく、程好い軽さの演奏と歌声に注目だ。
衝撃的なのが「コンプリケイション・シェイクダウン」。
あのクールでヒップな名曲が、ここでは明るいコードで全然違う味わい。
楽しい曲になっちゃってる。
原曲が好きすぎるので、複雑な心境ではあるけれど、これはこれで面白い試み。
ハートランドはこういうことだって出来る、とでも言いたげだ。
「ニューエイジ」の演奏は尖ってなくて優しい。
なのに佐野さんが気合いの入った歌い方なのが対照的だ。
「インディビジュアリスト」のスカ・ファンクのリズムは好きすぎる。
いつ聴いても心が跳ねるが、ライヴ・ヴァージョンだとさらにテンション上がる。
「ドゥー・ホワット・ユー・ライク」はスウィング・ジャズでお洒落なグルーヴ。
「プリーズ・ドント・テル・ミー・ア・ライ」はガラリと変わってブルースっぽいアレンジ。
「ロックンロール・ナイト」はいつもにも増して、ベース・ラインが強調された演奏。
ハイライトでの佐野さんの絞り出すようなシャウトがかなり長くて凄い。
前曲から間髪入れずカウントが入って「サムデイ」が始まる時の興奮。
「ガラスのジェネレーション」はバラードっぽいアレンジ。
佐野さんは初期の頃から、ライヴではアレンジを変えて演奏するタイプのアーティストだということを実感した。
ボブ・ディランほどではないけれど、時々、慣れ親しんだ名曲を、ガラリと雰囲気違えて演奏することがある。
それでたまにガッカリすることもあるけれど、同時に、音楽の奥深さを知ることにもなる。
バンドとしてのピークと、ヴォーカリストとしての最初のピークはこの頃だったんではないだろうかと思わせるライヴ盤。
(2024.10.18)
『SOMEDAY Collector’s Edition』
発売20周年を記念してリリースされた『SOMEDAY』のデラックス盤。
本編は置いておくとして、今回はボーナス・ディスクの楽曲を聴いた。
アルバム未収録曲や別テイクなど、レアなものが光り、なかなかの味わい。
「シュガータイム」はシングル・ヴァージョンのモノ・ミックス。
ステレオとかモノとか、僕にはあんまり違いがわからないけど、大好きな曲での幕開けは本編と同じ。
「スターダスト・キッズ」はオリジナル・ヴァージョンということで。
イントロの瑞々しいハーモニカが印象的だけど、全体的にはラフで、ちょっとチープにも思えるくらいシンプルな演奏。
しかしそれ故、ライヴ感を感じる疾走感と迫力がある。
「バイ・バイ・ハンディ・ラブ」も「ソー・ヤング」もオリジナル・ヴァージョン。
これらも「スターダスト・キッズ」と同じ印象のサウンド。
これら3曲のオリジナル・ヴァージョンというのは、シングルのB面曲に収まってたヴァージョンそのものなのかな?
「ワンダーランド」が一番の目玉か。
シングルのB面曲で、ここで初のCD化。
冒頭の佐野さんのシャウトがテンション高い。
甘くキャッチーなメロディで、コーラス・ワークも楽しい、ビートルズやマージー・ビート風のオールド・タイプのロックンロール。
佐野さんにしては珍しく全編英語詞で、洋楽のカヴァーなのかなと思ってしまうほど。
「マンハッタンブリッヂにたたずんで」は『ナイアガラ・トライアングル VOL.2』収録のそのものかな?
「ダウンタウンボーイ」は、オリジナル・ヴァージョンとの説もあるし、ベスト盤『20th Anniversary Edition』に収録の99年リミックス・ヴァージョンという説もある。
「サンチャイルドは僕の友達」はアナザー・ミックス。
ここまでの他の曲と違い、シングルとは関係ないこの曲を入れた意味とは。
「シュガータイム」で始まり、「サンチャイルド」で終わるという、本編と同じ構成にしたかったのかな。
基本的には、『SOMEDAY』制作時にリリースされたシングルで、アルバム本編には収録されなかった曲を中心にまとめたのが、このボーナス・ディスクという認識でいいのかな。
オリジナル・ヴァージョンというものが、シングルのB面に収録されたヴァージョンとはまた別のものとなれば、話は変わってくるのだけど、僕はシングルまで集めて聴き比べしたわけではないから、正確なところはわからない。
30分に満たないボーナス・ディスク。
まあ、それでも、本編に収録されなかった曲の数々を振り返るだけでも、いかにこの時期の楽曲制作が充実していたかがわかる。
(2024.8.22)


コメント